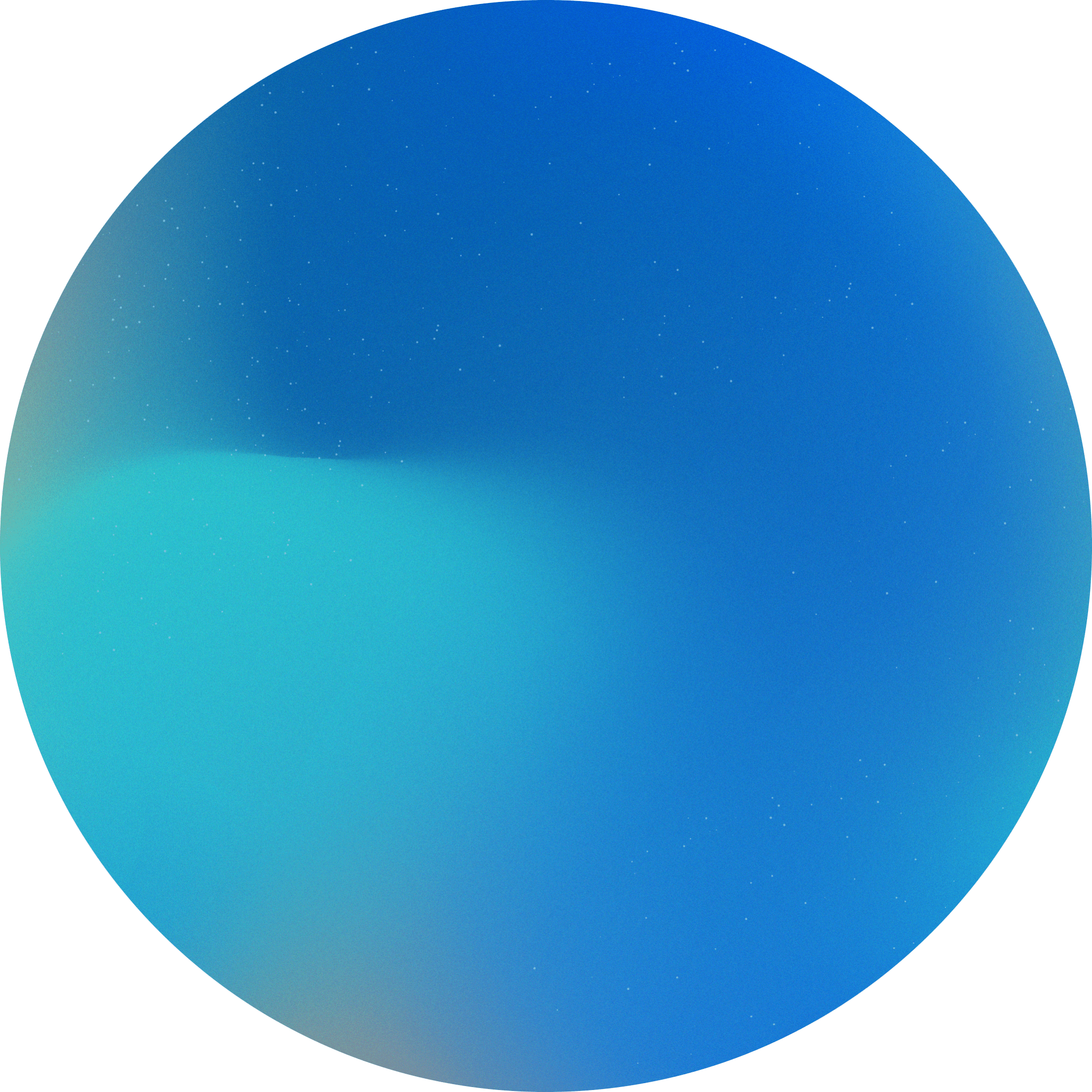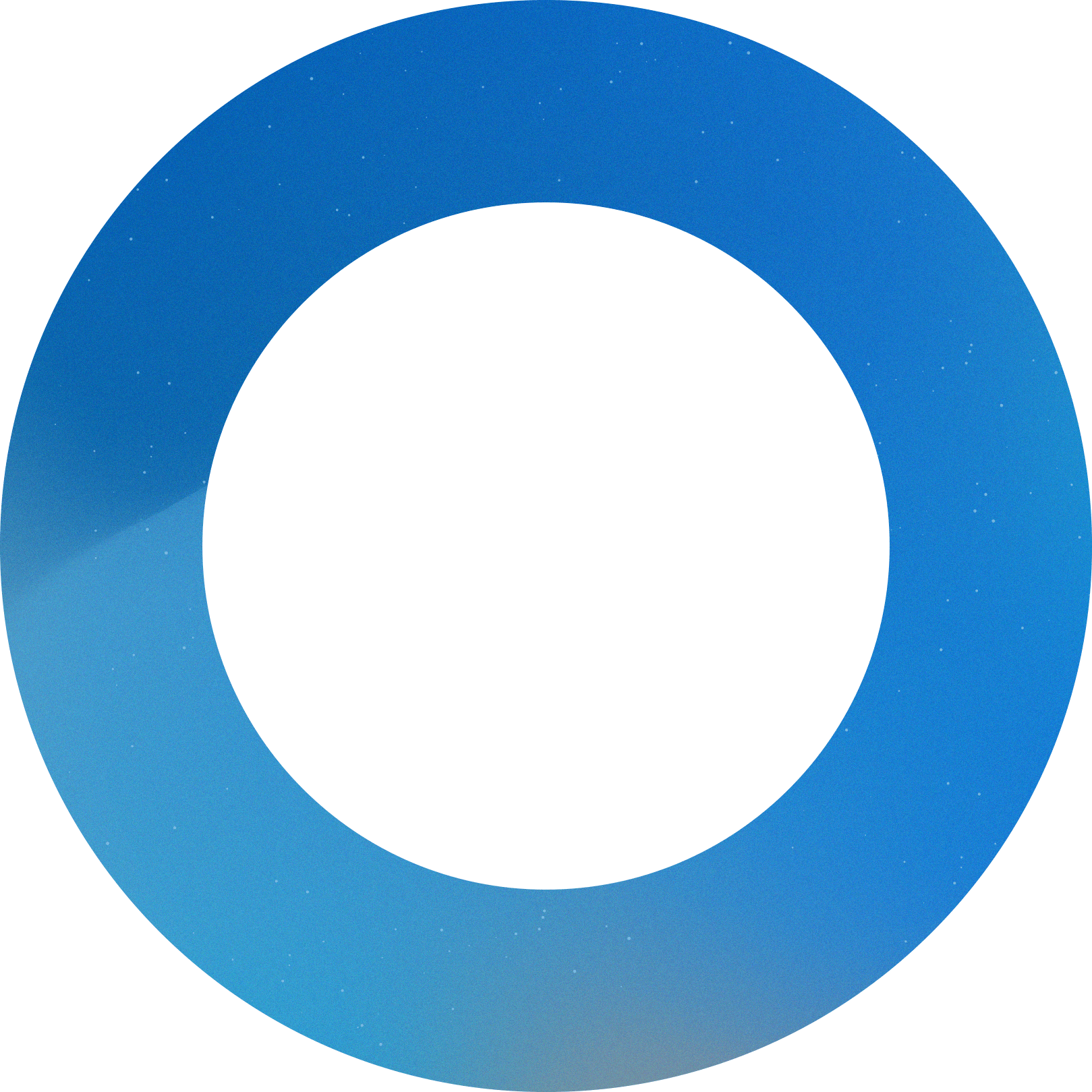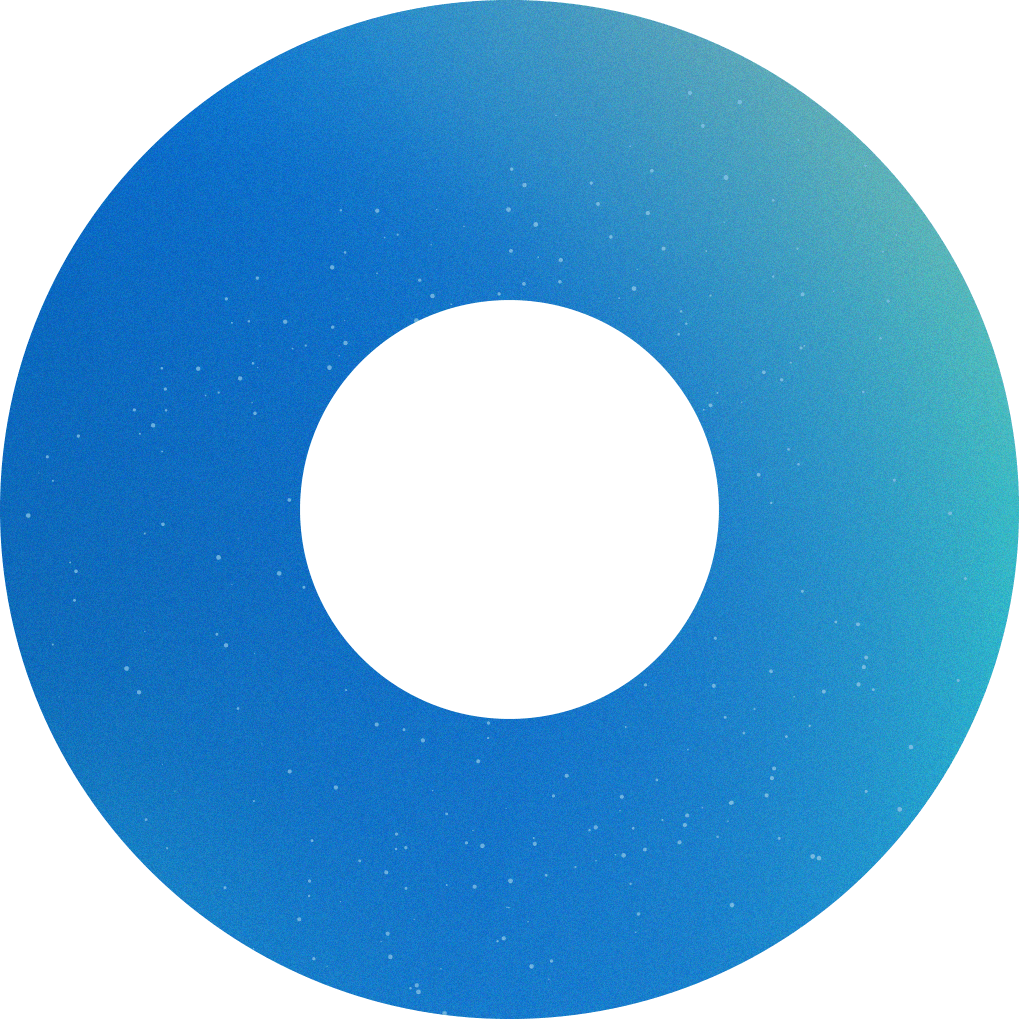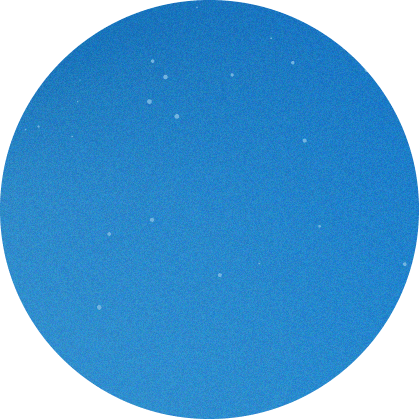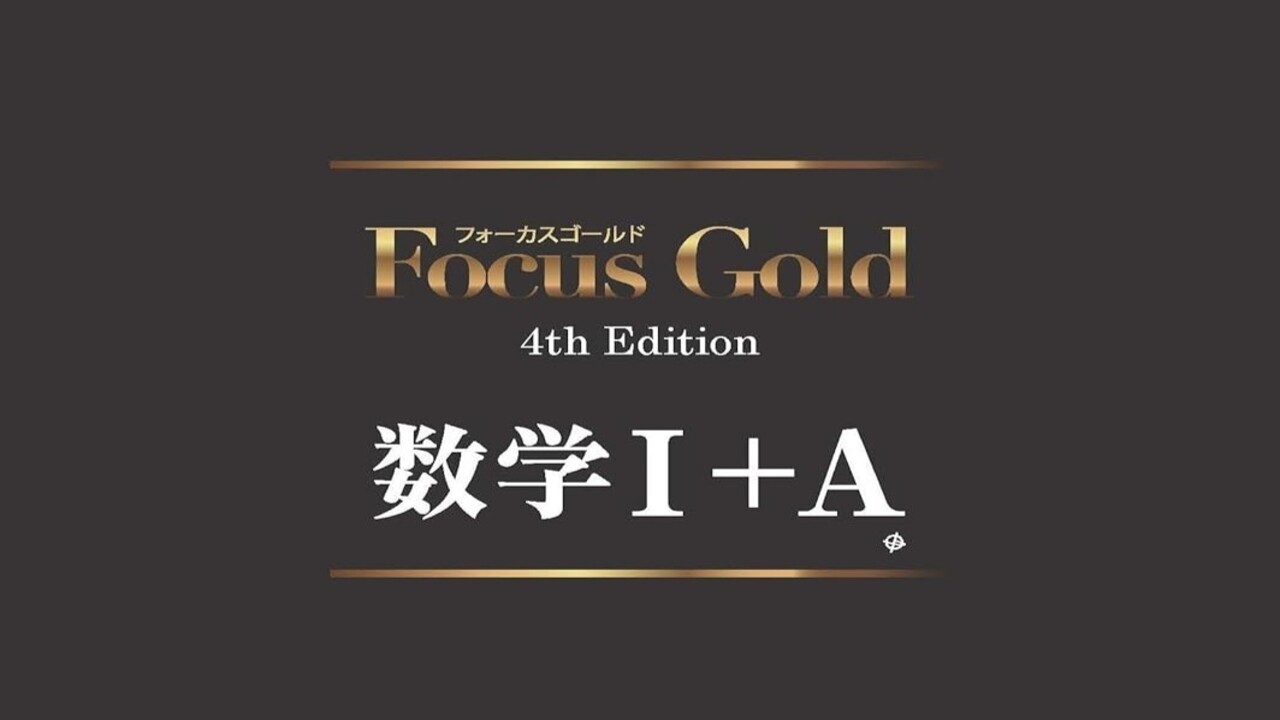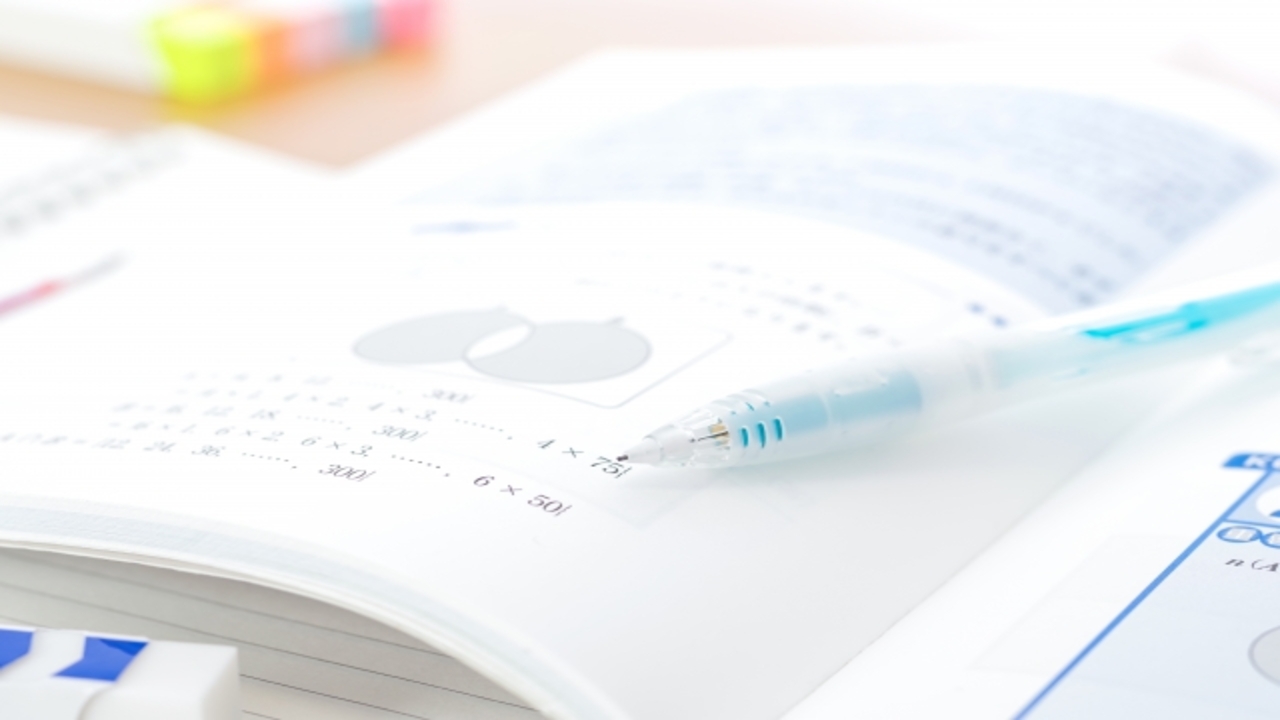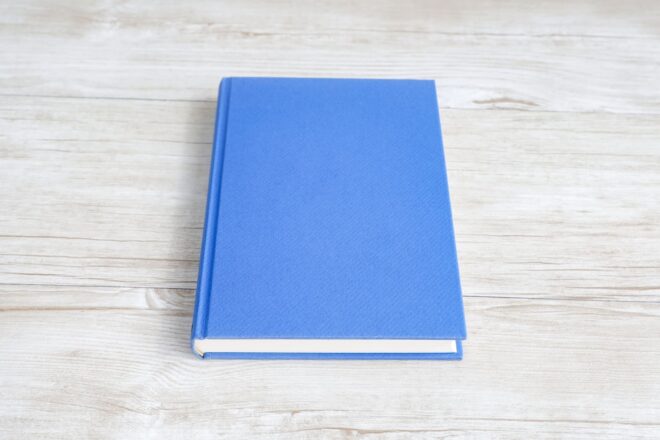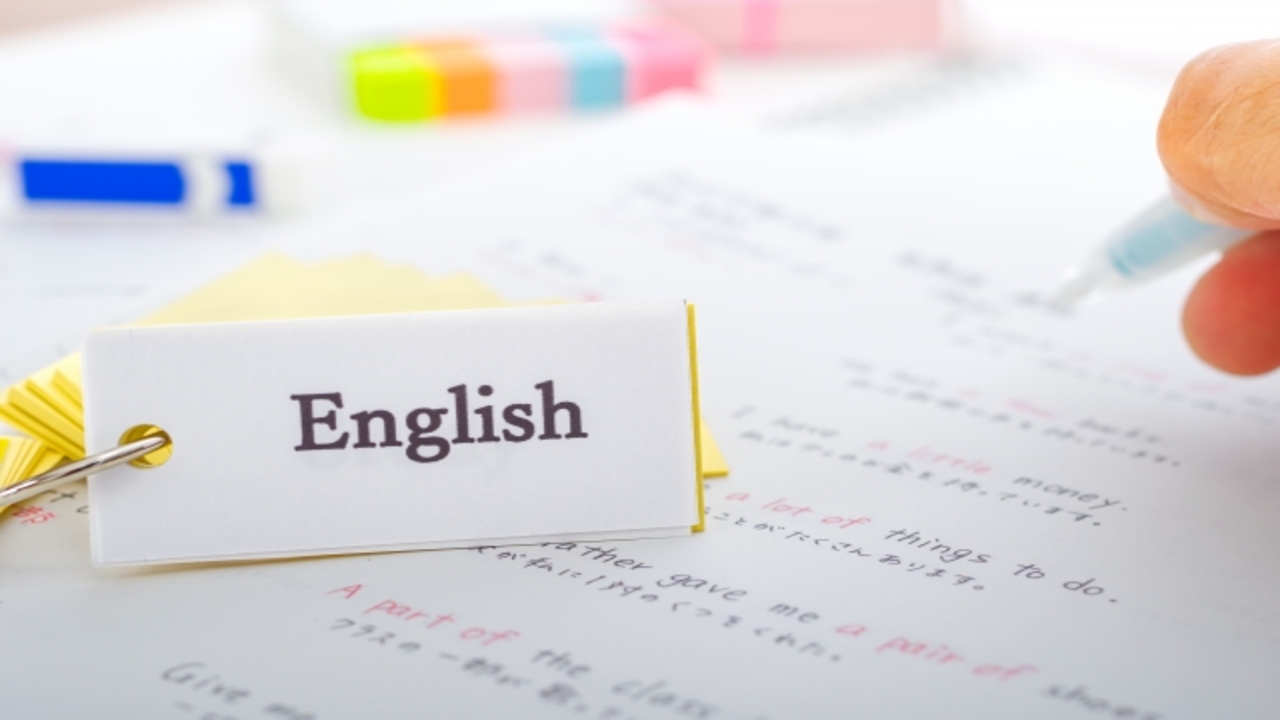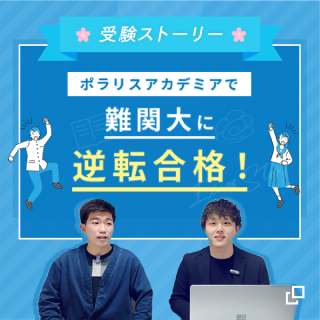古文読解が苦手な人必見!「主語」の見つけ方から始める古文の解き方

1.はじめに:古文読解が苦手なあなたへ
あなたは古文読解に
苦手意識を持っていませんか?
「何となく意味は分かるけれど、
誰が何をしているか掴めない…」「試験
で点数を落とす…」
多くの受験生が古文に苦労しています。
古文読解が難しく感じられる
原因は主に以下の2つです。
-
基礎知識(単語・文法・古典常識)の不足
-
文章中の主語が分からないこと
特に主語の特定は、
省略が多い古文ならではの難しさです。
主語が分からなければ、
登場人物の行動や心情を正確に追えず、
文章全体の理解が難しくなります。
この記事では、古文読解が難しい原因から、
その「解き方」、特に多くの人が苦手とする
「主語の見つけ方」に焦点を当てて解説します。
古文読解への苦手意識を克服し、
得点源にできるようになるための
具体的なステップを掴んでいただければ幸いです。
2.なぜ古文読解は難しいのか?よくある課題
古文読解が難しいと感じるのには、
いくつかの理由があります。
現代文とは異なる独特のルールや表現が、
理解を妨げることが多いからです。
主な課題としては、以下のような点が挙げられます。
-
主語の省略が多い:
誰が行動しているのかを
文脈から判断する必要があります。 -
単語や助動詞の多義性:
同じ言葉でも複数の意味を持つため、
適切な意味を選ぶのが難しいです。 -
現代語との感覚の違い:
敬語や表現のニュアンスが現代とは異なります。 -
文章構造の違い:
単語間に明確な区切りがなかったり、
現代語のように論理的に
分解・再構築しにくい場合があります。
参考資料でも、
「単語間に隙間がない」
「文章を情景として捉えにくい」
といった点が難しさとして挙げられています。
単に単語や文法を覚えるだけでなく、
文章全体を立体的に理解する必要があるため、
難しく感じてしまうのです。
これらの課題に対処するための
「解き方」について、
次の章から具体的に見ていきましょう。
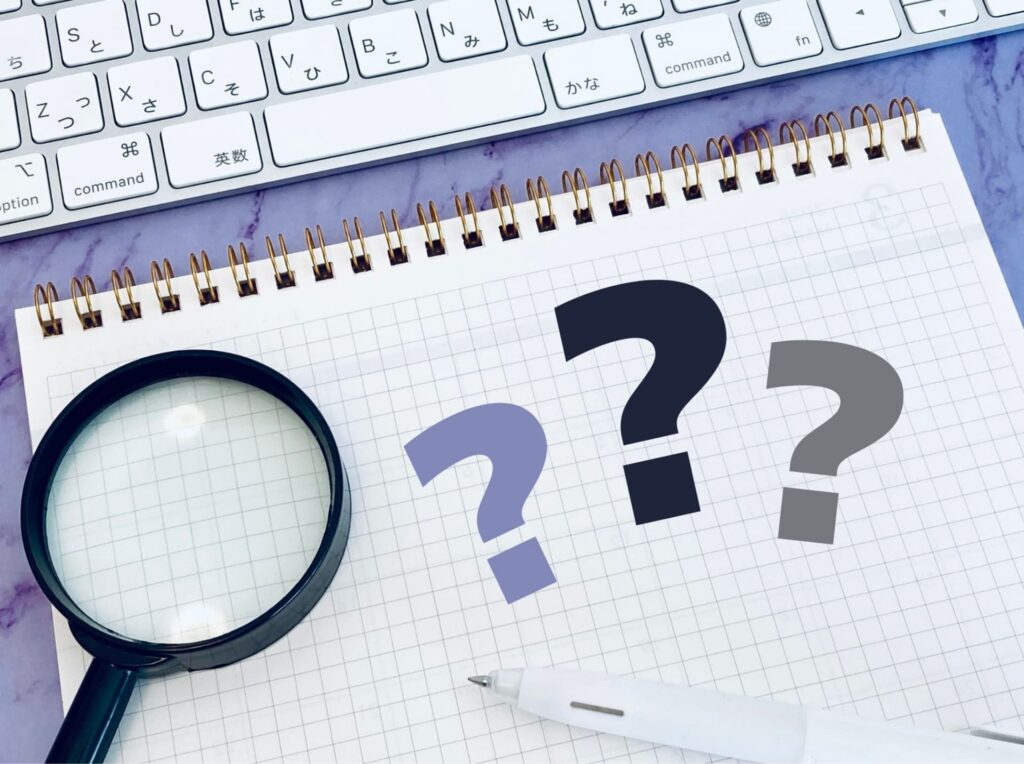
3.古文読解の「解き方」全体像と効率化の視点
古文読解では、
限られた時間内に正確に内容を把握し、
問題を解くことが求められます。
特に受験においては、
15分から20分という短い時間で
古文を解き終える必要があります。
そのため、効率的な「解き方」を
身につけることが非常に重要になります。
効率化のためには、以下の点を意識しましょう。
-
時間配分: 全体を完璧に理解しようとせず、
限られた時間で最大限の情報を引き出す。 -
全体像の把握: まず問題を確認し、
本文を読む前に何が問われているのかを把握する。 -
基礎知識の活用: 単語・文法・古文常識
といった基礎知識を速やかに適用する。
|
手順の概要 |
効率化のポイント |
|---|---|
|
1. 問題の先読み |
設問から本文のテーマや |
|
2. 単語・文法問題 |
本文読解前に解ける問題で |
|
3. 本文読解 |
主語補填などを意識し、 |
これらの視点を持つことで、
古文読解のスピードと精度を
同時に向上させることができます。
4.最重要!主語を見つけるためのステップとテクニック
古文読解で最もつまずきやすい
ポイントの一つが「主語」の特定です。
誰がその動作をしたのか、
誰がそのセリフを言ったのかが分からなければ、
文章全体の意味や
登場人物の心情を
正確に理解することはできません。
主語を見つけるための
基本的な考え方は、
「ある動作やセリフが、
いったい誰のものなのか」を
常に意識することです。
特に、敬語表現(尊敬語、謙譲語、丁寧語)は
主語や目的語・補語を判断する上で
重要なヒントになります。
例えば、尊敬語が使われていれば、
動作の主体(主語)は
話し手や書き手より身分が高い
人物である可能性が高いと考えられます。
本文を読み進める際には、
以下のような点を意識すると
主語を見つけやすくなります。
-
登場人物の確認: 誰が登場しているのかを
最初に把握しましょう。 -
敬語のチェック: 誰に対する敬語か、
誰の動作に尊敬語が使われているかを
確認します。 -
会話文の前後: 会話をしている人物が
誰かを文脈から判断します。 -
動作の主体: その動作をするのが
自然な人物は誰かを考えます。
これらのテクニックを意識しながら、
積極的に主語を特定する
練習を重ねることが、
古文読解力向上の鍵となります。
5.読解を支える基礎知識(単語・文法・古典常識)
古文の読解をスムーズに進めるためには、
いくつかの基礎知識が不可欠です。
単語、文法、そして古典常識は、
文章の意味を正確に把握し、
内容を深く理解するための
土台となります。
特に重要なのは、以下の3点です。
-
単語: 現代語とは異なる意味を
持つ単語が多く存在します。
単語の意味を理解することで、
文章の具体的な内容を
イメージしやすくなります。
単語帳の豆知識なども活用しましょう。 -
文法: 古文の文法は、
現代語とは異なる活用や
接続のルールがあります。
文法を理解することで、
文章の構造や修飾関係を
正確に把握できます。
教科書の付録などを参考に、
活用などを覚えましょう。 -
古典常識: 時代背景や当時の文化、
習慣に関する知識です。
これを知っていると、
物語の登場人物の行動や心情、
出来事の背景などが理解しやすくなります。
過去問の解説なども参考になります。
これらの基礎知識をしっかりと
身につけることが、
古文読解力向上への第一歩となります。
6.実践的な「解き方」のプロセス
古文をスムーズに読み解くためには、
いくつかのステップを踏むことが効果的です。
まず、文章全体に目を通し、
おおまかな内容を把握しましょう。
特にリード文や注釈は、
古典常識や背景理解の助けになります。
次に、一文ずつ丁寧に読んでいきます。
ここで重要なのが、「主語」を意識することです。
誰が(何が)どのような動作をしているのかを
常に考えながら読み進めましょう。
敬語表現も主語を特定する
大きな手がかりとなります。
また、単語の意味を文脈から
判断する力が必要です。
同じ単語でも文によって
意味が異なることがあるため、
前後のつながりをよく見て
適切な訳を選びましょう。
文法知識も活用します。
特に助動詞や助詞は、
文章の意味を正確に
理解するために不可欠です。
品詞分解の練習も有効です。
【古文読解のプロセス例】
-
全体把握: リード文・注釈を確認し、
おおまかな内容をつかむ -
一文精読:
-
主語を意識する(敬語も手がかりに)
-
単語の意味を文脈から判断する
-
助動詞・助詞などの文法を確認する
-
-
内容整理: 人物関係や出来事を
整理しながら読み進める
これらのステップを意識することで、
古文読解の精度が向上します。

7.まとめ:古文読解力向上の道筋
古文読解力を向上させるためには、
まず基本となる知識をしっかりと
身につけることが大切です。
特に重要なのは、以下の3点です。
-
単語: 約300語の頻出単語を中心に、
現代語との意味の違いや
多義語に注意しながら覚えましょう。
単なる暗記ではなく、
語のイメージをつかむことが効果的です。
音読も活用しましょう。 -
文法: 助動詞の意味と活用、
そして識別は古文読解の要です。
活用表をリズムで覚えたり、
品詞分解の練習をしたりすることで、
文の構造を正確に捉える力がつきます。
特に、試験で頻出の「ぬ」「る」「なり」の
識別はマスターしたいところです。 -
古典常識: 当時の文化や価値観を知ることで、
登場人物の行動や心情の背景が
理解できるようになります。
これらの基礎知識を土台に、
主語を意識して補いながら
文章を読む練習を重ねましょう。
最初から完璧を目指さず、
少しずつ着実に学習を進めることが、
古文読解力向上の道筋となります。