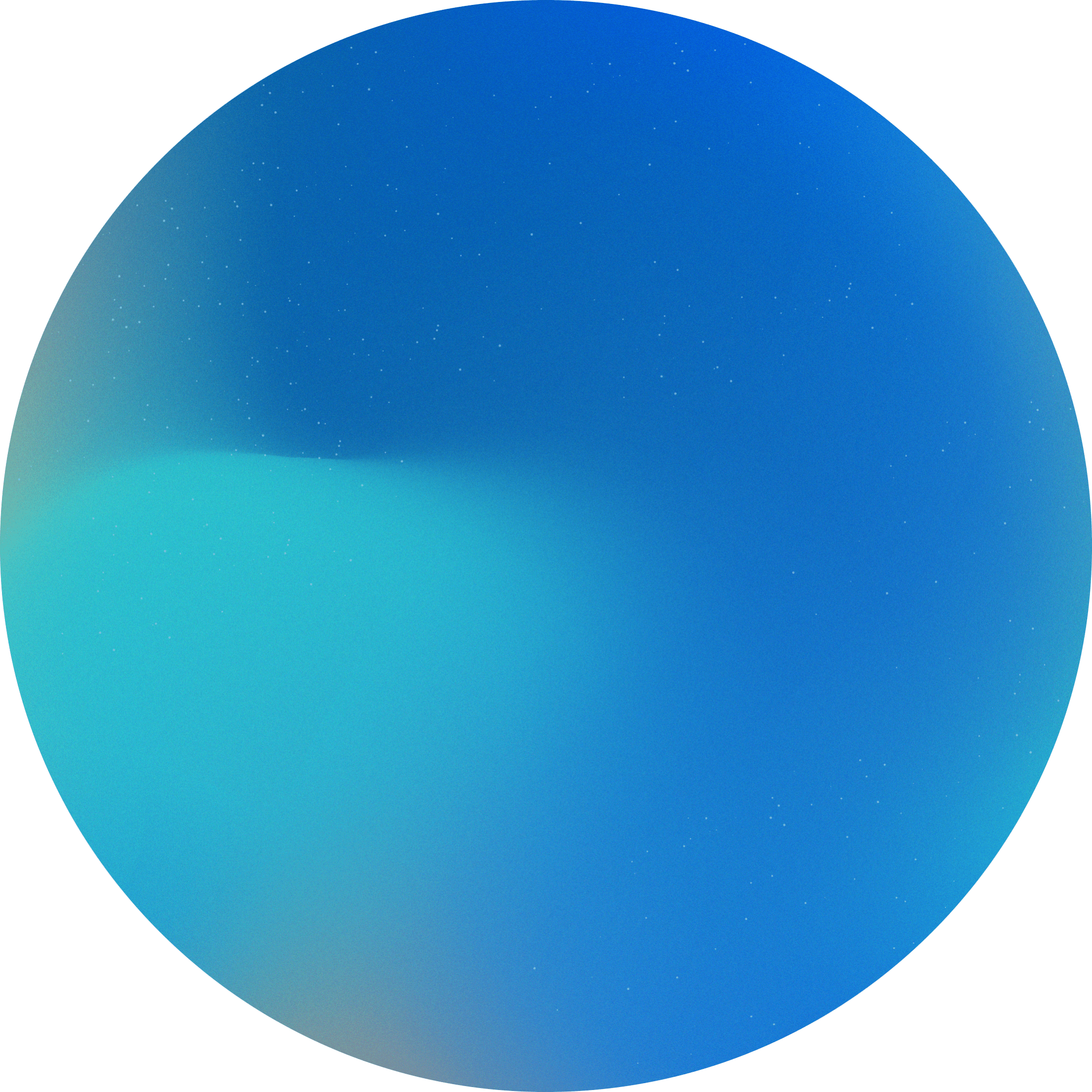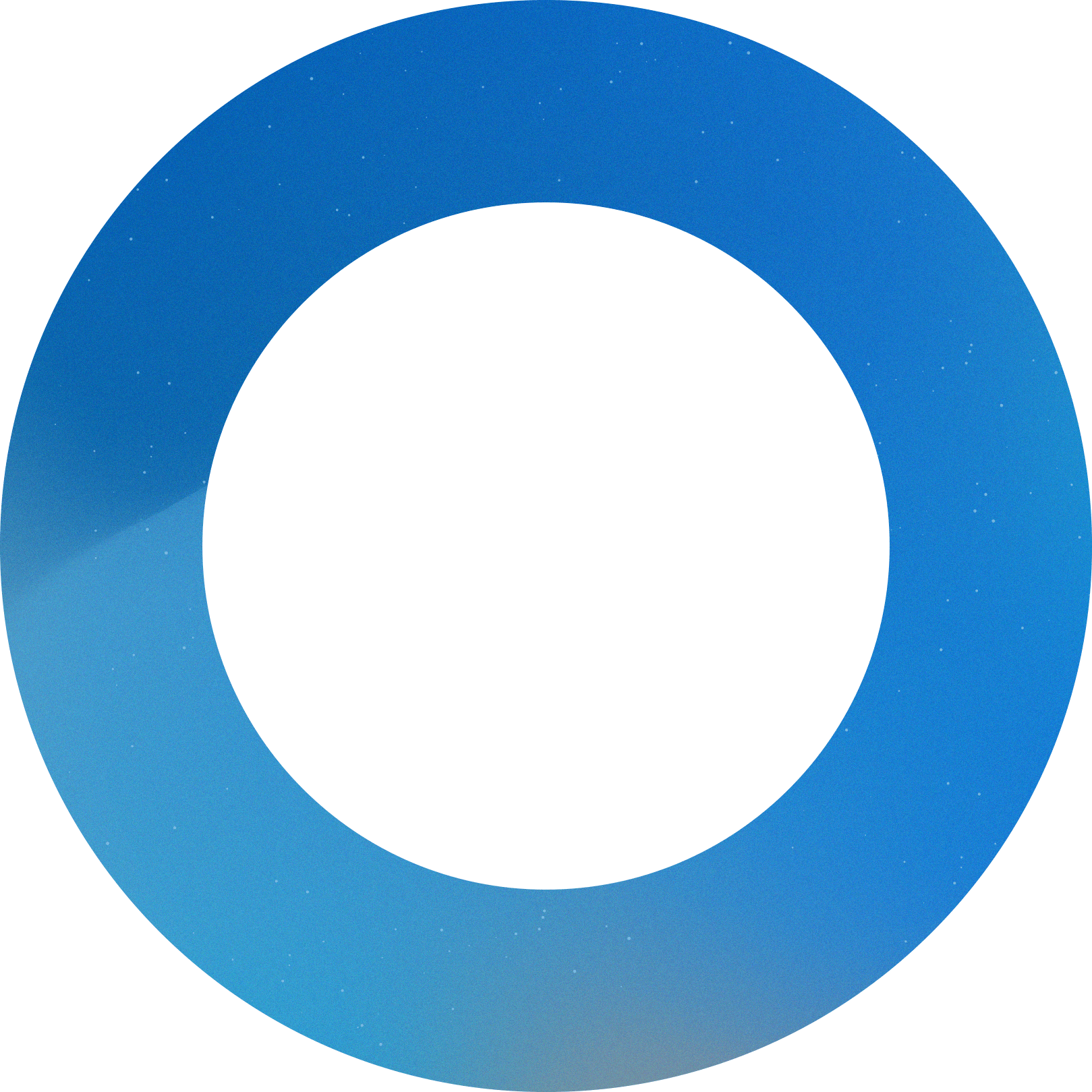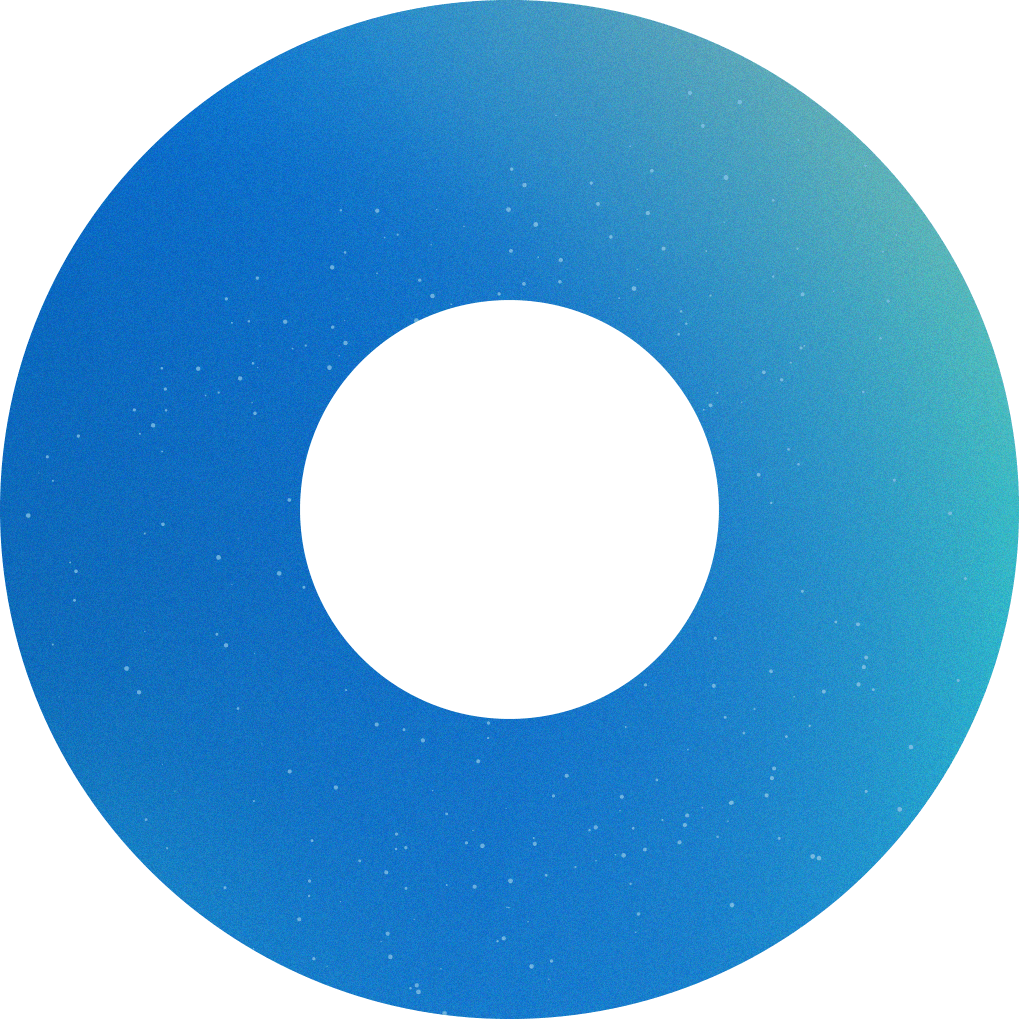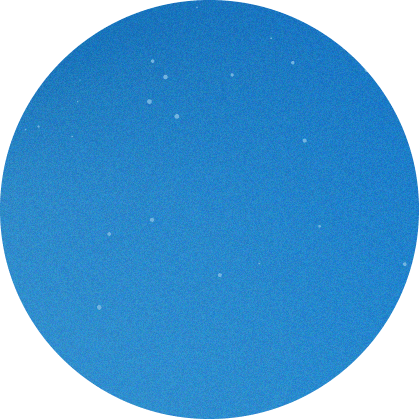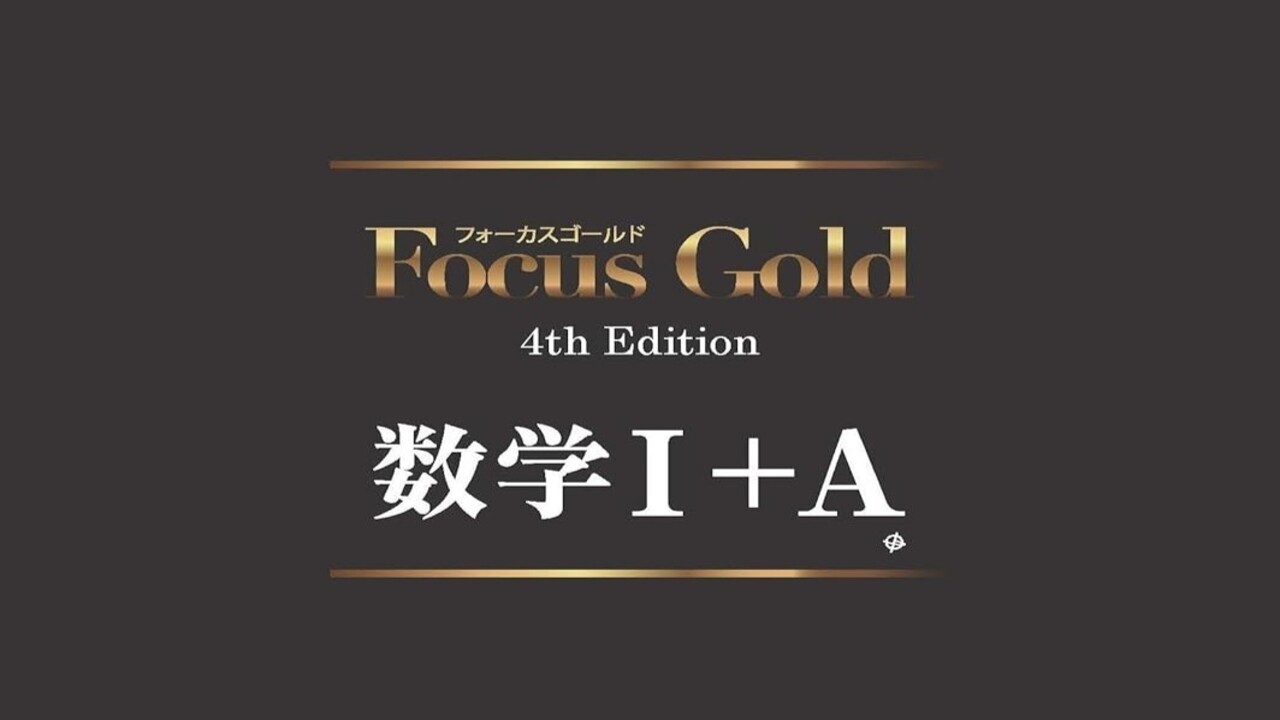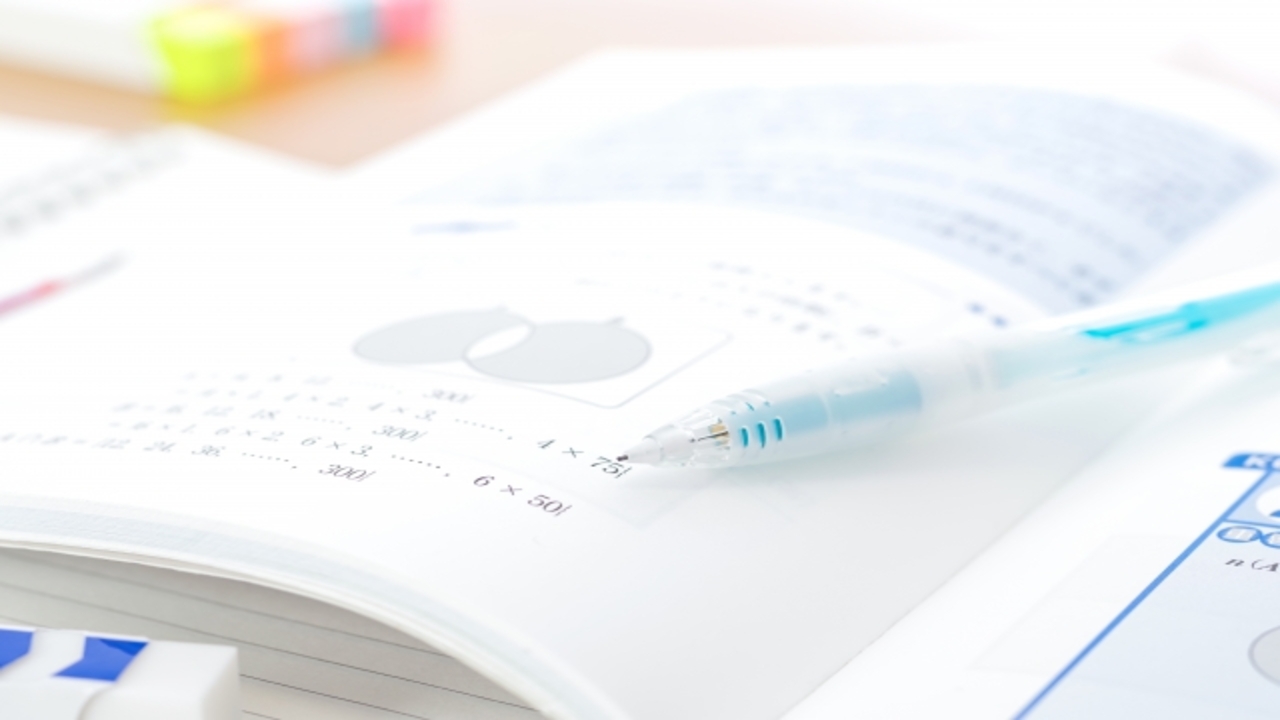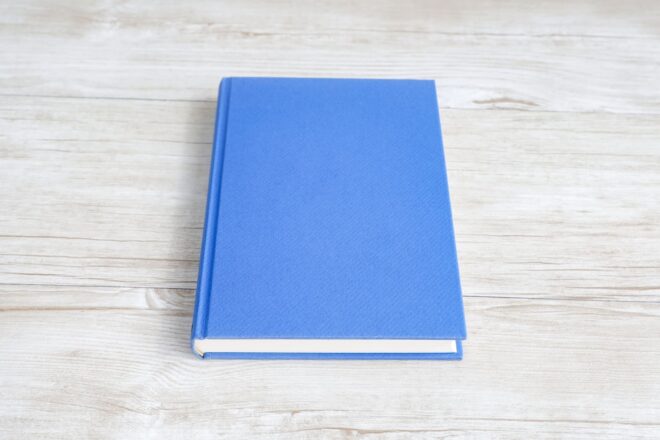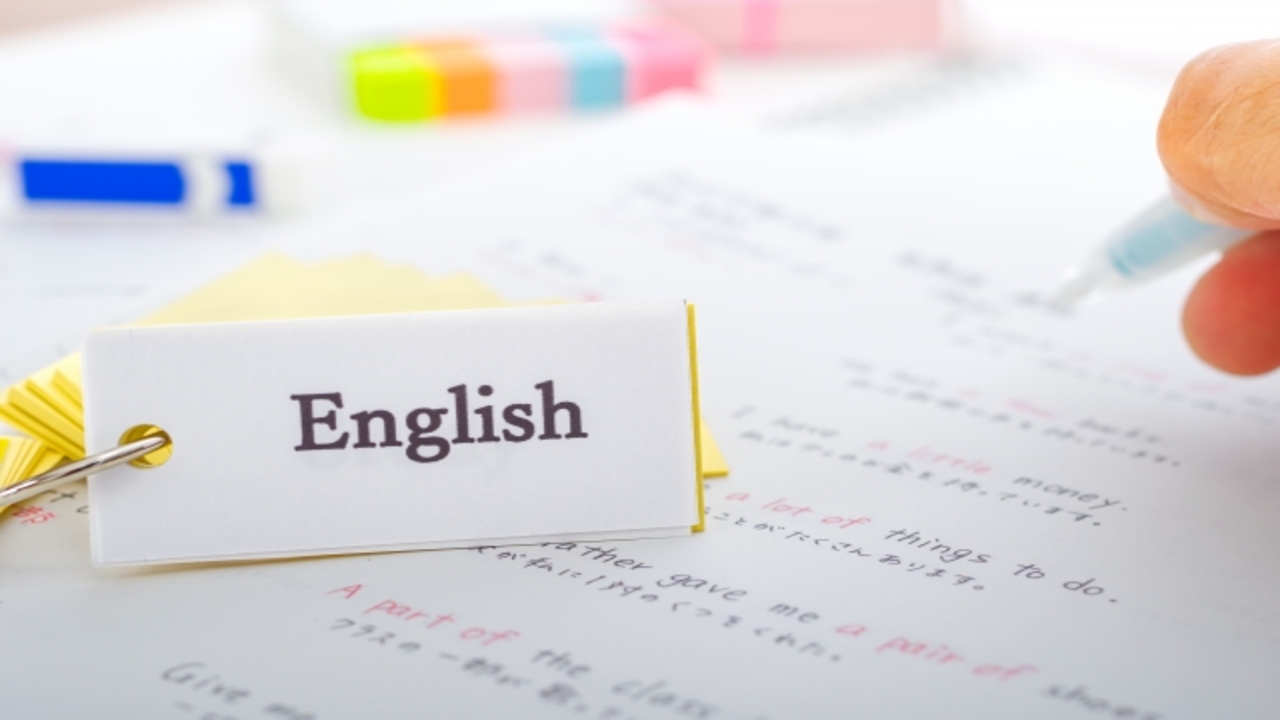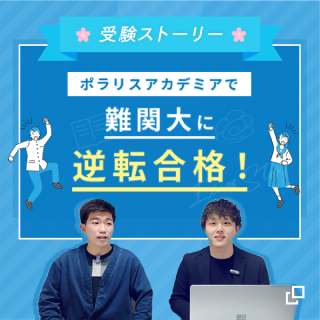新高3生の皆さん、いよいよ受験本番の1年が始まりますね。特に小論文を課す大学を志望している人にとって、小論文対策をいつから、どのように進めるべきかは大きな悩みの一つです。
「書くのが苦手…」「何から始めればいいかわからない…」と不安を感じている人も多いかもしれません。しかし、小論文はしっかりとした準備をすれば確実に力がつく科目です。
本記事では、新高3生がスムーズに小論文対策を進められるように、基礎固めから実践的な練習方法まで、具体的なステップを詳しく解説します。
1. 小論文対策は「読む」「考える」「書く」の3ステップ
小論文の力を伸ばすには、単に「たくさん書く」だけではなく、「読む」「考える」「書く」の3つの力をバランスよく伸ばすことが重要です。
① 「読む」 – 良い文章に触れて基礎力を養う
小論文は、論理的な文章を読み慣れることが上達の第一歩です。日頃から、新聞の社説や時事問題の解説記事、入試過去問の模範解答などを読んでおくと、文章の組み立て方や論理展開の仕方を学ぶことができます。
【おすすめの読み物】
✅ 新聞の社説(朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞など)
✅ 読解の参考書
✅ 小論文の参考書の模範解答
「毎日読まないといけない」と気負う必要はありません。最初は、週に3~4回、5分~10分程度読むことから始め、徐々に慣れていきましょう。
② 「考える」 – 自分の意見を持つ練習をする
小論文は「自分の考えを論理的に表現する力」が問われます。そのため、ただニュースや時事問題を知るだけでなく、「自分はどう思うか?」を考える習慣をつけることが大切です。
【考える力をつける練習】
✅ ニュースを読んだら、「この問題の原因は?」「解決策は?」と考えてみる
✅ 家族や友人と時事問題について話してみる
✅ 「なぜそう思うのか?」を自分に問いかける癖をつける
例えば、「AIが仕事を奪う」というテーマを読んだら、「AIの導入にはメリットもあるが、デメリットもある。では、そのバランスをどう取るべきか?」と考えてみる。このように、普段から「自分の意見を持つ」練習を積むと、小論文を書く際にスムーズに主張がまとまります。
③ 「書く」 – 実際に文章を作る練習をする
「読む」「考える」力がついたら、いよいよ実際に小論文を書いてみましょう。最初は長い文章を書くのが難しいと感じるかもしれませんが、最初から完璧を目指さなくても大丈夫です。
【小論文を書くステップ】
- 課題文型 or テーマ型 のどちらかを選ぶ(大学の傾向を確認)
- 「序論」「本論」「結論」の3部構成を意識する
- 書き終えたら、文法ミスや論理の流れをチェックする
最初は短めの文章(200~400字)から始め、徐々に600字、800字と書く量を増やしていくのがおすすめです。
2. 小論文対策のスケジュール(新高3生向け)
小論文はすぐに上達するものではないため、計画的に対策を進めることが重要です。以下のスケジュールを参考に、少しずつ学習を進めましょう。
【3~5月】基礎固め(読む・考える・書く練習を始める)
✅ 新聞やニュース記事を読む習慣をつける
✅ 時事問題について「自分の意見」を持つ練習をする
✅ まずは短めの小論文(200~400字)を書いてみる
【6~8月】応用練習(過去問演習を取り入れる)
✅ 過去問を解いて、大学の出題傾向を分析する
✅ 添削指導を受け、改善点を把握する
✅ 600~800字程度の小論文に挑戦する
【9~11月】実践練習(本番を想定したトレーニング)
✅ 試験本番と同じ時間設定で小論文を書く
✅ 「時間内に論理的な文章をまとめる」練習を繰り返す
✅ 志望大学の過去問を重点的に対策する
【12月~本番直前】仕上げ(添削を受けて完成度を上げる)
✅ これまでの課題を見直し、改善ポイントを意識して書く
✅ 過去に書いた小論文を読み返し、自分の成長を確認する
✅ 最後に頻出テーマをチェックして最終確認
このスケジュールに沿って進めれば、無理なく小論文対策を進められます。
3. 小論文対策でおすすめの勉強法
① 1日1テーマについて考える
毎日書くのは難しくても、「1日1つのテーマについて考える」習慣をつけるだけで、小論文の発想力が鍛えられます。
例えば、「日本の少子化対策」について考えるなら、
- 現在の状況(データ)
- 問題の原因
- 具体的な解決策
この3つを意識しながら考えてみると、論理的に整理する力が身につきます。
② 書いた小論文を添削してもらう
独学で対策するのも良いですが、第三者の意見をもらうことで自分では気づかない改善点を知ることができます。
✅ 学校の先生に見てもらう
✅ 塾や予備校の添削サービスを活用する
✅ 友達とお互いの文章を読み合う
添削を受けることで、論理の流れがわかりやすいか、主張が明確になっているかを客観的に判断できます。
③ 志望大学の過去問を早めにチェックする
大学ごとに小論文の出題傾向が異なるため、早めに過去問を確認し、どのような問題が出るのか把握することが重要です。
例えば、
- 課題文を読んで意見を述べる形式
- 社会問題や哲学的なテーマについて論じる形式
- グラフやデータを読み取る問題
このように、大学によって問われる内容が違うので、志望校の傾向に合わせた対策を進めましょう。
まとめ
小論文は、計画的に学習すれば確実に力がつく科目です。新高3生のうちから**「読む」「考える」「書く」の3ステップ**を意識し、段階的にトレーニングを進めましょう。
受験本番に向けて、早めに対策を始めることで、余裕を持って準備できます。ぜひ今日から少しずつ取り組んでみてください!あなたの受験成功を応援しています!