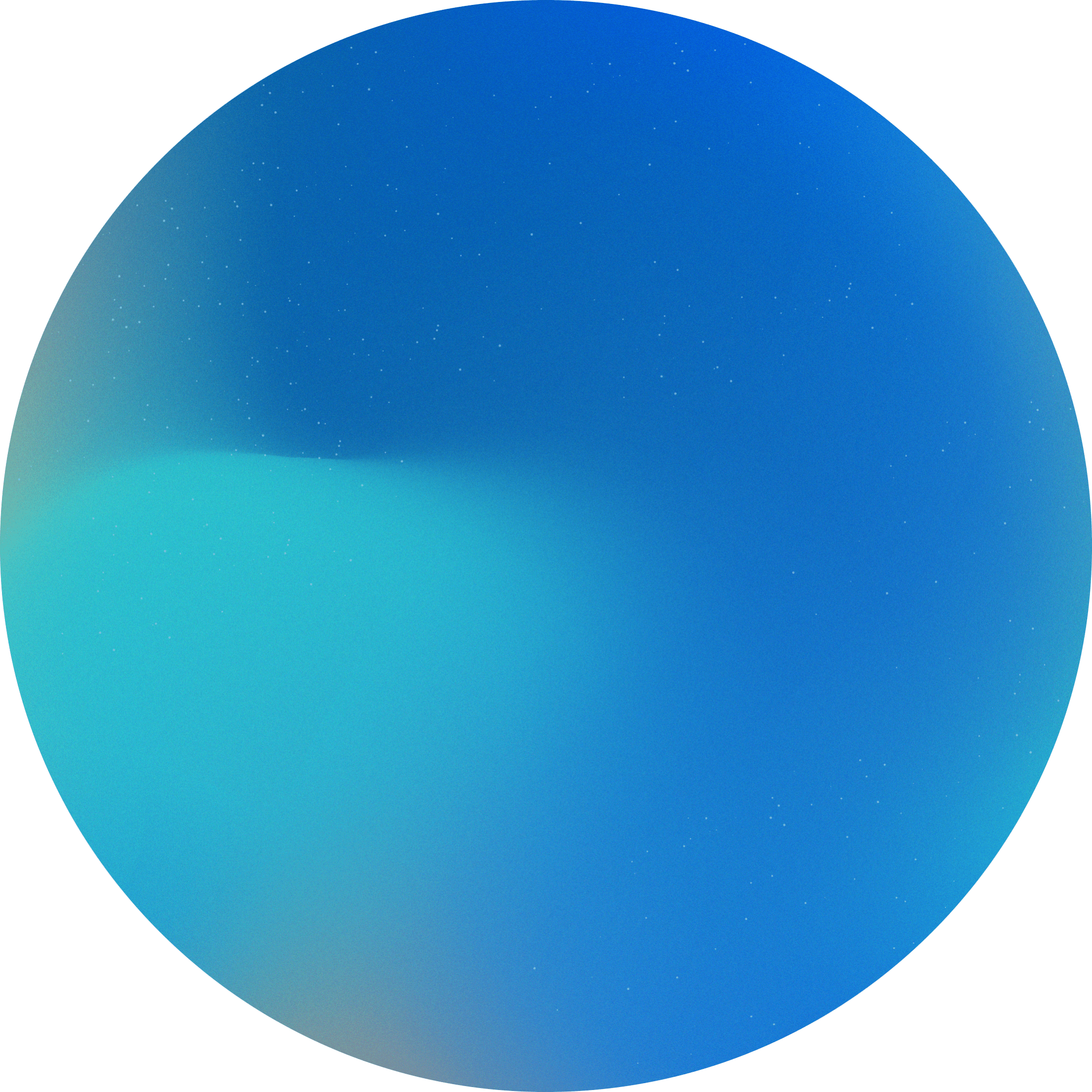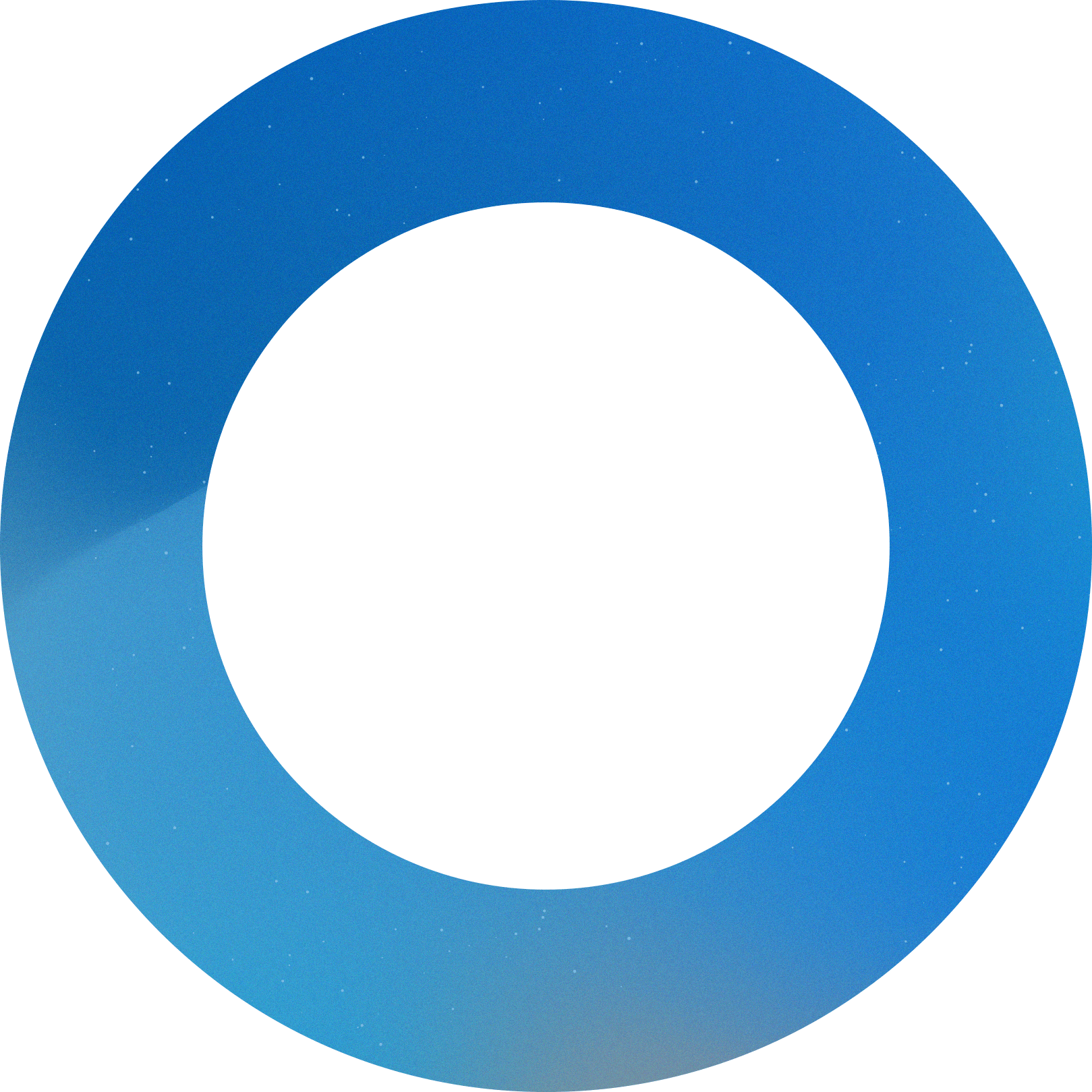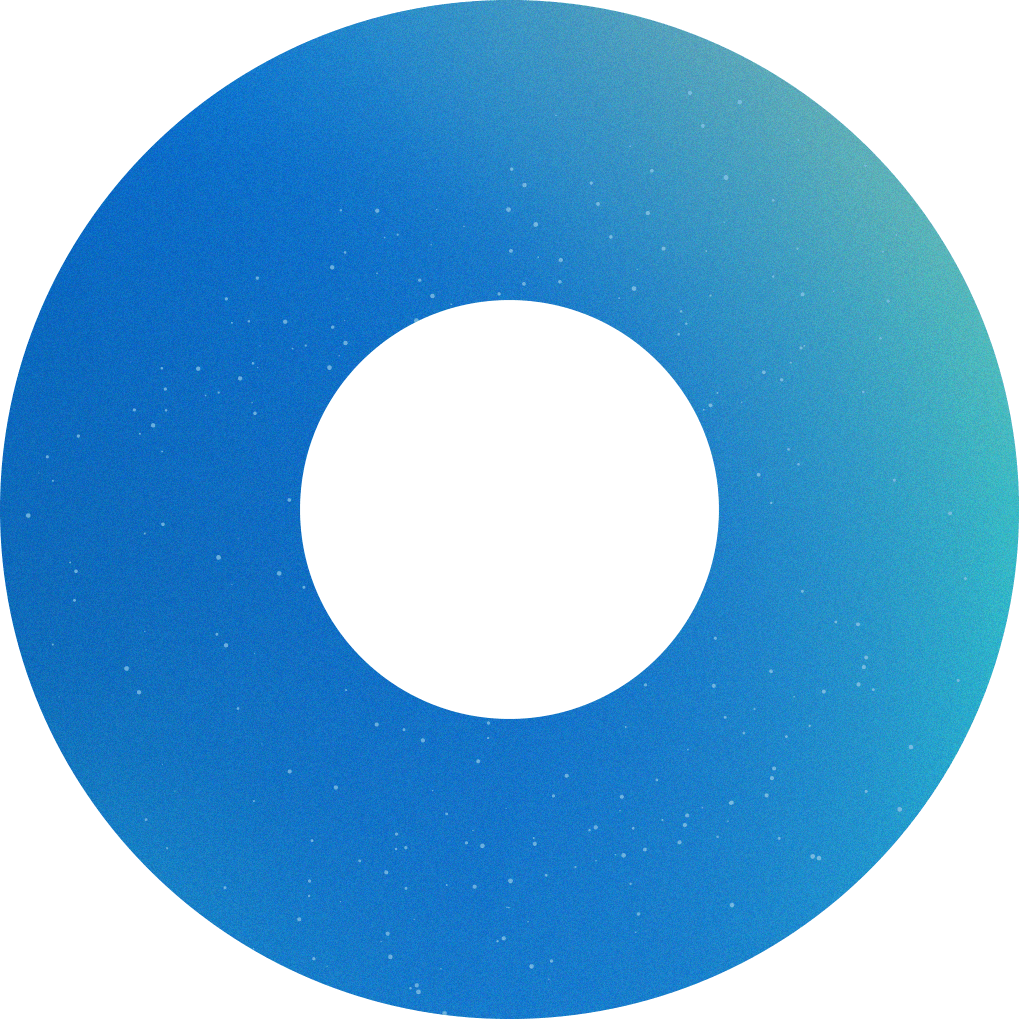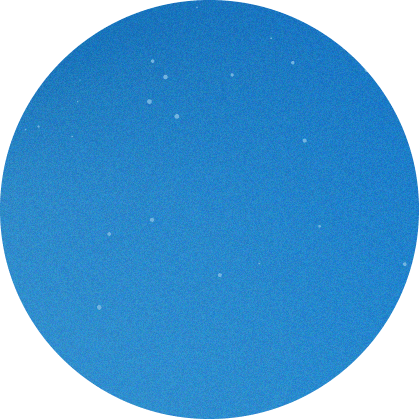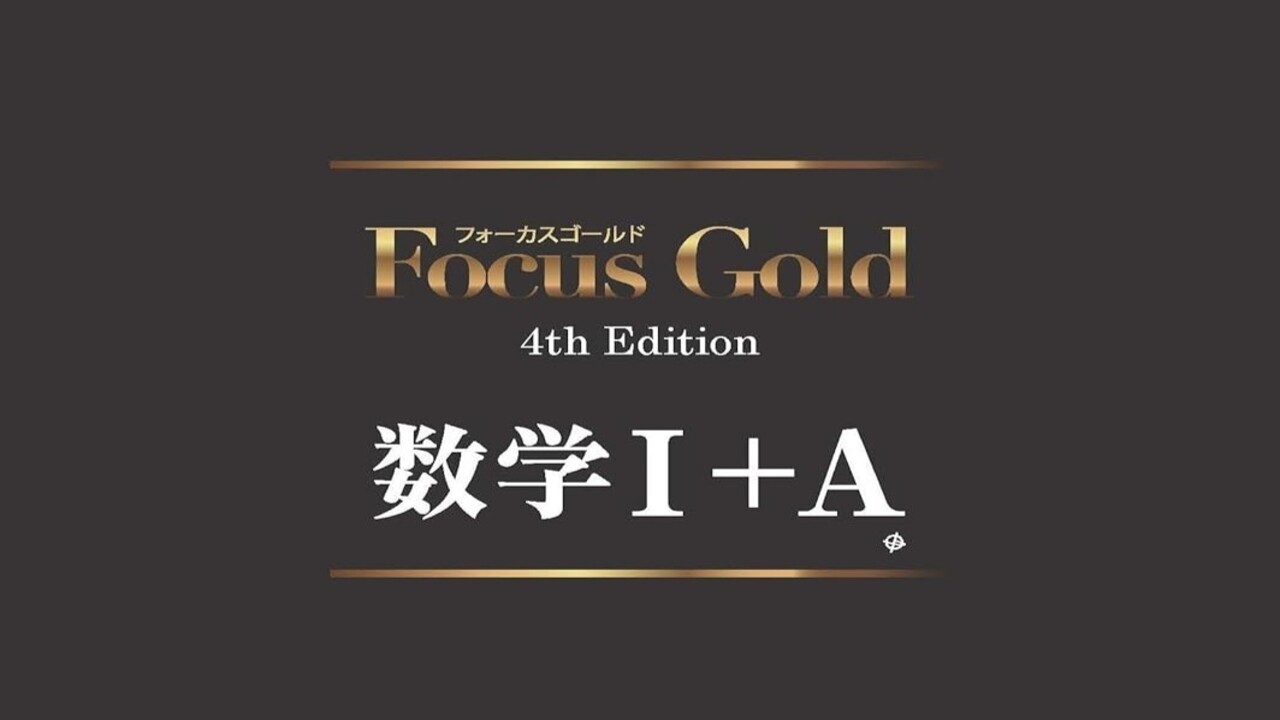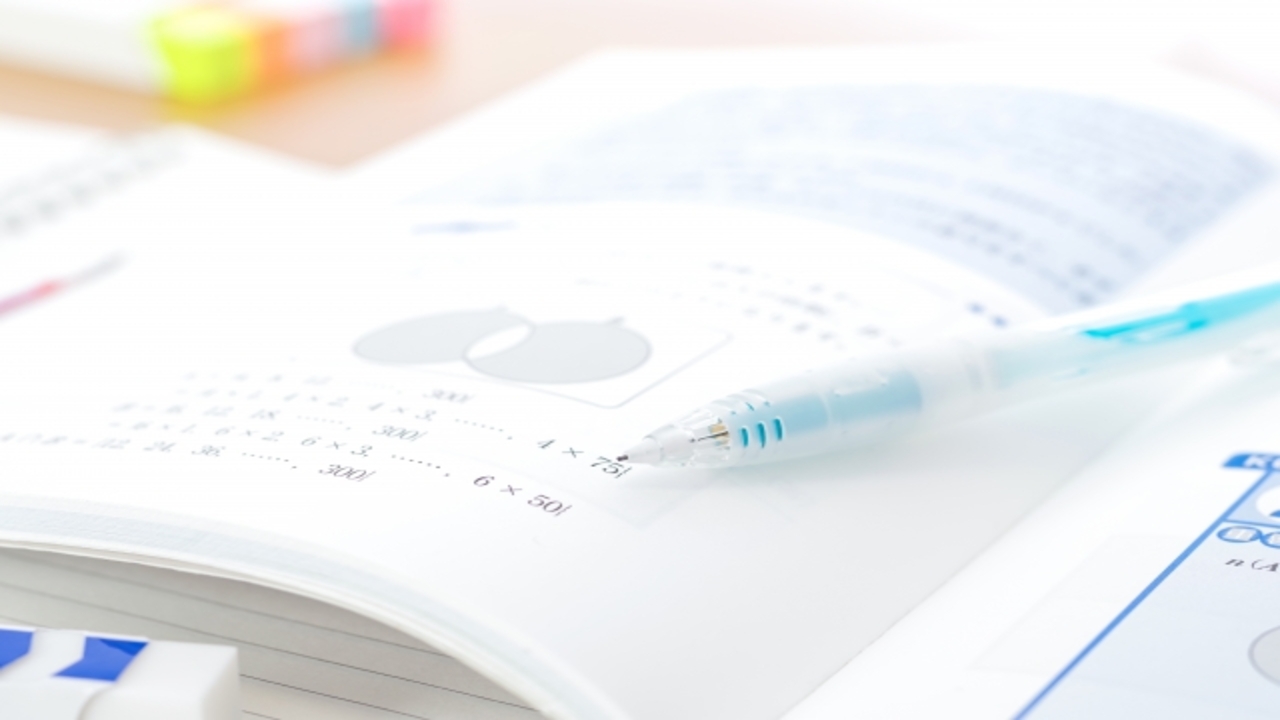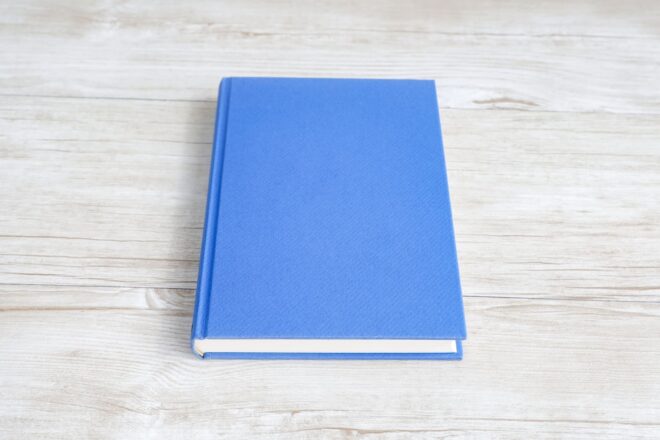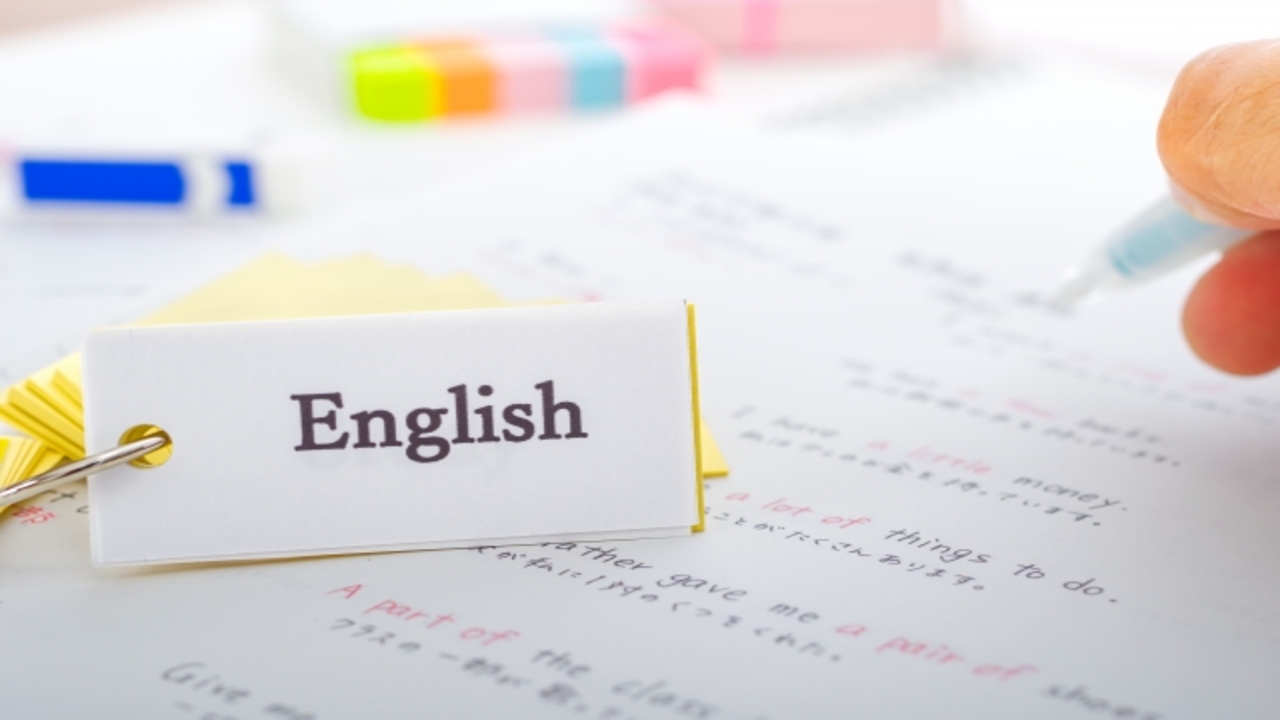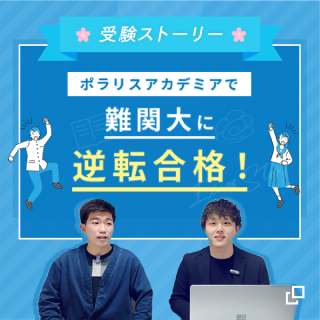基礎問題精講は、高校数学の基礎固めの参考書として多くの受験生に愛用されています。
しかし「例題だけ解けばいいのか」「演習問題もやるべきか」「1日に何問解くのがベストか」など疑問を抱えている人も多いのではないでしょうか。
本記事では、 数学の得点力を飛躍的に伸ばすための基礎問題精講の正しい勉強法や使い方を解説します。
基礎問題精講の正しい勉強法や使い方を実践し、数学の基礎をしっかり固めましょう。
基礎問題精講とは、どのような参考書?
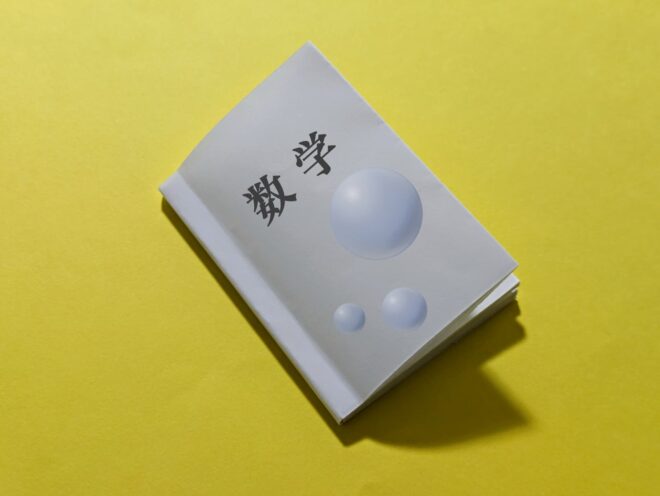
基礎問題精講は、旺文社が出版する高校数学の基礎固めに特化した網羅系参考書です。
数学の基礎的な考察力を身につけることを目的とし、「基礎問」「精講」「解答」「ポイント」「演習問題」の流れで構成されています。
- 基礎問 :入試で頻出の基本問題を厳選
- 精講 :問題を解く際の考え方やポイントを解説
- 解答 :丁寧でわかりやすい解説付き
- ポイント :必ず押さえておくべき知識や公式を整理
- 演習問題 :基礎問の類題を収録し、実践力を養成
基礎問題精講は、基礎力を確実に身に付ける工夫が多いです。
例えば、精講のパートでは問題の背景知識や解法の発想が詳しく説明されているため、単なるパターン暗記ではなく数学的思考力を養えます。
共通テスト対策や日東駒専レベルの入試突破を目指しながら、難関大学の数学問題を解くための基礎力も養えます。
基礎問題精講シリーズには、数学の理解度に応じて「入門問題精講」「標準問題精講」「上級問題精講」のようなステップアップ用の参考書が用意されています。
- 入門問題精講 :数学が苦手な人向けの基礎固め
- 基礎問題精講 :偏差値40~50程度の受験生向けの標準的な問題集
- 標準問題精講 :有名私立や国公立大レベルの問題を収録
- 上級問題精講 :東大・京大など最難関大向けのハイレベル問題集
入門問題精講は、基礎問題精講を終えた後も続けて取り組みやすく、段階的に学習を進められる参考書です。
一方で基礎問題精講と標準問題精講との間にはレベル差があり、スムーズに進めるために別の問題集を挟むこともおすすめします。
基礎問題精講が優れている点

基礎問題精講の最大の強みは、コンパクトな構成でありながら、数学の基礎力を効果的に養える点です。
受験までの時間が限られている人や、青チャートなどの分厚い参考書に取り組むのが苦手な人に適しています。
基礎問題精講をしっかり仕上げることで、以下のような学力を身に付けられるでしょう。
- 日東駒専レベルの入試問題に対応できる
- 教科書レベルの問題をスムーズに解けるようになる
- 共通テストの数学で安定して得点できる基礎力が付く
基礎問題精講は、限られた時間の中で数学の基礎をしっかり固めたい人に最適な一冊です。
ただし、青チャートやFocus Goldなど網羅系の問題集と比べると、収録されている問題数が少ないです。
基礎問題精講だけで、数学の全範囲を完璧にするのは難しいかもしれません。
基礎問題精講を完璧に仕上げた後、追加の問題集で応用力を養う使い方が理想的です。
時間に余裕がある人や難関大学を目指す人は、青チャートやFocus Goldなど演習量が豊富な問題集に取り組むことも良いでしょう。
基礎問題精講の勉強法をおすすめしたい受験生の特徴3つ

数学の基礎固めにおすすめの基礎問題精講ですが、すべての受験生にとって万能な教材ではありません。
基礎問題精講が特におすすめな受験生の特徴は以下の3つです。
- 偏差値50〜55程度で時間をかけずに私立大学の数学対策をしたい
- 偏差値60前後の大学を志望しているが、数学が苦手で効率的に基礎を固めたい
- 現状4〜5割の得点率だが、共通テストで7割を取りたい
自分に当てはまるかどうか、ぜひチェックしてみてください。
特徴1. 偏差値50〜55程度の私立大学を目指す受験生
基礎問題精講は、日東駒専・産近甲龍レベルの私立大学を志望する受験生におすすめです。
入試で頻出の基礎問題が厳選されて収録されており、効率的に基礎固めができます。
問題数が青チャートなどの網羅系参考書よりもコンパクトにまとめられているため、短期間で基礎固めを完了できる点も大きなメリットです。
効率的に基礎を固めたい人には最適な1冊ですが、これだけで受験を突破できるとは限りません。
実際の入試では「基礎+α」の問題が出題されることも多いため、基礎問題精講を終えた後は、過去問演習や標準レベルの問題集で応用力を身に付けましょう。
特徴2. 偏差値60前後の大学を志望しつつ数学が苦手な受験生
数学が苦手な受験生には、いきなり網羅系参考書に取り組むのはハードルが高いかもしれません。
基礎問題精講は、解法の説明が丁寧で「なぜその解き方をするのか」が理解しやすいため、数学に苦手意識を持っている人でも取り組みやすい点が特徴です。
例題と演習問題がセットになっており、「解法を学ぶ→類題で実践する」という流れでスムーズに知識を定着させられます。
基礎問題精講を1周し、基礎的な解法をしっかり定着させたうえで、標準問題精講やFocus Goldなどのステップアップ教材に進むと着実にレベルアップできます。
特徴3. 共通テストで7割を目標にし、現状4〜5割の得点率の受験生
基礎問題精講は、共通テストで7割程度の得点を目指す受験生にも適した参考書です。
共通テストの数学は、基本問題の正確な処理と解法のスピードが求められます。
基礎問題精講は頻出の基礎問題が厳選されており、問題ごとに解法のポイントが整理されているため、共通テストの基礎固めに最適です。
現状4〜5割の得点率の受験生は、基礎問題精講で数学の基本的な考え方を理解し、典型問題をスムーズに解けるようになりましょう。
基礎問題精講の勉強法と正しい使い方3Step

基礎問題精講を解きっぱなしや、やり方を暗記するだけでは、数学の本当の力は身に付かないでしょう。
基礎問題精講の効果的な勉強法と正しい使い方を3ステップで紹介します。
- 講義型の参考書と併用して、教科書レベルの知識を固める
- すべての問題を完答できるようにし、解き直しを徹底する
- 過去問や応用問題で、基礎問題精講の知識を活用できるか確認する
正しい使い方を意識しながら勉強を進めると、入試本番で通用する確かな数学力が身に付けましょう。
Step1.講義型の参考書と併用して、教科書レベルの知識を固める
共通テストや私大、国公立大の個別試験においても、教科書レベルの問題を確実に解けることは入試において必須です。
国語や英語でも、基礎となる語彙や文法の理解ができなければ、どのような試験でも太刀打ちできません。
数学も同じで、基本となる知識が身に付いていないと、いくら演習をしても成績は伸びない可能性があります。
ただし、公式や定理をただ暗記するだけでは不十分です。
公式の意味や成り立ちを理解していないと、新しい問題に対応できず、応用問題が解けません。
基礎問題精講は、参考書というよりも問題集の側面が強いです。
基礎知識が定着していない状態で取り組むと、解法の本質を理解しないまま進み、かえって非効率になってしまいます。
教科書レベルの内容を押さえるために「始めから始める」シリーズや「ひとつひとつわかりやすく」シリーズのような講義型の参考書と併用しましょう。
数学が苦手な人でも理解しやすい構成になっているため、基礎問題精講を解く前の準備として最適です。
ただし、参考書はあくまで一例なので、自分に合った参考書を探してみてください。
Step2.基礎問題精講の全ての問題を完答できるようにする
基礎問題精講には、入試で頻出の基礎レベルの問題が厳選されています。
一冊をしっかり仕上げることで、数学の土台が完成し、入試問題に対応できる実力が身に付きます。
しかし、よっぽど数学が得意な受験生でない限り、最初からすべての問題を完璧に解けるわけではありません。
特に数学が苦手な人は「解説を読んでも理解できない」「間違えた問題がなかなか克服できない」など悩みを抱えることが多いでしょう。
間違えた問題を確実に克服し、解ける状態にすることが大切です。
効果的な復習法は以下を参考にしてください。
- 問題を解く(まずは自力で挑戦する)
- 解説を読む(間違えた問題の解法を理解する)
- 解説を閉じて、もう一度解く(完全に理解できているかチェック)
- 3日後に再チャレンジ(人間は忘れる生き物なので、時間を空けて確認)
問題を解いた後は解説を読んで終わりでは、非常に非効率です。
間違えた問題はその場で理解したつもりでも、しばらくすると忘れてしまいます。
人間の脳は多くのことをすぐに忘れるため、解説をじっくりと読んでも3日後にすべての問題ができるようになっているとは限りません。
解説を閉じた状態で解き直し、完答できるようになるまで繰り返すことで、確実に自分の力として定着させましょう。
Step3.初見の問題でも、基礎問題精講の知識を使って解けるようにする
基礎問題精講の全問題を解けるようになったら、次のステップに進みます。
標準問題精講や過去問演習に取り組み、応用力を身に付けましょう。
実際の入試では、まったく同じ問題が出るわけではありません。
しかし、基礎問題精講で学んだ考え方やポイントは、多くの入試問題に応用できます。
基礎問題精講で身に付けたポイントや考え方を活かして、他の問題集や過去問を解けるようになれば、問題対応力がしっかりと身に付いているといえます。
一方で、正解できない問題も出てくるでしょう。
もし解けなかった場合の対処法は、以下を参考にしてください。
- 間違えた問題のポイントを分析する
- 基礎問題精講の中でその問題と類似の問題を探す
- その問題の解法や考え方を再度押さえる
- 基礎問題精講の問題と間違えた問題との相違点を確認する
- 解説を見ずに正解できるようになるまで繰り返し解く
演習をしていく中で、初見の問題に出会った際に基礎問題精講のどの問題の考え方やポイントを使っているかわかる状態になることが理想です。
入試本番でも「この問題はあの解法を使えば解けるな」と考えられるような引き出しが多ければ多いほど、数多くの問題に対応できるようになります。
基礎問題精講で学んだ解き方やポイントをしっかり身に付けて、過去問や発展問題に取り組んで実践力を鍛えましょう。
基礎問題精講の勉強法、よくある悩み&解決策

基礎問題精講の勉強法や使い方に関するよくある悩みにお答えします。
基礎問題精講は1日に何問解けば効率的?
基礎問題精講は、一般的に1日10〜20問を目安に進めると無理なく学習の基礎を固められます。
進度別の進め方は以下を参考にしてください。
- 時間に余裕がある場合(高1・高2):1日10問ほどをじっくり解く
- 受験学年(高3・浪人生):1日15~20問ペースで進め、演習量を増やす
- 短期間で仕上げる必要がある場合:1日30問以上を解き、1か月ほどで1周する
ただし、ただ解くだけで終わらず、解法を理解して同じミスを繰り返さないように復習を徹底することです。
間違えた問題は再度解き直し、解法が定着しているか確認しましょう。
基礎問題精講はどのくらいの期間で1周するのがベスト?
基礎問題精講を1周するのにかかる期間は、受験までの残り時間や学習の進度によって異なります。
一般的な目安として、以下のスケジュールがおすすめです。
- 半年以上の余裕がある場合:3〜4か月で1周
- 共通テスト対策で基礎固めをする場合:2か月で1周
- 短期間で完成させたい場合:1か月で1周
1周目で理解しきれなかった問題はきちんと復習し、2・3周目で定着させましょう。
1周目は解説をしっかり読みながら進め、2周目以降で間違えた問題を中心に復習すれば、効率的に数学力を伸ばせます。
数学の勉強でやってはいけないNGな勉強法とは?
数学の勉強で成果が出ない原因の一つは、間違った勉強法を続けてしまうことです。
以下のNGな勉強法に注意しましょう。
- 解説を読んで「分かったつもり」になる
- できる問題ばかり解いてしまう
- 公式や解法を丸暗記する
問題を解いた後に解説を読み、納得するだけで終わるのはNGです。
数学が苦手な人は、自分が解ける問題ばかりを繰り返し解きがちですが、得意な問題だけ解いても苦手な問題の克服にはなりません。
間違えた問題こそ重点的に復習し、なぜ間違えたのかを分析する習慣を付けましょう。
数学は公式の成り立ちや意味を理解せずに丸暗記してしまうと、応用問題に対応できません。
公式の導出や具体的な例を用いて、なぜこの公式を使うのかを考えながら学習してみてください。
基礎問題精講の効果的な進め方や順番は?
基礎問題精講を使う際には、以下の順番を意識しましょう。
- 例題を解き解説をしっかり読み、解法の流れを理解する
- 演習問題で定着を図る
- 苦手な問題を中心に繰り返し復習する
- 実際の入試問題や過去問とリンクさせる
解説を読んだ後、3日後にもう一度解いてみて定着度をチェックしてみてください。
苦手な問題は、1周目は解法の理解、2周目は自力で解けるようにする、3周目は時間制限を設定して素早く解けるようにするという意識で取り組みましょう。
基礎問題精講の正しい勉強法と使い方をマスターして学力を効率的に伸ばそう

基礎問題精講の正しい勉強や使い方をマスターすれば、数学の基礎力を大きく伸ばし、志望校合格に一歩近づきます。
しかし、効果的な勉強法を自分で見つけるのは難しいかもしれません。
最短ルートで合格を目指すなら、プロの受験コンサルタントに相談してみませんか。
ポラリスアカデミアでは、受験生の皆さんの悩みに寄り添い、最も効率的な学習プランを提案する無料受験相談を実施しています。
- 基礎問題精講をどう活用すればいいかわからない
- 自分に合った参考書の選び方を知りたい
- E判定だけど、志望校に何とか合格したい
受験のお悩みを抱えている方は、ぜひポラリスアカデミアの無料受験相談をお試しください。
たった数分で申し込みが完了し、合格への第一歩を踏み出せます。
今すぐ無料相談を申し込み、効率的な勉強法で合格をつかみ取りましょう。
この記事を書いた人

吉村暢浩京都大学工学部卒業
2018年、京都大学工学部を卒業、同大学大学院に進学。2019年に京都大学大学院を退学し、受験コンサルティング事業「ポラリスアカデミア」を立ち上げる。2021年、株式会社ポラリスを設立。社会で勝ち抜くために必要な問題解決能力を大学受験を通じて身に付ける独自の指導を行っている。