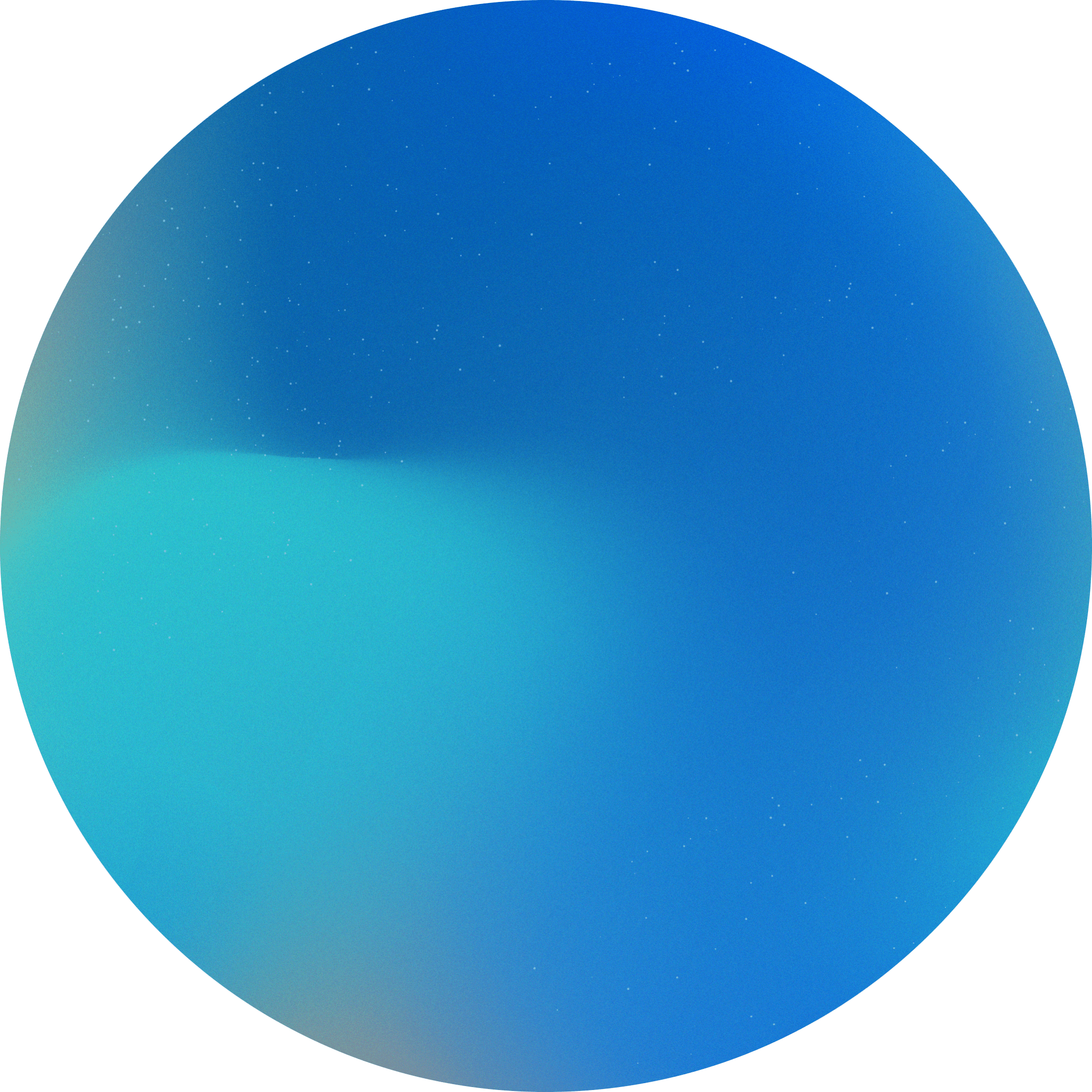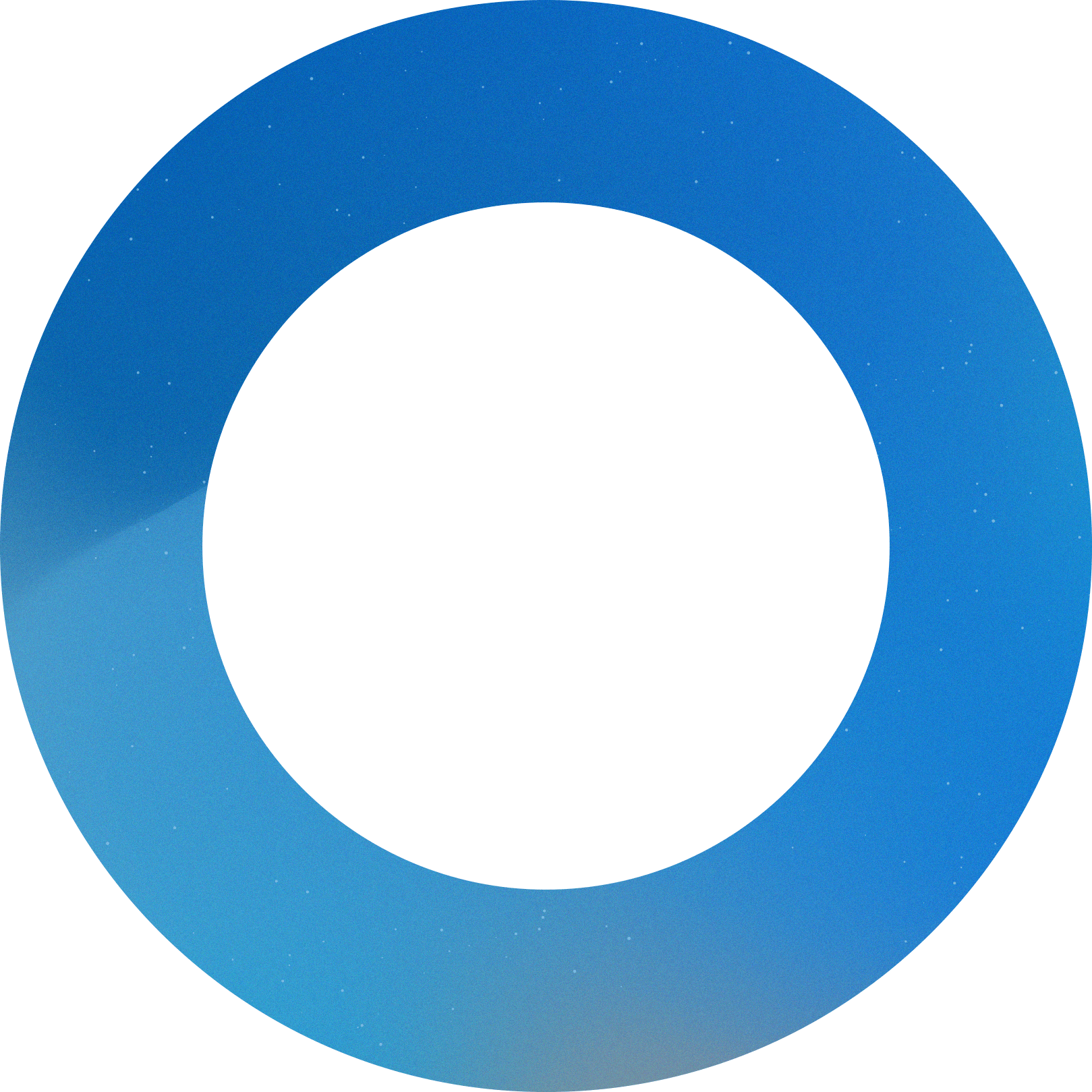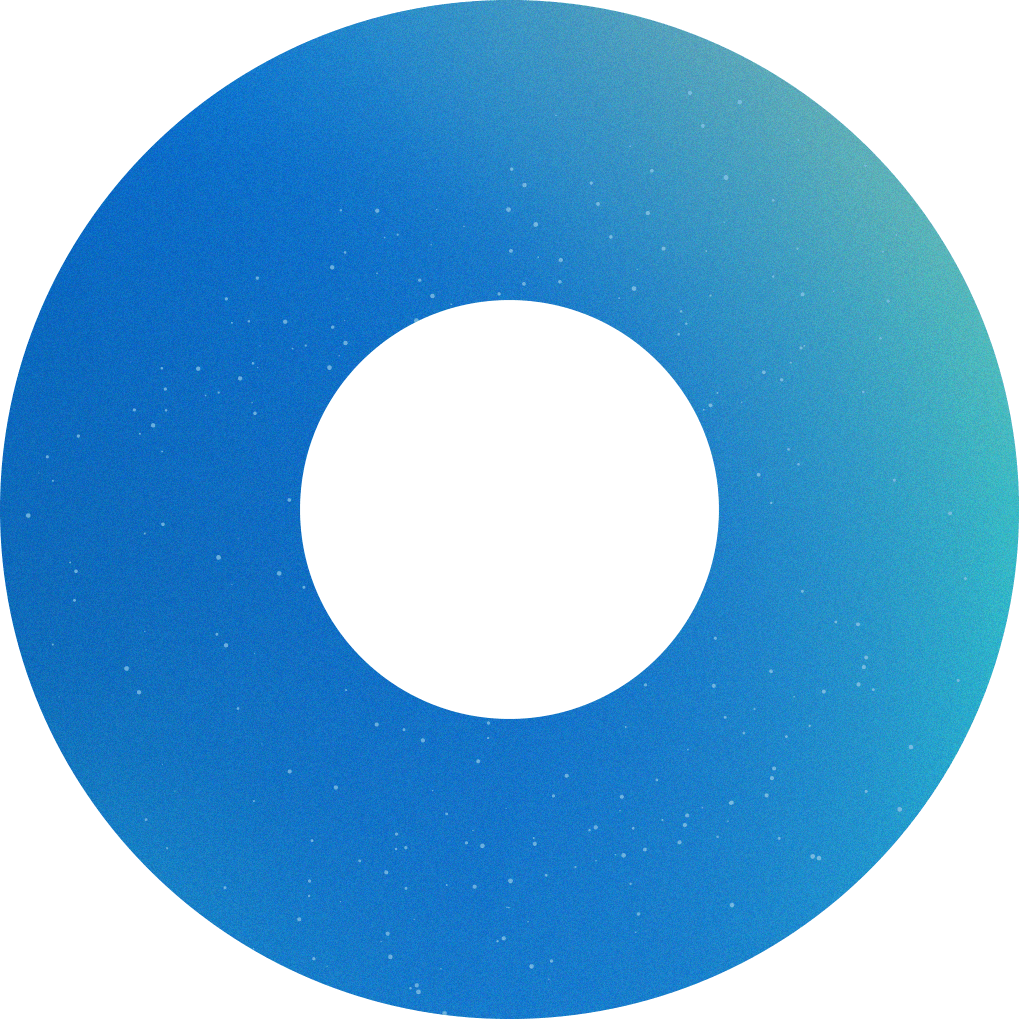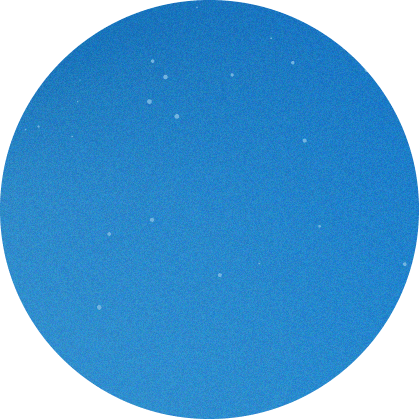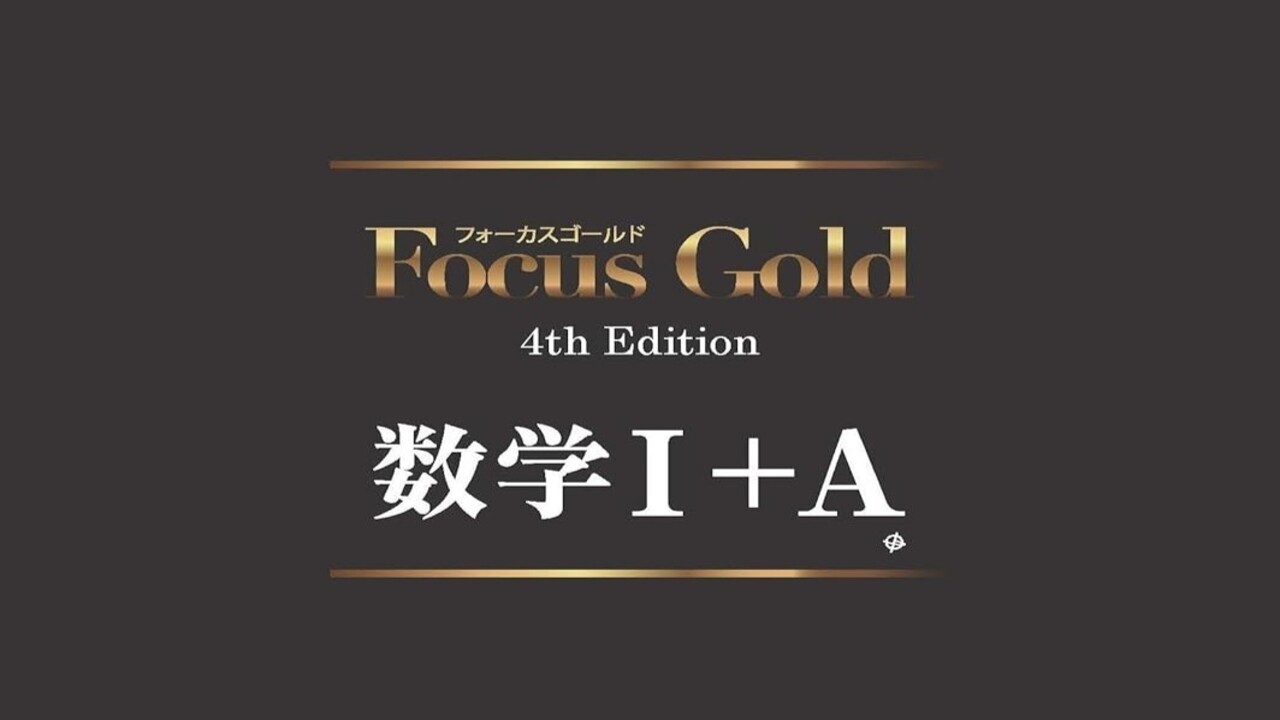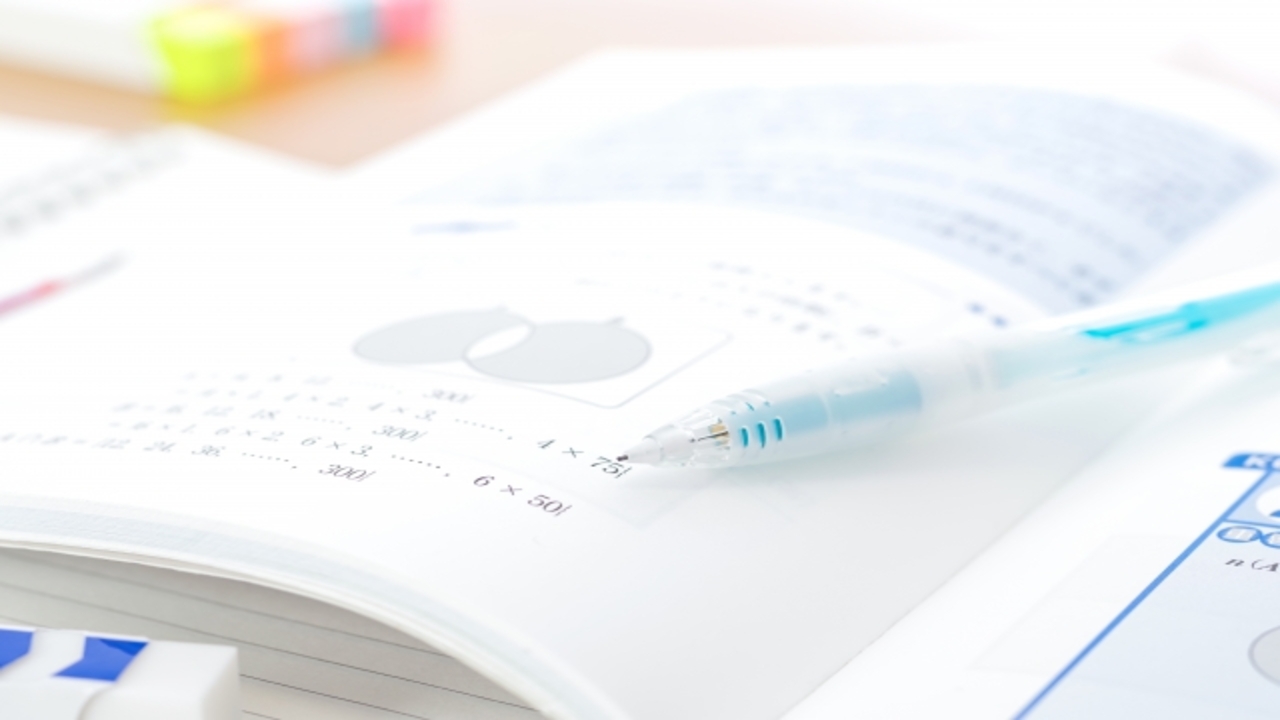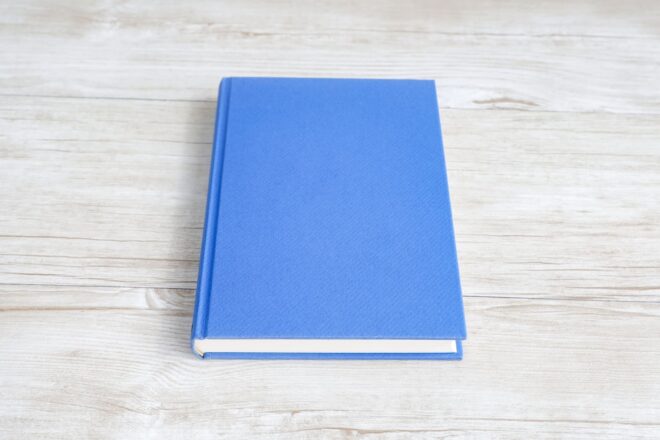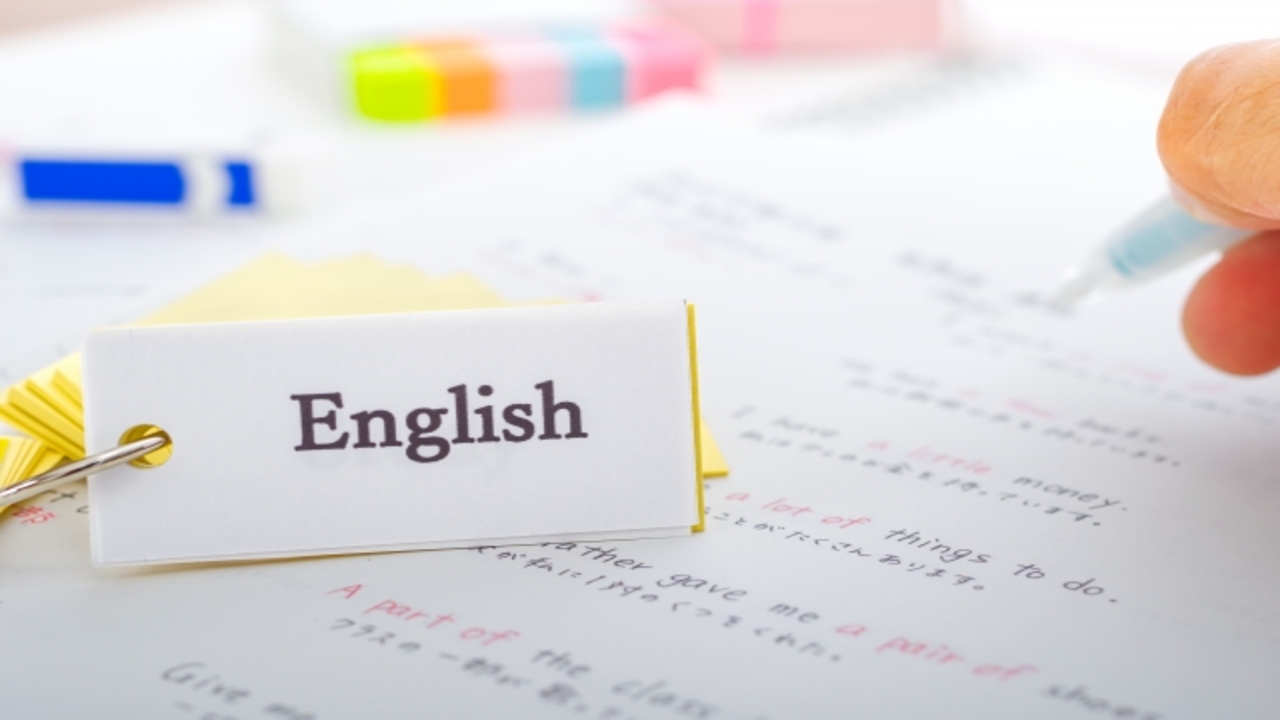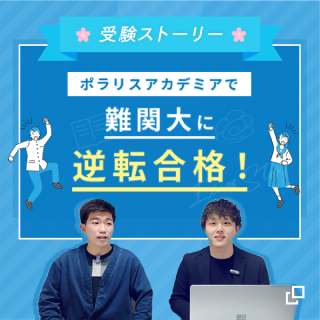数学の定番参考書として、多くの受験生が手に取る 「青チャート」。
しかし 「どのように使えば効果的なのか」「例題だけ解けばいいのか」など青チャートの使い方に悩んでいる人も多いでしょう。
青チャートは使い方次第で大きく成績を伸ばせる一方で、間違った進め方では時間をかけても成果が出にくい参考書です。
本記事では、 青チャートを最大限活用するための具体的な使い方や注意点を解説します。
青チャートの効果的な使い方を知りたい、数学の偏差値を伸ばしたい人は、ぜひ参考にしてください。
青チャートってどんな参考書?
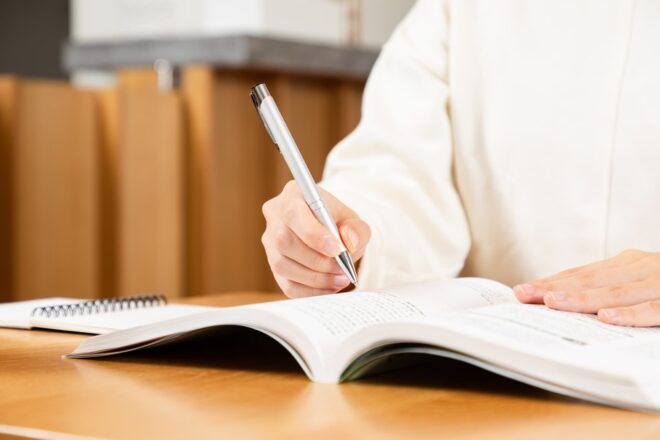
青チャートとは、数研出版から出ている高校数学の網羅系参考書で、多くの進学校や予備校でも採用されている定番の問題集です。
数学の基礎から応用まで幅広くカバーしており、 基本例題・演習例題・重要例題の3種類の例題に加え、 練習問題・Exercise・章末問題などが収録されています。
青チャートは数学の良問が厳選され、解法の考え方が詳しく解説されている点が特徴です。
問題ごとに解法のポイントが整理されているため、 数学の解き方を体系的に学べます。
青チャートの他に、白・黄・赤などレベル別のシリーズがあります。
- 白チャート:数学が苦手な人向けの基礎固め用
- 黄チャート:中堅大学向けの標準レベル
- 青チャート:共通テスト〜難関大学(MARCH・関関同立・地方国公立)向けの標準〜発展レベル
- 赤チャート:東大・京大・東工大など超難関大向けの高度な問題集
緑チャート(共通テスト対策用)や紫チャート(中堅私大〜地方国公立向けのアウトプット型) など新しいシリーズも登場しています。
青チャートを使うメリット

青チャートの最大の強みは圧倒的な網羅性です。
一冊で数学の基礎から旧帝大を除く難関大学レベルまで対応可能であり、基本問題だけでなく、応用問題や入試で使える解法テクニックまでカバーされています。
多くの進学校で、学校指定の参考書として採用されている信頼性の高い教材です。
「青チャート一冊で大学受験数学は完結できる」ほどの膨大な問題量を誇ります。
数学ⅠA・ⅡB・Ⅲそれぞれで950題・1100題・850題以上の問題が収録されており、文系なら2,000題以上、理系なら3,000題以上の問題が解けます。
しかし、圧倒的なボリュームがデメリットになり得ることも頭に入れておきましょう。
全問を解こうとすると時間がかかりすぎてしまい、途中で挫折してしまう人も少なくありません。
入試までの残り期間が短い場合や数学に苦手意識がある人には、 問題量の多さが学習の負担になる可能性が高いです。
数学を基礎からしっかり学びたい、幅広い問題パターンを網羅したい人は、青チャートをおすすめします。
短期間で効率よく基礎固めをしたい人は、 基礎問題精講など別の参考書を周回する方が効果的な場合も。
自分の学習ペースや志望校レベルに合わせて、青チャートの使い方を見極めましょう。
青チャートの正しい使い方とは?メリットを活かした勉強法4Step

青チャートを効果的に使えている受験生は、ただ解くだけではなく、正しいステップを踏んで勉強を進めています。
受かる受験生が実践している青チャートの使い方を、わかりやすく4つのステップに分けて解説します。
「なんとなく解いているだけ」から脱却し、数学の力を確実に伸ばしましょう。
Step1.例題は書かずに解法を理解する
青チャートには膨大な問題数が収録されているため、 すべての例題を紙に書いて解くのは非効率です。
青チャートの目的は頻出問題の解法を暗記し、定着させることです。
例題は書かずに頭の中で考え、解答・解説を読んで解法を理解すれば、効率的に学習が進められます。
ただし、ここでいう「暗記」は、単純に答えを丸暗記することではありません。
「この問題を見たら、どの解法を使うべきかがすぐに思い浮かぶ」状態にすることです。
公式やパターンを覚えるのではなく、 解き方の流れや考え方を理解し、応用できるようになりましょう。
例題の解説を読みながら、なぜこの解法を選んだのかを自分に問いかけることもおすすめです。
問題の本質を理解しやすくなり、類題にも対応できる力が身に付きます。
Step2.練習問題で解法を定着させる
例題で解法を理解・暗記した後は、ページ下の練習問題で実際に手を動かしながら定着させます。
練習問題は例題の類題になっていることが多いため、例題で学んだ解法をすぐに使えるかを試してみましょう。
解いた後は、解いた問題の横に 〇・✕の印を付けてください。
正答できた問題には〇を、正答できなかった問題には✕を付け、バツが付いた問題は再度解法を確認します。
✕が付いた問題は、 解法をもう一度見直し、正しく理解できるまで復習しましょう。
その日の夜や翌朝にもう一度解き直すと、定着度が向上します。
問題を解く際は制限時間を設けるのもおすすめです。
ダラダラと解いてしまうと、試験本番のタイムマネジメントがうまくいかず、実力を発揮できない原因になります。
Step3.3周解いて無意識に解法が浮かぶようにする
青チャートは、1周解いただけでは定着しません。
最低でも3周は繰り返し、解法を無意識レベルまで落とし込む必要があります。
2周目以降は、 〇の付いた練習問題はノーヒントで(例題に目を通さずに)解いてみましょう。
1周目に身に付けた解法がきちんと定着しているかを確認するためです。
2周目でも詰まりなく解けたなら、その問題の解法はもう習得したとみなし、1周目に書いた〇を塗りつぶしましょう。
そして、✕の付いている問題は再度例題の解法を理解・暗記してから練習問題に取り組みます。
前回どうして間違えたのかをメモしておくと、良い復習になるでしょう。
2周目で正答できたのなら✕の横に〇を付け、また間違えてしまった場合は✕の横にもう1つ✕を付けましょう。
例題から解き直したり、先生や友達に質問したりなど2周目以降も復習も忘れないでください
2回連続で間違えたなら、そもそも解法の意味や着眼点を理解していない可能性が高いです。
3周目は、2回目で●(塗りつぶした〇)が付いている問題は既に習得済みのため飛ばして構いません。
それ以外の〇✕・✕✕が付いている練習問題のみ取り組んでいきましょう。
〇✕が付いている問題をノーヒントで正答できたなら〇を塗りつぶして●✕にし、その問題は習得済みとみなします。
✕✕が付いている問題を正答できたなら〇✕✕とし、3周目は終了です。
3周目終了時点で●の割合が80%を超えていれば合格ラインです。
ここまでやれば、その章のほとんどの問題で、解法が無意識に浮かぶようになっています。
その章はクリアだと考えて、自信を持って次の章に進みましょう。
●となっていない練習問題は4周目に入っても良いですが、あまり深追いしても効率が悪いため時間を空けてからの演習がおすすめです。
Step4.Exerciseはレベル③まで解けたらOK
青チャートの Exerciseは、入試レベルの問題が多数含まれています。
Exerciseの部分を解くかどうかは、 志望校や現在の学力によって判断しましょう。
「他の入試問題集を使う予定があるなら、無理に解く必要はない」などの意見もあります。
しかし 「いきなり入試問題集はハードルが高い」と感じる人には、有効な演習です。
なぜなら、青チャートのExerciseは 単元ごとに細かく分かれており、解法の予測がしやすいためです。
過去問や入試問題集を解くことに不安がある人は、Exerciseを活用しましょう。
ただし、 Exerciseのレベル④・⑤は難易度が非常に高いため、解くのはレベル③までで構いません。
※問題番号の横に記載されている 〇で囲まれた数字がレベルを表しています。
レベル③まで解けるようになれば、その単元の実力は十分に身に付いているため、自信を持って次のステップに進みましょう。
青チャートの使い方、注意したい3つのこと
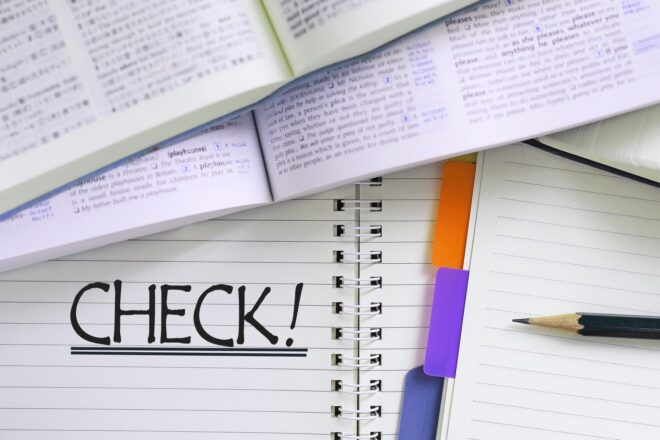
青チャートを効果的に活用するためには、使い方だけでなく注意点もしっかり押さえましょう。
青チャートは問題数が多く難易度も幅広いため、学習の進め方に工夫が必要です。
青チャートを使う際に注意すべき3つのポイントを解説します。
効率よく学習を進めたい人は、ぜひチェックしてください。
青チャートの使い方の注意点1. 一度に詰め込みすぎない
青チャートは網羅性が高く、多くの問題が掲載されているため、一度に大量の問題を解こうとすると非効率です。
効率的に活用するためには「分散学習」を意識しましょう。
分散学習とは、時間を置いて何度も繰り返し復習することで、記憶を長期的に定着させる方法です。
1日に同じ単元の問題をすべて解くのではなく、1日おきに異なる問題を解けば、学習効果を高められます。
問題を解く際には、優先順位を決めて進めることも重要です。
まずは未着手の問題に取り組み、次に過去に解けなかった問題を重点的に復習しましょう。
解けた問題ばかりを繰り返しても学習効果は低いです。
一度解けた問題は模試の前などに軽く見直す程度に留め、時間を有効に使うことを意識しましょう。
青チャートの使い方の注意点2. 解けない問題に固執しすぎない
青チャートの問題には、基礎レベルから応用レベルまでさまざまな種類が含まれています。
中にはどうしても解けない問題が出てくることもあるでしょう。
しかし、解けない問題に時間をかけ過ぎると、他の問題を解く時間がなくなり、学習の効率が大幅に低下してしまいます。
解けない問題に時間をかけ過ぎるよりも、一度解説を読み、理解を深めた後で類題に取り組む方が効率的です。
「わからない問題=自分にとって必要な学習課題」と捉え、時間を設定して取り組みましょう。
1問にかける時間の上限を決め、15分考えても解法が思い浮かばなければ解説を読み、次の問題に進むなどルールを設定することもおすすめです。
解けなかった問題は後日改めて取り組むことで、理解の定着を図れます。
青チャートの使い方の注意点3. 解説を丁寧に理解する
青チャートの問題を解く際、ただ答えを合わせるだけでは学習が身に付いたとはいえません。
解答を見ながら、なぜこの公式を使うのか、別の解法はないかと自問自答しながら理解を深めましょう。
青チャートには各章の最初に「まとめ」が掲載されています。
重要な定義や公式が書かれていますが、内容が抽象的で難しく感じるかもしれません。
わからない場合は、無理に暗記しようとせず、実際の問題を解きながら理解を深めることが効果的です。
青チャートの使い方に関するQ&A
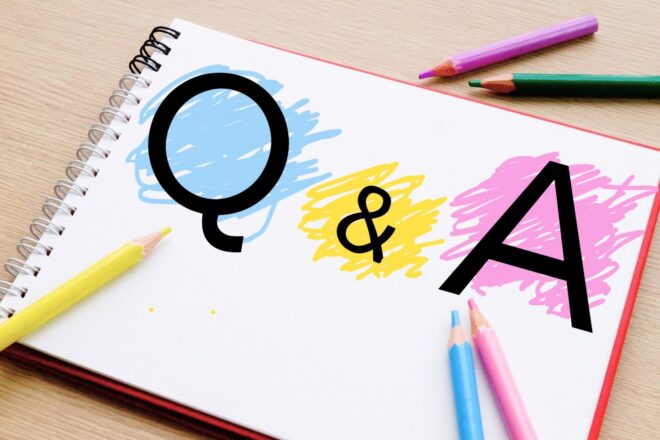
青チャートの使い方に関するよくある質問に答えます。
青チャートは1日に何問解けば効率が良いの?
青チャートの学習ペースは、目標とする大学のレベルや残りの受験期間によって異なりますが、1日10〜20問を目安に進めるのが一般的です。
数学が苦手な人や基礎からしっかり固めたい人は、焦らずに1日10問程度からスタートし、徐々にペースを上げましょう。
数学を得点源にしたい人や難関大学を目指している人は、1日20〜30問を目標にしてみてください。
青チャートを終わらせるのに何ヶ月かかる?
青チャートは数学の基礎から応用までを網羅した参考書で、数学ⅠA・ⅡB・Ⅲの全範囲を終わらせるには、かなり時間が必要です。
1日15〜20問のペースで進めた場合、ⅠA・ⅡBはそれぞれ3〜4ヶ月、数学Ⅲは2〜3ヶ月かかります。
ただし、苦手な単元や応用問題に時間がかかる場合もあるため、1周するのに6〜8ヶ月程度見積もっておいた方が良いでしょう。
青チャートだけでどこまで偏差値を上げられる?
青チャートは基礎から応用まで幅広くカバーしているため、しっかり活用すれば偏差値を10〜15程度上げることも可能です。
青チャートの例題と練習問題を完璧に解けるレベルになれば、共通テストや私立大学、地方国公立大学の一般入試で十分な得点を取れるでしょう。
共通テストレベルの数学であれば、青チャートの内容をしっかりマスターすることで偏差値60前後まで到達できる可能性が高いです。
青チャートをやり込めば、どのレベルの大学に合格できる?
青チャートは、MARCH・地方国公立大学レベルの数学を網羅しています。
ただし、旧帝大・医学部・早慶レベルなど難関大学を目指す場合、青チャートの内容だけでは対応しきれない場合が多いです。
特に記述式の答案作成力や複雑な応用問題への対応力を求められる試験では、過去問演習や発展的な問題集にも取り組む必要があります。
また、大学ごとの過去問を解き、出題傾向を把握することも重要です。
青チャートの正しい使い方を知り、効率良く勉強を進めよう

青チャートの正しい使い方を知れば、数学の得点力を伸ばせます。
しかし、青チャートは問題量が多いため、やみくもに取り組むと途中で挫折してしまうことも。
青チャートは、頻出問題の解法を定着させるための参考書です。
メリットである膨大な網羅度が逆にデメリットになってしまわないよう、効率重視で解法を身に付けていきましょう。
特に現役生は時間が限られているため、計画的に学習を進めることが重要です。
青チャートを正しく使い、数学を得意科目にしましょう。
ポラリスアカデミアでは、無料の受験相談を実施しています。
- E判定だけど、志望校に合格したい
- 今の勉強法が本当に合っているのか不安
- モチベーションを上げる何かが欲しい
このような悩みを抱えているなら、たった数分で登録できる受験相談をご活用ください。
プロの受験コンサルタントがあなたの学習計画を個別にアドバイスし、勉強の悩みを解決します。
興味のある受験生は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人

吉村暢浩京都大学工学部卒
2018年、京都大学工学部を卒業、同大学大学院に進学。2019年に京都大学大学院を中退し、受験コンサルティング事業「ポラリスアカデミア」を立ち上げる。2021年、株式会社ポラリスを設立。社会で勝ち抜くために必要な問題解決能力を大学受験を通じて身に着ける独自の指導を行っている。