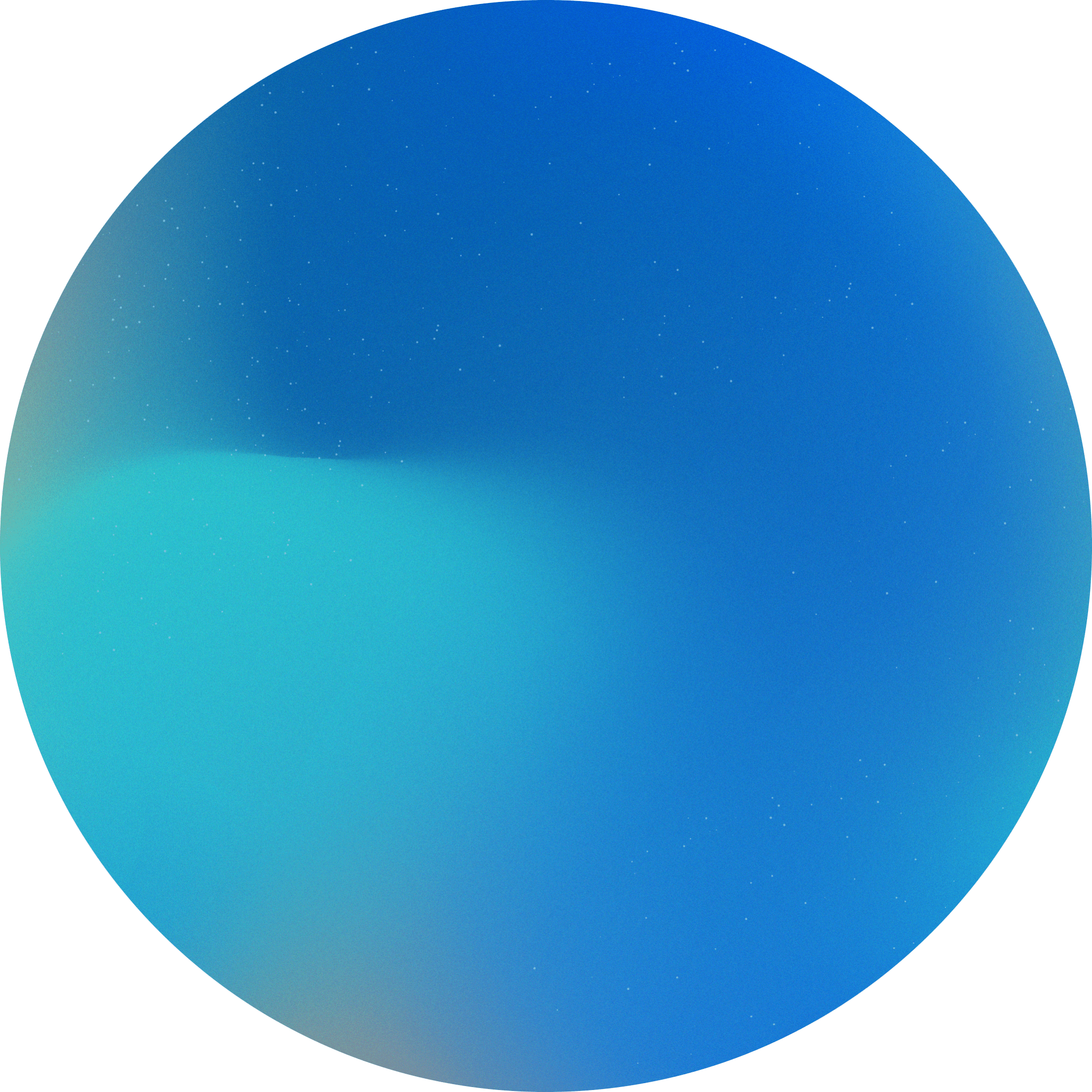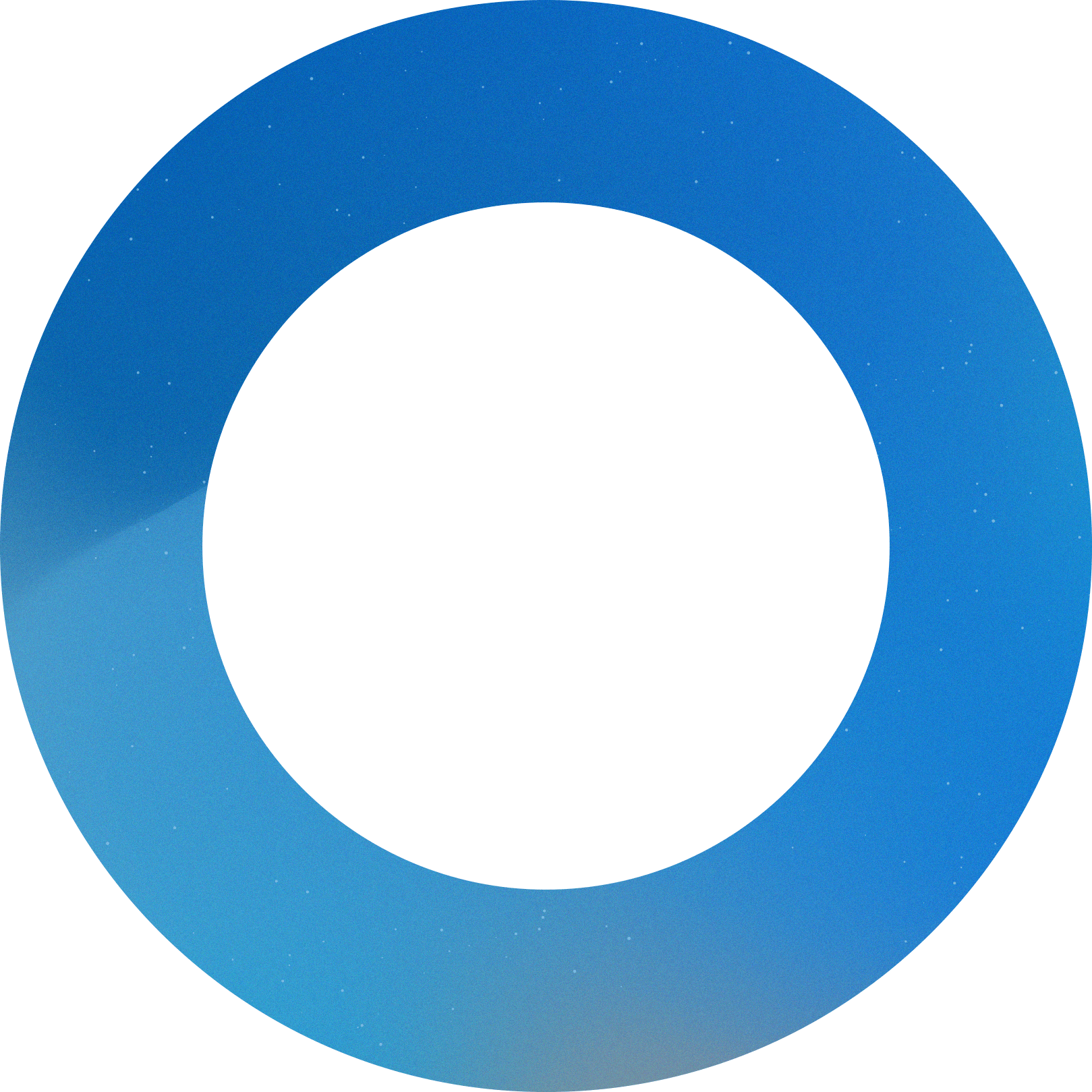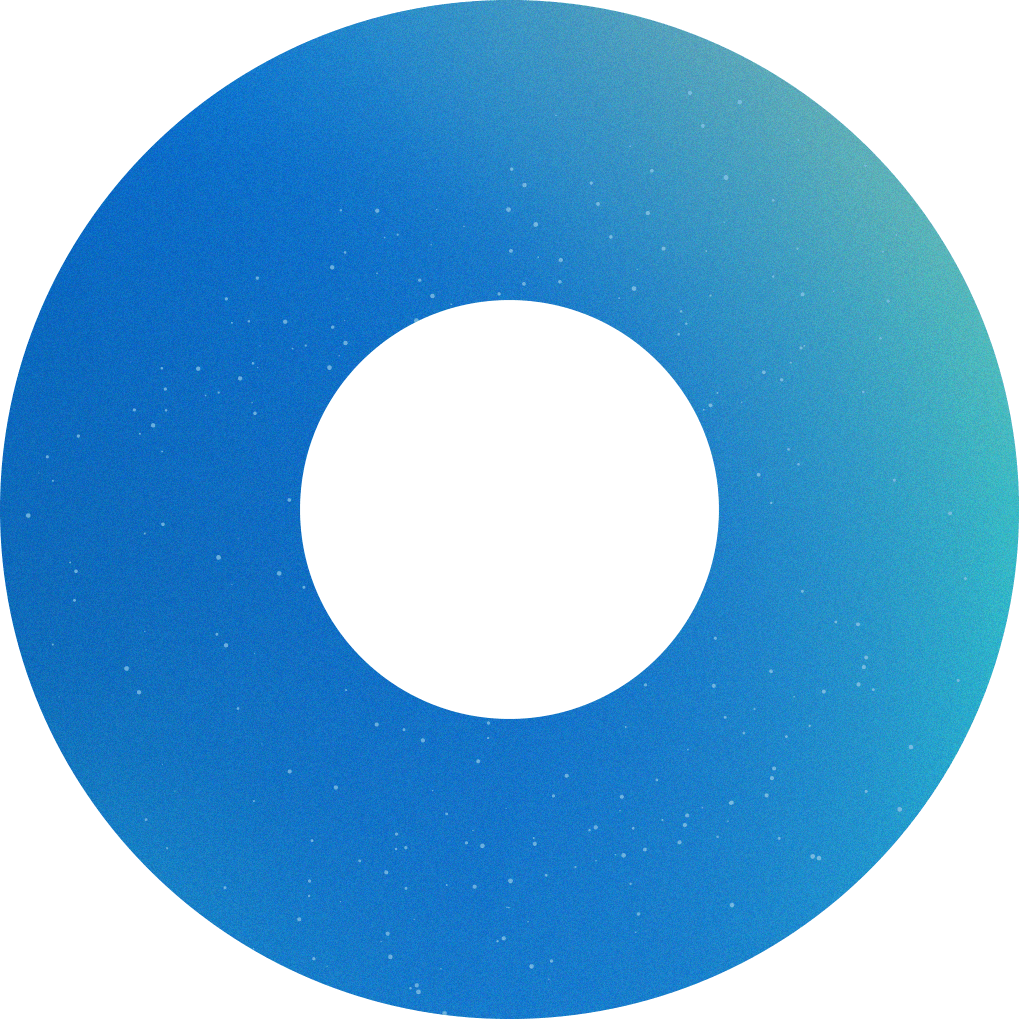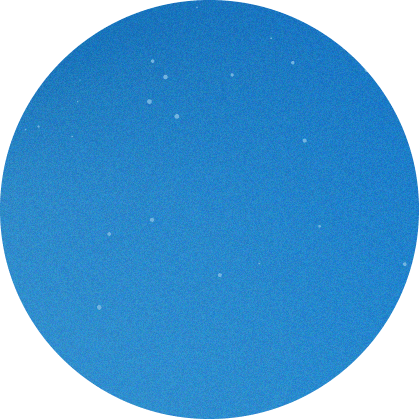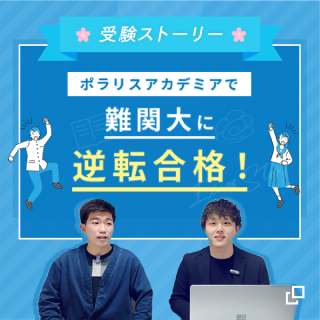目次
1. レベル別リスニング学習ロードマップ|4月からのスタートダッシュを切る!
(1) 基礎レベル(偏差値40-50):英語の音に慣れるトレーニング
– 英語の音声変化のルールを学ぶ
英語のリスニングで高得点を取るためには、音声変化のルールを理解することが重要です。単語単体で発音する際と、文章の中で発音する際には音が変化することがあります。これらの変化を理解していないと、単語を聞き取ることが難しく、内容理解に支障をきたします。特に基礎レベルの方は、音声変化のルールを学ぶことで、リスニング能力を飛躍的に向上させることができます。
音声変化には、様々な種類があります。代表的なものを以下にまとめました。
|
音声変化の種類 |
説明 |
例 |
|---|---|---|
|
連結 |
語尾の子音と語頭の母音が繋がり、滑らかに発音される |
get up → ge tup |
|
同化 |
隣り合う音が影響し合って、音が変化する |
handbag → hanbag |
|
脱落 |
音が弱化したり、消失したりする |
want to → wanna |
|
弱化 |
母音が弱くなり、あいまいな音になる |
can → cn |
これらの音声変化は、実際に英語を聞いているうちに自然と慣れていく部分もありますが、意識的に学習することで、より早く、より正確に聞き取れるようになります。音声変化のルールを学ぶための具体的な方法としては、下記のような方法がおすすめです。
-
音声変化に特化した教材やアプリを利用する
-
英語の音声学の参考書を読む
-
ネイティブスピーカーの発音を注意深く聞き、変化のパターンを分析する
これらの学習方法を参考に、積極的に音声変化のルールを学び、リスニング力を強化しましょう。
– 基本的な単語・フレーズを聞き取る練習
リスニング対策の基礎は、単語やフレーズを正確に聞き取ることです。単語帳の音声を活用したり、リスニング用の教材で集中的に練習することで、着実に聞き取る力を向上させることができます。
①基礎単語の確認:まずは、大学受験で必須となる基礎単語の発音を完璧にマスターしましょう。単語帳に付属の音声CDやアプリを活用し、何度も繰り返し聞いて発音を確認し、発音できるまで練習しましょう。
②短いフレーズの聞き取り:基礎単語の発音が身についたら、短いフレーズの聞き取り練習に進みます。教科書やリスニング教材に収録されている短い会話やフレーズを聞き、意味を理解できるか確認しましょう。
③聞き取れない箇所の分析:聞き取れなかった単語やフレーズは、スクリプトで確認し、なぜ聞き取れなかったのかを分析することが重要です。発音記号を確認したり、音声変化のルールを学ぶことで、聞き取りの精度を高めることができます。
④反復練習:聞き取れるようになるまで、何度も繰り返し音声を聞きましょう。最初はゆっくりとした速度で聞き、徐々にスピードを上げていくことで、自然な速さで聞き取れるようになります。
これらのステップを着実に踏むことで、英語の音に慣れ、基本的な単語・フレーズを正確に聞き取れるようになります。4月から基礎を固め、スムーズに次のステップへ進みましょう。
– 短い会話やアナウンスを聞いて内容理解
基礎レベルの学習では、短い会話やアナウンスを聞いて、全体の内容を理解する練習が中心となります。登場人物は何を話しているのか、アナウンスは何を伝えているのかを正確に把握することを目指しましょう。
具体的には、以下のようなステップで学習を進めていくのが効果的です。
-
まずは、何も見ずに音声を聞きます。この段階では、完璧に理解しようとせず、聞こえてきた単語やフレーズから、話の大まかな内容を推測することに集中しましょう。
-
次に、スクリプトを見ながら音声を再度聞きます。聞き取れなかった部分を確認し、内容を理解します。
-
最後に、スクリプトを見ずに音声をもう一度聞きます。理解度が深まっているかを確認しましょう。
短い会話やアナウンス教材は、市販の教材やアプリで手軽に入手できます。自分に合った教材を選び、繰り返し練習することで、リスニングの基礎固めをしっかり行いましょう。具体的な教材については、後ほど詳しくご紹介します。
(2) 中級レベル(偏差値50-60):実践的なリスニング力UP
– 長めの会話や講義を聞いて内容理解
中級レベルの学習者にとって、長めの会話や講義を聞いて内容を理解することは、リスニング力向上において重要なステップとなります。
短い会話と比べて情報量が多く、集中力を維持することが求められます。
効果的な学習方法として、以下の3つのステップで取り組むことをおすすめします。
①まずは全体を聞き流し、会話や講義のテーマや大まかな流れを掴みます。
②重要なキーワードやフレーズを意識しながら、もう一度聞き取ります。メモを取りながら聞くのも効果的です。
③最後に、聞き取った内容を整理し、概要をまとめます。スクリプトを確認して、聞き取れなかった部分を分析しましょう。
また、教材選びも重要です。
自分の興味のある分野や、大学で学びたい分野に関連した教材を選ぶことで、より楽しく学習を進めることができます。
例えば、以下のような教材がおすすめです。
-
大学入試センター試験の過去問
-
TOEICの公式問題集
-
TEDなどの英語講演
これらの教材を活用し、長めの会話や講義を聞いて内容理解する練習を積み重ねることで、実践的なリスニング力を身につけることができます。
さらに、次のステップである「言い換えや推測問題への対策」にスムーズに進めるための土台を築くことができるでしょう。
– 言い換えや推測問題への対策
中級レベルの学習者は、正答の選択肢が本文の音声中で言い換えられている場合や、直接的には述べられていない情報を推測する必要がある問題に苦労するかもしれません。これらの問題は、語彙力や文脈理解力が試されるため、対策を怠ると得点に大きく響きます。
言い換え問題で意識すべきポイントは、同義語・類義語を理解しているかどうかです。例えば、”important”という単語が聞こえた場合、選択肢には”essential”や”significant”といった同義語が使われている可能性があります。普段から類義語を意識して学習しておきましょう。また、英文を自分の言葉で言い換えるパラフレーズも効果的です。
推測問題では、断片的な情報から全体像を把握する練習が必要です。話者の発言の意図や背景知識なども考慮しながら、推測力を磨きましょう。例えば、話者が疲れた様子で”I’ve had a long day.”と言った場合、”The speaker is tired.”と推測できます。このように、直接的に述べられていない情報を推測する練習を積み重ねることが重要です。これらの対策を通して、言い換えや推測問題にも自信を持って解答できるようになり、リスニングスコアを着実に伸ばせるはずです。
– スピード調整やシャドーイング、ディクテーション
中級レベルでリスニング力を向上させるには、音声の操作や書き取りを通して、英語の音声に慣れ親しむことが重要です。ここでは、スピード調整、シャドーイング、ディクテーションの効果的な活用法について解説します。
まず、スピード調整は、自分のレベルに合った速度でリスニングすることで、理解度を高めるための方法です。最初はゆっくりとした速度で始め、徐々に速度を上げていくことで、自然な速さの英語にも対応できるようになります。
次に、シャドーイングは、音声を追いかけるように発音することで、英語のリズムやイントネーションを体得するのに効果的です。発音に自信がない人も、積極的に取り組むことで改善が見込めます。
最後に、ディクテーションは、聞き取った内容を書き取ることで、正確なリスニング力を養うトレーニングです。最初は短い文章から始め、徐々に長い文章に挑戦していくと良いでしょう。
これらの学習法を組み合わせて、集中的に取り組むことで、リスニング力の飛躍的な向上が期待できます。
(3) 上級レベル(偏差値60-70):得点力を最大化するための戦略
– 複雑な会話や議論を聞いて詳細な情報把握
上級レベルを目指す皆さんは、複雑な会話や議論を聞いて詳細な情報把握に取り組む必要があります。ここでは、そのための具体的な方法やポイントを紹介します。
複雑な会話や議論を理解するためには、話の流れを掴むだけでなく、話者が伝えたい意図や、それぞれの主張の根拠を正確に捉えることが重要です。
-
ディクテーション:聞こえた内容を書き出すことで、細かい情報も聞き逃さないようにする練習です。
-
パラフレーズ:聞いた内容を自分の言葉で言い換えることで、理解度を確認する練習です。
-
要約:聞いた内容の重要なポイントをまとめて、簡潔に表現する練習です。
これらのトレーニングに加えて、多様なアクセントに慣れることも重要です。イギリス英語、アメリカ英語、オーストラリア英語など、様々なアクセントの音声を聞く機会を増やすことで、より実践的なリスニング力を身につけることができます。
大学受験では、講義形式のリスニング問題も出題されることがあります。講義形式のリスニングでは、話者が一方的に情報を伝えるため、集中力を維持しながら重要な情報を聞き取る必要があります。メモを取りながら聞く練習も効果的です。
– 多様なアクセントへの対応
上級レベルを目指す上で、多様なアクセントへの対応は必須です。英語には様々なアクセントが存在し、それらを聞き分けることは高得点獲得に繋がります。特に、イギリス英語、アメリカ英語に加え、オーストラリア英語やインド英語、アフリカ英語など、様々な国のアクセントへの対応力を磨くことが重要です。
色々なアクセントに触れることで、リスニング力が格段に向上します。例えば、アメリカ英語に慣れている人がイギリス英語を聞くと、最初は戸惑うかもしれません。しかし、繰り返し聞くことで、次第に慣れて理解できるようになります。
様々なアクセントへの対応力を高めるための具体的な方法として、以下の3つの方法が挙げられます。
-
積極的に様々なアクセントの英語を聞く
-
英語字幕を活用し、発音とスペルの違いを理解する
-
スピーカーの出身地を意識しながらリスニングする
特に、インターネット上には様々な国の英語話者のコンテンツが溢れています。これらを活用しない手はありません。積極的に様々なアクセントの英語に触れ、リスニング力を鍛えましょう。4月から多様なアクセントへの対応力を磨くことで、本番でどんなアクセントが出題されても落ち着いて対応できるようになります。
– 速聴やノートテイキング
上級レベルを目指す上で、速聴とノートテイキングは必須スキルです。これらを効果的に学習に取り入れることで、リスニング能力を飛躍的に向上させることができます。
まず速聴は、通常の速度よりも速いスピードで音声を聞き取る練習です。最初は聞き取れなくても、徐々に慣れていくことで処理速度が向上し、標準速度のリスニングが格段に楽になります。
次にノートテイキングは、音声の内容を効率的にメモする技術です。重要なキーワードや情報を書き出すことで、記憶の定着を促進し、後から見直す際にも役立ちます。
効果的なノートテイキングのコツは以下の通りです。
-
記号や略語を使う
-
図や表を活用する
-
キーワードのみを書き出す
-
自分が見やすいように工夫する
速聴とノートテイキングを組み合わせることで、相乗効果が期待できます。速聴で音声に慣れ、ノートテイキングで重要な情報を整理することで、複雑な内容も正確に理解できるようになります。これらのスキルを磨くことで、大学受験のリスニング試験で高得点を獲得できるだけでなく、将来的な英語学習にも役立つでしょう。
2. 目的別おすすめ勉強法|志望校合格へ導く戦略的リスニング対策
(1) 共通テストリスニング対策:設問形式に慣れる
共通テストのリスニング問題は、日常生活や大学での講義といった場面を想定した幅広いテーマの音声が用いられます。設問形式に慣れることが高得点への近道です。
|
設問形式 |
対策 |
|---|---|
|
図表問題 |
図表と音声の内容を素早く関連付ける練習をしましょう。キーとなる語句を聞き取る訓練が効果的です。 |
|
要約問題 |
複数ある選択肢から、最も適切な要約を選ぶ問題です。全体の内容を理解し、重要な情報を整理する練習が重要です。 |
|
複数選択問題 |
2~4つの選択肢から、正しい答えを選ぶ問題です。選択肢ごとの微妙な違いを聞き分けられるように練習しましょう。 |
|
発言の意図・状況の推測 |
話し手の意図や会話の状況を推測する問題です。登場人物の関係性や発言のトーンに注目して練習しましょう。 |
共通テスト特有の設問形式としては、複数の写真やイラストから正しいものを選ぶ問題や、会話の流れに合うように適切な応答を選ぶ問題などがあります。過去問や予想問題を活用し、様々な設問形式に触れて、解答の手順を確立しましょう。 本番を想定した時間配分で行う練習も重要です。
4月から計画的に対策を進めることで、本番で落ち着いて問題に取り組むことができます。
(2) 大学別2次試験リスニング対策:大学ごとの出題傾向を掴む
大学別の2次試験リスニング対策では、志望校の出題傾向を徹底的に分析することが重要です。大学によって、出題される問題形式や難易度、会話のテーマ、アクセントなどが大きく異なります。過去問や問題集を活用し、傾向を把握することで、効率的な対策が可能になります。
例えば、以下のような観点で分析を行いましょう。
|
項目 |
内容 |
|---|---|
|
問題形式 |
会話・講義・アナウンスなど |
|
難易度 |
語彙・文法・内容の複雑さ |
|
テーマ |
社会問題・科学技術・文化など |
|
アクセント |
アメリカ英語・イギリス英語・オーストラリア英語など |
|
スピード |
自然な速さ・やや速い・非常に速い |
|
特殊な設問 |
要約問題・推測問題・複数選択問題など |
大学によっては、特定のアクセントやテーマに偏りがある場合があります。例えば、イギリス英語のアクセントが多い大学や、科学技術系のテーマがよく出題される大学などです。これらの傾向を事前に把握しておけば、対策に集中することができます。
また、過去問を解く際には、解答解説をよく読んで、間違えた理由を分析することも大切です。苦手な問題形式やテーマを特定し、集中的に対策することで、弱点克服につながります。
大学ごとの出題傾向を分析し、戦略的に対策することで、2次試験のリスニングで高得点を獲得できる可能性が高まります。
(3) おすすめ教材・アプリ紹介
(1) 基礎レベル(偏差値40-50)
英語の音に慣れるための教材が必要です。発音記号や音声変化のルールを解説した教材と、基本的な単語・フレーズを収録したリスニング教材を併用すると効果的です。
|
教材 |
説明 |
|---|---|
|
『英語耳』(松澤喜好 著) |
英語のリズムやイントネーションを理解するのに役立ちます。 |
|
『DUO 3.0』(鈴木陽一 著) |
重要な単語・熟語を効率的に学べます。CDを活用してリスニング学習にも利用できます。 |
|
スタディサプリENGLISH TOEIC対策コース |
アプリで手軽に学習を進められます。基礎的なリスニング力を鍛えるのに最適です。 |
(2) 中級レベル(偏差値50-60)
実践的なリスニング力を養うには、長めの会話や講義を題材とした教材がおすすめです。シャドーイングやディクテーションに活用できる教材を選ぶと、より効果的に学習できます。
|
教材 |
説明 |
|---|---|
|
『速読速聴・英単語 Core1900 ver.5』(桐原書店) |
標準レベルの英文を収録しており、リスニングだけでなくリーディング対策にもなります。 |
|
TED |
興味のある分野の講演を英語で聞けるので、楽しみながらリスニング力を高められます。 |
(3) 上級レベル(偏差値60-70)
複雑な議論や多様なアクセントに対応できる教材が必要です。速聴やノートテイキングの練習にも活用できる教材を選びましょう。
|
教材 |
説明 |
|---|---|
|
『CNN ENGLISH EXPRESS』(朝日出版社) |
時事問題を扱っているので、高度なリスニング力と語彙力を習得できます。 |
|
BBC Learning English |
イギリス英語に慣れるのに最適な教材です。様々なレベルの学習コンテンツが用意されています。 |
3. モチベーション維持のコツ|リスニング学習を継続するための秘訣
(1) 毎日コツコツ継続!短時間でもOK
リスニング学習において最も重要なのは、毎日継続して英語の音に触れることです。一度に長時間学習するよりも、短時間でも毎日続ける方が効果的です。
スキマ時間を有効活用することで、無理なく学習を継続できます。例えば、通学中の電車内や寝る前の時間などを活用してみましょう。
以下に、短時間学習のメリットと具体的な方法をまとめました。
-
メリット
-
習慣化しやすい
-
集中力を持続しやすい
-
負担が少ないため継続しやすい
-
-
具体的な方法
-
アプリを活用する
-
音声教材をダウンロードして持ち歩く
-
タイマーを使って学習時間を管理する
-
毎日継続することで、英語耳が鍛えられ、リスニング力が向上していきます。4月からコツコツと学習を進め、着実にリスニング力を伸ばしていきましょう。焦らず、少しずつでも毎日続けることが、最終的な目標達成につながります。
(2) 好きな教材で楽しく学習!飽きさせない工夫
リスニング学習は継続が命です。楽しく続けられる工夫を取り入れ、飽きずに学習を続けましょう。自分に合った教材を見つけることが、モチベーション維持の秘訣です。
|
興味 |
おすすめ教材・学習法 |
|---|---|
|
英語圏の音楽 |
歌詞を見ながら曲を聴いたり、カラオケで歌ったりすることで、楽しく英語の発音やリズムに慣れることができます。 |
|
英語圏の映画・ドラマ |
字幕付きで見てストーリーを理解した上で、英語音声のみで見てみましょう。好きな俳優や女優が出演している作品を選ぶと、より楽しく学習できます。 |
|
英語圏のPodcast・ラジオ |
ニュース、英会話、ストーリーなど、様々なジャンルの番組があります。自分の興味のある分野を選んで、気軽にリスニング学習に取り組めます。通勤・通学時間などを活用してみましょう。 |
|
YouTube |
英語学習者向けのチャンネルからエンタメ系まで、様々なコンテンツがあります。自分が楽しめる動画を見つけて、リスニング力を高めましょう。 |
また、教材を定期的に変えることも効果的です。新しい教材に挑戦することで、新鮮な気持ちで学習に取り組めます。無料のアプリやウェブサイトを活用するのも良いでしょう。様々な教材を試して、自分にぴったりの学習方法を見つけてください。
楽しく学習を続けるためのポイントは以下の通りです。
-
好きなジャンルやテーマの教材を選ぶ
-
難易度が適切な教材を選ぶ
-
短時間でも毎日続ける
-
継続しやすい環境を作る
これらの工夫を取り入れて、リスニング学習を習慣化し、目標達成を目指しましょう。
4. まとめ:4月から始めるリスニング対策でライバルに差をつけよう!
4月からリスニング対策を始めることで、大学受験本番で大きなアドバンテージを得ることができます。計画的に学習を進めることで、着実にリスニング力を向上させ、目標達成に近づきましょう。
本記事では、レベル別に最適な学習方法を紹介しました。自身のレベルに合った方法で、無理なく学習を進めていくことが重要です。
また、共通テストや大学別二次試験など、試験の種類に合わせた対策も重要です。出題傾向を分析し、効果的な対策を立てましょう。
継続的な学習がリスニング力向上には不可欠です。毎日少しでも時間を確保し、コツコツと学習を続けることで、大きな成果に繋がるでしょう。好きな教材やアプリを活用し、飽きずに楽しく学習することも大切です。
-
毎日学習を継続する(短時間でもOK)
-
飽きない工夫をする(好きな教材・アプリを使う)
4月から計画的にリスニング学習に取り組むことで、ライバルに差をつけ、志望校合格を勝ち取りましょう。