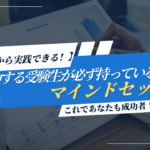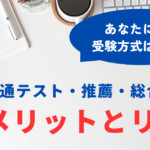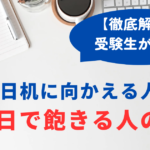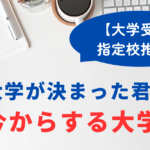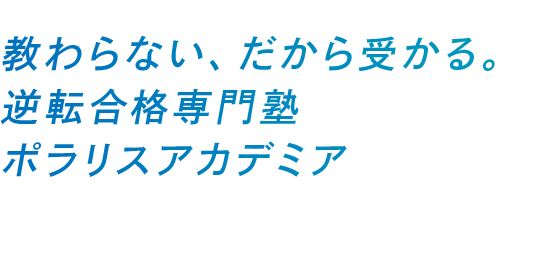【当てはまる受験生は危ないかも】成績が伸びない理由3選
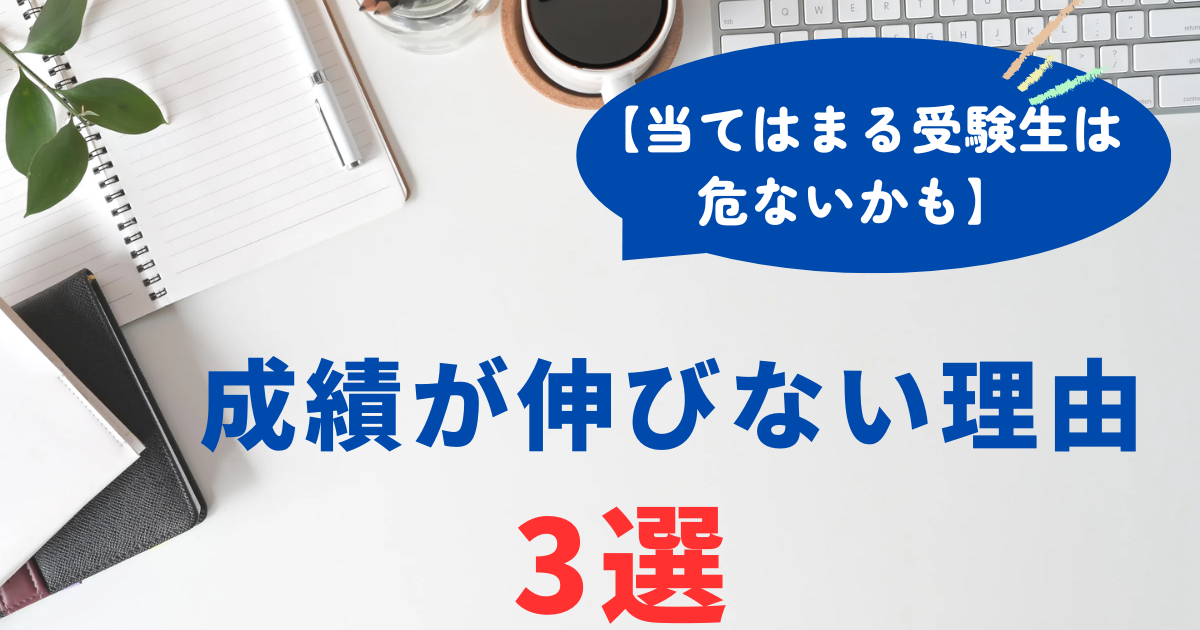
【当てはまる受験生は危ないかも】成績が伸びない理由3選
「毎日ちゃんと勉強しているのに、成績が全然上がらない…」
「模試でE判定ばかり…」そんな悩みを抱えていませんか?
実は、成績が伸びない受験生には、ある“共通点”があります。
今回は、「成績が伸びない受験生の特徴」を3つご紹介します。
もし、あなたに当てはまっている項目があれば、要注意です。
この記事をきっかけに、勉強法を見直しましょう。
① 課題をこなすだけの「作業」になっている

多くの受験生が陥る落とし穴のひとつが、「とにかく毎日やることをこなす」という“作業勉強”です。
●「勉強=タスク消化」になっていないか?
予備校の東進ハイスクールが公表している受験生へのアンケートによると、「毎日勉強しているのに模試の成績が上がらない理由」として最も多かったのが、「ただ参考書をこなしているだけだった」という回答でした。
参考書を1周しただけで理解できたつもりになり、復習や演習を怠ってしまう人が非常に多いのです。
●大切なのは「目的」と「分析」
「何のためにその問題集を解いているのか?」
「間違えた原因は何だったのか?」このような“問い直し”ができているかが、成績向上の分かれ道です。
成績が上がる生徒は、1冊の問題集を3周・4周とやり込み、間違えた問題は解き直しノートにまとめ、類題演習まで徹底して行います。
●チェックポイント
-
1周しただけで終わりにしていないか?
-
毎回の復習が雑になっていないか?
-
自分で解けるようになったか確認しているか?
② 再現性のない計画を立てている

「今日はとりあえず英語と数学をやろう」
「この夏はがんばるぞ!」
…その計画、具体性はありますか?成績が伸びない受験生の多くは、抽象的で再現性のない計画を立ててしまい、勉強が「気合と根性」に依存してしまいます。
●「1日単位」ではなく「週単位」で管理しよう
駿台予備学校が推奨しているのは、「週間目標」の設定です。1日ごとの気分やスケジュールに左右されず、勉強の全体像を俯瞰することで、安定した学習リズムを作ることができます。
●成果の“測定可能性”が重要
「数学を勉強する」ではなく、「Focus Goldの例題20〜30を3周する」「不安な単元の小テストを週2回行う」など、明確に数値化できる計画が大切です。
これにより、「できた」「できなかった」の振り返りが可能になり、次の改善点が見えてきます。
●チェックポイント
-
計画は数値や範囲で管理しているか?
-
進捗を記録して、振り返りができているか?
-
「やったつもり」になっていないか?
③ 足りないものを把握していない

「過去問で点が取れない…」
そのときに、「なぜできなかったのか?」を分析していますか?
成績が伸びない生徒は、自分の弱点を客観的に分析できていないケースがほとんどです。
●「科目」ではなく「単元」で分析しよう
Z会が実施した受験生対象の調査によると、「自己分析ができていた生徒ほど、共通テスト・二次試験での得点が安定していた」という結果が出ています。
特に注意したいのは、「数学が苦手」などの大雑把な認識に留まってしまうことです。
本当にすべきは、「数列の漸化式の立式が苦手」「英語長文の設問処理で時間がかかる」などの細かな単元・スキルレベルの分析です。
●模試や過去問は“診断ツール”
模試や過去問は「本番の予行練習」ではなく、「弱点を炙り出す診断ツール」として活用すべきです。
特に記述模試では、解答解説を丁寧に読み、正解と自分の解答の違いを徹底的に分析するクセをつけましょう。
●チェックポイント
-
間違えた理由を言語化しているか?
-
自分の得意・不得意な単元を明確に説明できるか?
-
模試の解説を復習に活用しているか?
おわりに:伸びない原因は「やり方」にある

成績が思うように伸びないのは、あなたの“能力”ではなく、“やり方”に問題がある可能性が高いです。
今回紹介した3つの特徴――
-
課題をこなすだけの「作業」勉強
-
再現性のない抽象的な計画
-
弱点を正確に把握していないこと
これらに1つでも当てはまっていたら、すぐに勉強の仕方を見直してみましょう。
最後に、代々木ゼミナールの指導要綱にもあるように、「合格は戦略で勝ち取るもの」です。
闇雲に頑張るのではなく、“分析と修正”を積み重ねることが合格への最短ルートになります。あなたの努力が、正しい方向に進みますように。