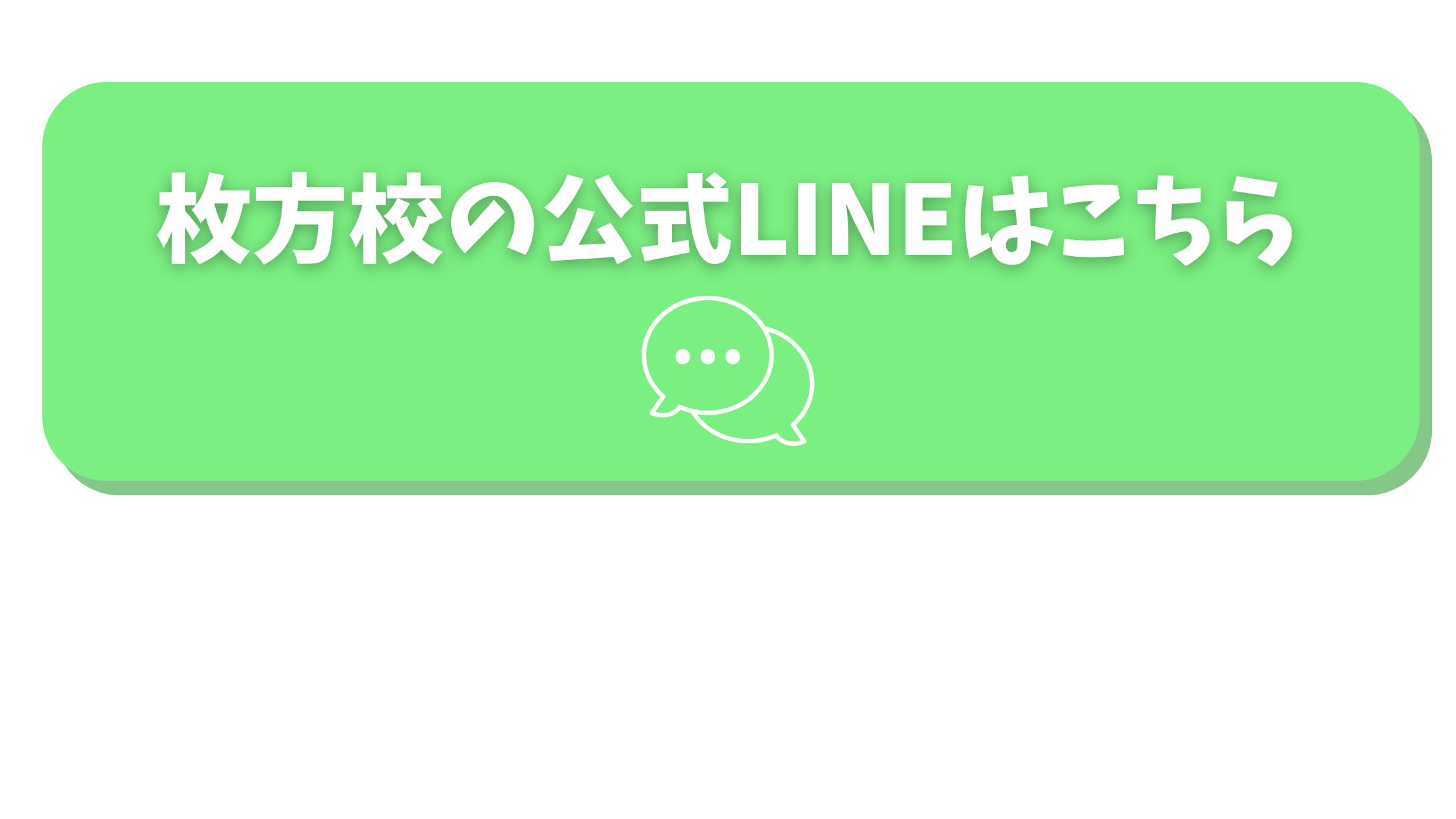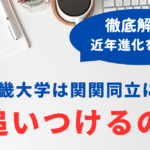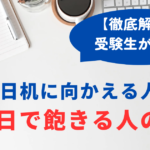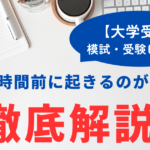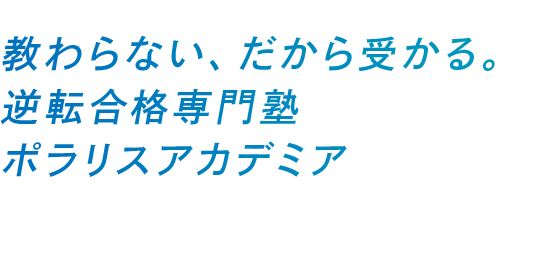関関同立特化!科目別「夏にやるべきこと」徹底解説
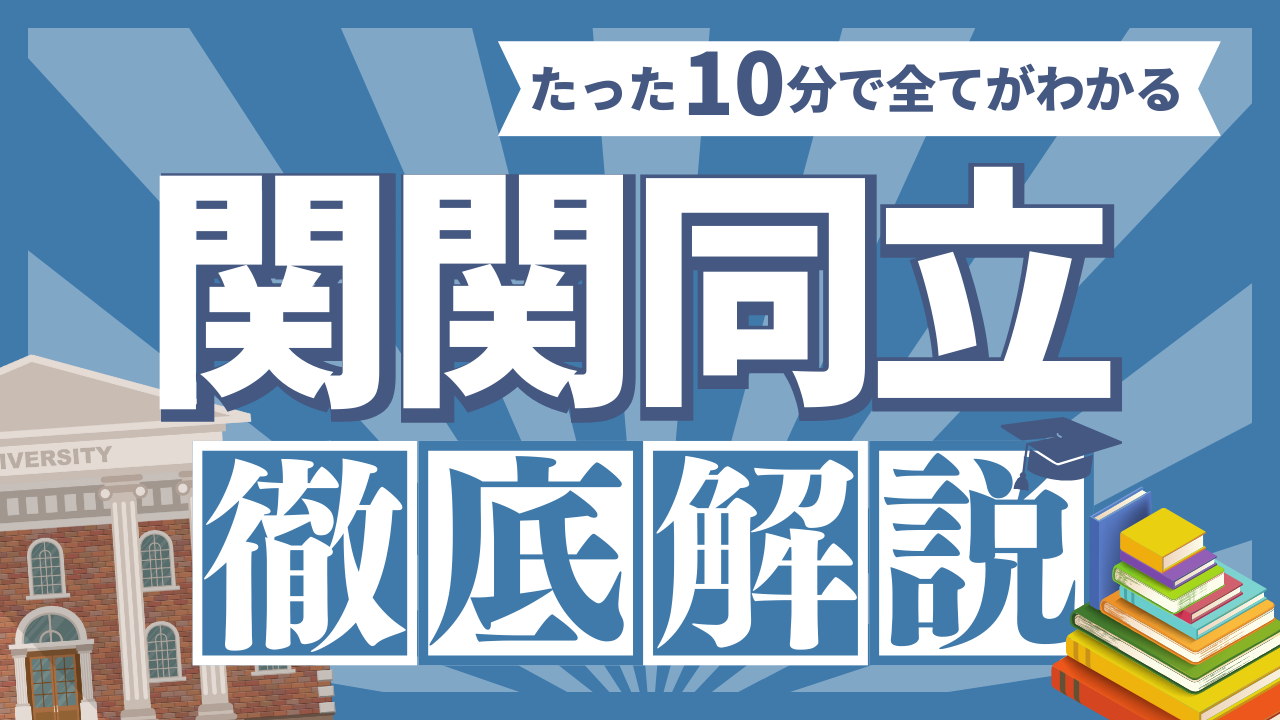
関関同立の入試は、大学ごとに異なる傾向を持つため、
志望校の出題傾向を詳細に把握し、それに基づいた対策を講じることが合格への近道となります!
今日は枚方校の生徒も志望することが多い、関関同立について
徹底解説した記事となっています!
永久保存版なので重要なところはスクショしたり印刷して
夏休みの受験勉強の際に活用して下さい!

英語:合格の鍵を握る最重要科目
関関同立の入試において、英語は配点が高い傾向にあり、
合否を大きく左右する最重要科目です 。
夏休み期間は、英語をメインに学習を進め、社会などの選択科目は2〜3割程度の時間配分とすることが推奨されます 。
関関同立の英語入試は、長文読解が大きなウェイトを占め、速読力と正確な読解力が強く求められますが、
リスニング問題は基本的に出題されないという特徴があります 。
- 単語・熟語:
- 目標: 8月中には「システム英単語帳」「英単語ターゲット1900」「必読英単語LEAP」「速読英単語」といった
ベーシックな単語帳を一冊ほぼ完璧にすること 。多義語や類義語の習得も目指し、即答レベルを目指す 。 - 熟語: 「速読英熟語」「解体英熟語」「英熟語ターゲット1000」といった熟語帳を8月の時点で6割程度覚えることを目標に、単語と並行して進める 。
- 目標: 8月中には「システム英単語帳」「英単語ターゲット1900」「必読英単語LEAP」「速読英単語」といった
- 文法・英文解釈:
- 文法: 基礎が不足している場合、「大岩のいちばんはじめの英文法【超基礎文法編】」などを1〜2周し、早急に基礎を固める 。
その後、「Next Stage」「Vintage」「英文法問題 Solution①」「英文法ポラリス【1 標準レベル】」といった4択問題集を最低3周行い、知識の定着を図る 。
既に何周かした場合は、文法の単元がシャッフルされた「英文法ファイナル問題集」や「英文法ポラリス ファイナル演習」で応用力を養う 。 - 英文解釈: 複雑な構文を正確に読み解く力を習得するために、「肘井学の読解のための英文法」を8月半ばまでに3周することが推奨される 。
その後、「入門英文問題精講」に進むのが効果的 。
また、「ポラリス英文解釈1」を用いて、一文一文のSVOOC(主語・動詞・目的語・補語・修飾語)を正確に把握する練習を週に10〜15章のペースで進める 。
音読やスラッシュリーディング、和訳演習を通じて、複雑な英文を正確に理解する力を養う 。
- 文法: 基礎が不足している場合、「大岩のいちばんはじめの英文法【超基礎文法編】」などを1〜2周し、早急に基礎を固める 。
- 長文読解:
- 目標: 7月から本格化させ、8月には他の教材と並行して取り組む 。
共通テストのリーディングで65%程度の得点率を目指すことが、関関同立合格への足がかりとなる。 - 実践: 「The Rules英語長文2」「英語長文solution2」「ポラリス英語長文1」といった問題集を完璧にすることを目指し、
可能であれば「やっておきたい英語長文」にも着手する 。
週に3〜4題のペースで解き、1題あたりの時間を意識しながら精読と速読のバランスを取る練習を開始する 。
毎日、あるいは隔日で長文に触れる習慣を確立し、時間を測って問題を解き、
徹底的な復習(音読、知らない単語・熟語のチェック、文構造の確認、間違い分析)を行う 。シャドーイングも速読練習に効果的 。
- 目標: 7月から本格化させ、8月には他の教材と並行して取り組む 。
【大学別傾向と対策(英語)】
- 関西大学: 英語の配点が高く、空所補充問題やパラグラフ整序問題、文法の読解知識問題が特徴 。
イディオム・語法を重点的に対策し、量が多いので速読の練習を積む 。長文問題は比較的易しいが、文章量・設問量が多く、問題文が英語で書かれているため、時間配分が鍵 。 - 同志社大学: 関関同立の中で最も難易度が高いとされ、9割近い得点を目指す覚悟が必要 。
長文問題が主体で、言い換え問題や内容一致問題が多く、8個の選択肢から正解を3つ選ぶ問題など、
多くの受験生が苦戦する形式が見られる 。高い単語力が求められる 。
会話文問題も難しい部類に入るが、口語表現はあまり出題されないため、確実に高得点を狙いたい 。 - 立命館大学: 大問1と2が長文問題で、大問1は内容理解中心、大問2は空所補充と指示語中心と、問題傾向が異なる 。語彙・文法的な力を試す挿入問題や類義語を選ぶ問題が出題される 。
特に大問4では文法的な知識を問う挿入問題が8題ほど出題される傾向にあり、難易度は高くないため、素早い解答で満点を狙うべき 。長文は非常に長いため、読み慣れる練習が不可欠 。 - 関西学院大学: 英語全体的に難易度が高く、文法・イディオムからの出題が中心で、英文中の空所補充のウェイトが高い 。
並べ替え問題が特徴的で、文法問題の配点が高い 。
多くの分野から問題が出題され、受験生の総合的な英語知識が問われる 。
過去問演習を通じて、得点が最大化されるような解き方の順番やペース配分を見つける必要性が高い 。文法問題は難しくないものが多いため、合格を目指すならば満点を狙いたい 。
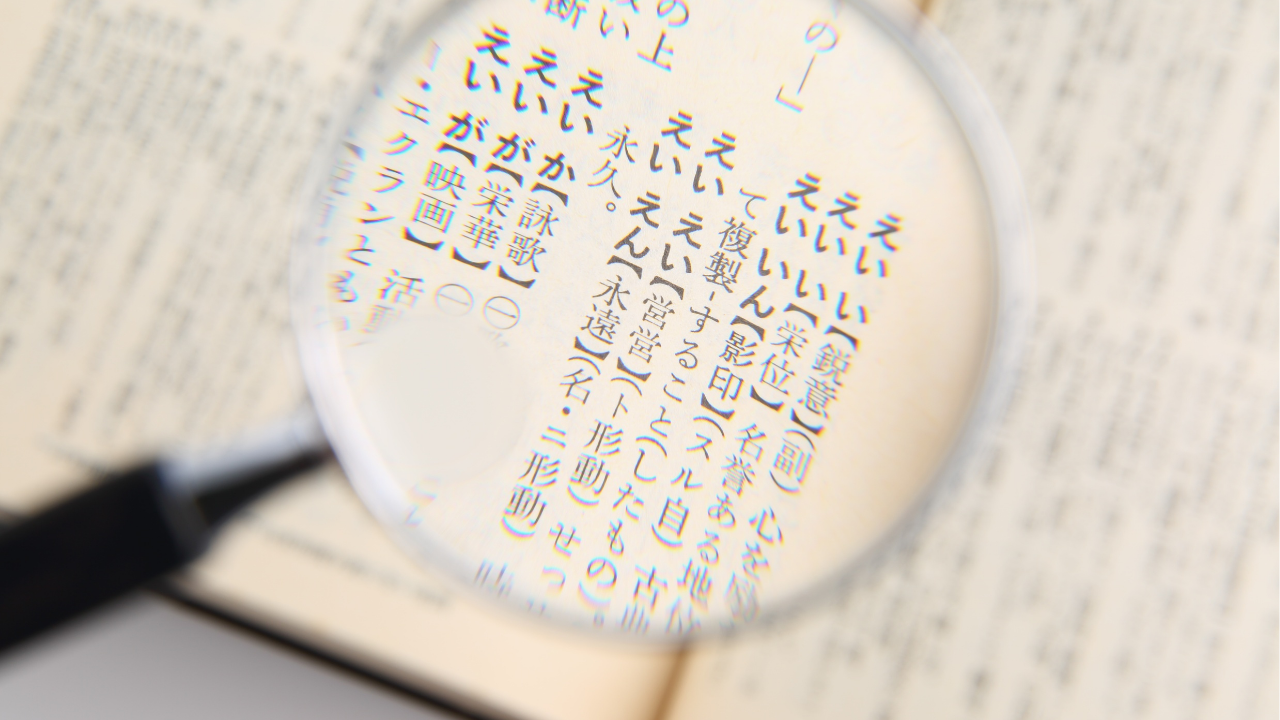
国語:現代文と古文のバランス
国語の学習は、夏以降の本格的な演習や過去問対策が始まる前の「準備期間」として重要です 。
夏休みも基礎固めを徹底する最後の機会となります。
現代文が苦手な場合は、まず現代文を優先的に伸ばす必要があります。
現代文の読解力は、すべての科目の文章理解に通じる基礎的な能力だからです 。
一方で、現代文が得意な場合は、1日30分ほど古文に触れるなど、古文に重点を置くことが推奨されます 。
- 現代文:
- 習慣化: 毎日一題は必ず読む習慣をつけ、読むスピードを速め、論理展開を意識して解く練習を積む 。
- 速読力: 文字数が多い文章をゆっくり読んでいる時間はないため、縦読みに慣れるために夏休み中は読書をしてみるのも良いでしょう。
週に1冊のペースで4冊ほど読めば、読解スピードの向上が期待できます 。 - 要約力: 文章を読んでも内容が分からない場合は、要約の練習が効果的です。
文章全体を100字〜200字ほどでまとめたり、段落ごとに内容に合ったタイトルを付けたりすることで、要約力が高まります 。 - 語彙力: 評論で頻出する専門的な語句の意味をしっかりと理解しておくことが重要です。
「ことばはちからダ」や「現代文キーワード読解」で重要キーワードを押さえておきましょう 。
特に同志社大学志望者にとって、「現代文読解力の開発講座」は有効な教材であり、8月中に最低1周は終えることを目標にしましょう 。
- 古文:
- 基礎の徹底: 単語と文法の知識が学習のベースとなります 。
助動詞や敬語の完璧な暗記が特に重要です 。夏休みまでに文法を一通り覚えきることが目標です 。
文法が曖昧なまま長文に進むと、文法問題だけでなく、文章のニュアンスも正確につかめなくなり、古文全体が解けなくなる可能性があります 。 - 暗記法: 暗記する際は、「覚えた」と思ったら一度参考書を閉じて暗唱できるか確認する練習を取り入れましょう 。
古文単語は「古文単語315」などを活用し、ゴロで覚えることも効果的です 。 - 読解への移行: 単語と文法がある程度固まっている場合は、8月には長文読解に入り、
読解に関するインプット参考書を完璧にすることを目指し、余力があれば実際に読解問題を解いてみましょう 。
- 基礎の徹底: 単語と文法の知識が学習のベースとなります 。
【大学別傾向と対策(国語)】
- 関西大学: 最大の特徴は、本文に傍線部が引かれていない点 。
本文を読み進めながら問題を解く必要があり、現代文は共通テストのように漢字問題と読解問題で構成され、最後に記述問題が出題される 。
古文は平安時代の文章がよく出題され、現代語訳の記述問題が出るが、難易度はそれほど高くない 。
対策としては、現代文は過去問演習を通じて出題傾向に慣れること、古文は基本的な単語・文法を徹底することが第一歩 。
時間配分は現代文40分、古文30分を目安に、過去問演習を通じて自身に最適な配分を体得することが推奨される 。 - 関西学院大学: 出題傾向に統一性がなく、日程によってマーク式と記述式が異なるため、
必ず確認が必要 。現代文は漢字問題・空欄補充・傍線部問題が中心で、他の3校と比べて比較的容易 。
古文も基礎が分かっていれば解けるレベルで、素直な問題が多い 。
対策としては、現代文は問題集に取り組み、古文は基礎知識を積み上げてから、問題演習を繰り返すことが推奨される。 - 同志社大学: 毎年記述問題が出題されるのが特徴で、配点も大きいため、ここを落とすと大きな失点に繋がる可能性がある 。
現代文は様々なテーマから長文が出題されるが、問題自体は素直なため、難易度はそれほど高くない 。
古文は典型的な受験古文が出題され、基礎的な文法・単語・読解に慣れておくことが大切 。
例年、問題形式はほぼ固定されているため、演習を積み重ねることが対策の第一歩となる。 - 立命館大学: 現代文は幅広いジャンルからの出題があり、時間配分が難しいのが特徴 。随筆や小説も出題されるため、
評論文だけでなくこれらの対策も忘れずに行う必要がある 。
古文の難易度は関関同立の中でも最高峰とされ、解ける問題と解けない問題の取捨選択が重要 。
過去問演習を通じてコツを掴み、単語や文法だけでなく文学史まで網羅しておくことが推奨される 。
選択科目:効率的な学習と配点戦略
選択科目は、英語をメインに学習しつつ、1日2〜3時間を目安に勉強時間を確保することが推奨されます 。
夏休み期間中に、主要な選択科目の通史を1周することを目標とします 。
一問一答形式での学習だけでは点数が伸び悩む可能性があるため、
通史の参考書を用いてインプットとアウトプットを両立させる学習を意識することが重要です 。
- 日本史・世界史:
- 目標: 8月末までに通史を1周することを目安に学習を進める。
- 実践: 一問一答を回すだけでなく、「山川の教科書 詳説世界史B」や「山川の世界史用語集」といった
通史の参考書を用いて、流れの中で知識を定着させる学習が効果的 。
インプットした後は問題集を使って積極的にアウトプットを行い、夏休み中は基礎固めまでを目標とする 。 - 日本史傾向: 文化史の出題比重が高い 。遺跡や寺院などの文化遺産の位置を地図上から選択する問題も多く、
資料集での地図確認が重要 。史料問題も毎年出題される 。
全体としては教科書レベルの基本知識を問う問題が多く、8割以上の高得点を目指すべき 。
頻出時代は平安・江戸・明治(特に江戸・明治)。 - 世界史傾向: 特有の問題形式や特に変わった出題はない 。
文学史や近現代史が問われることもあるため、しっかりと対策が必要 。
書き取り問題も出題されるため、漢字などの書き取りも常に意識して学習する 。
中国史は徹底的にやり込むと良い 。文章の正誤問題が出題され、正しい知識が求められる 。
設問数が約50問と多いため、ハイペースで解いていく必要がある 。
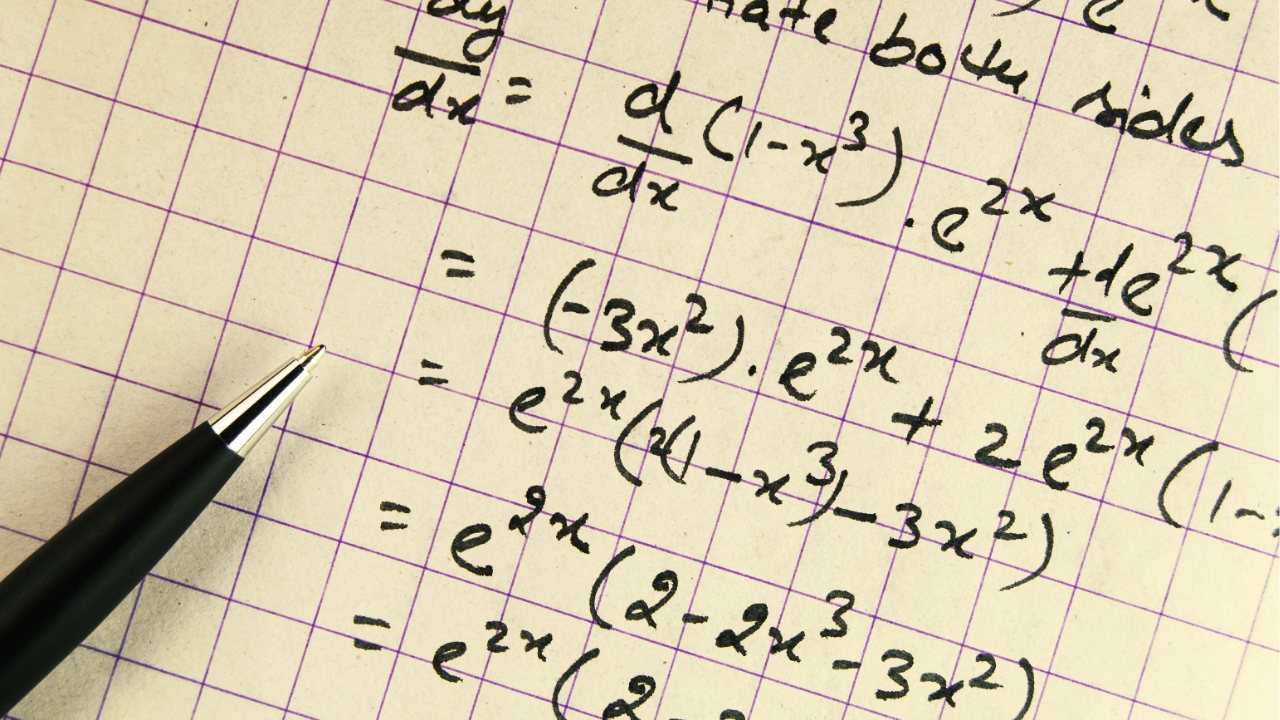
- 数学:
- 全体像: 関関同立の数学は、全体的に標準レベルの問題が中心で、
難問とされる問題は比較的少ない傾向にある 。
そのため、基礎・基本をしっかりと身につけることが合格に繋がる 。教科書の例題や参考書の例題を中心に、解法の手順を確実に習得し、
分野横断的かつ偏りのない学習を心がけ、苦手分野をなくすことが重要 。計算力が重視される問題も多いため、日頃から落ち着いて丁寧に計算練習を積み重ねることが求められる 。
試験時間は60分と決して長くはないため、時間配分も意識した演習が必要 。
- 関西大学(理系): 理系のほとんどの学部で数学が満点のうち36%以上の割合を占め、合格最低点が得点率45-50%であることを考えると、
数学でどれだけ得点できるかが合否を大きく左右する 。
大問は4問構成で試験時間は100分。大問1,3が記述式、大問2,4が穴埋め式 。
近年の出題分野には偏りがあり、微分積分、複素数平面、漸化式、三角関数、ベクトル、確率、数と式などが頻出 。 - 関西学院大学: 理系型は標準レベル、文系型はやや易しい問題が多く、難問は比較的少ない 。
記述式の問題は微分法・積分法が中心で、関数の増減・極値、面積・回転体の体積が頻出 。
計算力が重視されるが、グラフや図形が重要な役割を果たす問題も多く、図形的センスも求められる 。文系型では小問集合形式が2題あり、二次関数・確率、三角比・三角関数、数列ベクトルなど広範囲から出題される 。
- 全体像: 関関同立の数学は、全体的に標準レベルの問題が中心で、

- 理科(物理・化学・生物):
- 物理:
- 全体像: 問題文が長い傾向にあるが、問われる内容はそこまで難解ではなく、
教科書レベルの公式の使い方や意味、自分で導出できることなどが問われる 。全問空欄補充問題が多く、論述を行う必要がないため、比較的時間に余裕がある試験とされる 。
ただし、問題文が長く状況設定が複雑になる傾向があるため、普段の演習から時間を意識し、ハイペースで解く練習が必要 。 - 頻出分野: 力学と電磁気はほぼ毎年出題されており、
この2分野の対策は必須 。特に力学では単振動の問題、電磁気では電場と磁場に関する問題が頻出 。
波動・原子の単元は典型問題が多い傾向にある。 - 対策: 教科書レベルの知識に加えて標準問題が解けるようになっていると十分に高得点を狙える 。
人名や物理法則の名前のような語句を答えさせる問題も出題されるため、教科書などで確認しておく 。
- 全体像: 問題文が長い傾向にあるが、問われる内容はそこまで難解ではなく、
- 化学:
- 全体像: 理論化学が中心で、全体の約70%を占める 。
無機化学や有機化学と絡めて出題されることが多い 。
問題の難易度は標準的であり、正しい勉強をしていれば合格点がほぼ確実に取れるとされる 。 - 頻出分野:
- 理論化学: 計算問題の出題頻度が高く、化学平衡・熱化学・気体の状態方程式・溶解度積が頻出 。計算は素早く正確に行う訓練が必要。
- 無機化学: 単独出題は少なく、理論化学と絡めて出題されることが多い 。
気体の製法や金属イオンの性質、工業的製法など基礎内容で失点しないよう、
知識の整理と理論化学との関連付けが重要 。化学反応式を正確に書けるように練習しておく 。 - 有機化学: 構造決定問題が中心で、特にエステルの加水分解が頻出 。元素分析の結果を踏まえて解く問題が多いため、ここで間違えると大きな失点に繋がる 。単純な暗記ではなく、官能基ごとの性質や化学変化による変化の前後を理解することで、暗記量を減らし、確実な得点に繋げることができる 。
- 全体像: 理論化学が中心で、全体の約70%を占める 。
- 生物:
- 全体像: 幅広い分野から出題され、1つの大問に複数の分野がまたがって問題が作成される傾向がある 。
知識系統の問題とその場で考える問題がメインだが、独特な正誤問題や計算問題、
グラフから読み取る問題も出題される 。ただ知識を丸暗記するだけでなく、
なぜそうなるのかを理解していることが求められる 。 - 大学別傾向と対策:
- 関西大学: 遺伝の範囲からの出題が頻出だが、出題範囲は広いため、
各分野から満遍なく学習する必要がある 。
細かい知識が要求される論述や煩雑な計算問題には十分な対策が必要 。 - 関西学院大学: 論述問題が中心で、難易度が高い 。
文字数制限がないため、自分の頭の中にあるものを簡潔にまとめて文章にする能力が求められる 。
過去に行われた実験の内容について問われる問題も特徴的で、
有名な実験については資料集も活用して細かいところまで確認しておくことが推奨される 。 - 同志社大学: 実験考察問題は問題レベルが高く、問題文の文章量も多いため、一筋縄ではいかないことが多い 。
- 立命館大学: 出題形式は多岐にわたるが、いずれも基本〜標準レベルの難易度であり、
問題の癖も見られないため、まずは教科書や「基礎問精講」などの
基礎〜標準レベルの問題集でしっかりと基礎固めをしておく 。共通テストの過去問を解くのも有効 。
- 関西大学: 遺伝の範囲からの出題が頻出だが、出題範囲は広いため、
- 全体像: 幅広い分野から出題され、1つの大問に複数の分野がまたがって問題が作成される傾向がある 。
- 物理:

まとめ:夏休みを制する者が受験を制す!最終チェックリスト
関関同立合格を目指す上で、夏休みは学力の飛躍的な向上と、合格への確固たる基盤を築くための決定的な期間です。
この期間をいかに戦略的に、そして効率的に過ごせるかが、最終的な合否を大きく左右します。
最後に、この夏を最高の「伸びしろ」期間にするためのチェックリストです。
- □ 漠然とした不安を「伸びしろ」と捉え、前向きなマインドセットを持てているか?
- □ 模試や過去問で現状を分析し、「何を」「どこまで」やるか具体的な目標を設定したか?
- □ 限られた時間で最大の効果を出すため、「捨てる勇気」を持ち、優先順位を決めたか?
- □ 「時間」ではなく「質」を重視し、アウトプット中心の学習を意識しているか?
- □ 規則正しい生活リズムを確立し、計画的な休憩とリフレッシュを取り入れているか?
- □ 集中できる学習環境を整え、隙間時間を有効活用しているか?
- □ 英語を最重要科目と位置づけ、単語・文法・解釈・長文の基礎固めと演習を進めているか?
- □ 国語は現代文の読解力と古文の基礎知識(単語・文法)を徹底し、バランスよく学習しているか?
- □ 選択科目は通史を1周し、インプットとアウトプットを両立させているか?
- □ 志望校の科目別出題傾向を把握し、それに基づいた対策を講じているか?
夏休みは、あなたの人生を豊かにするための「スタートライン」です。
この期間の disciplined(規律正しい) かつ戦略的な学習が、関関同立合格への道を確実に切り拓くでしょう。
この記事を読んで、自分だけでは計画を立てるのが難しい、
もっと具体的なアドバイスが欲しいと感じた方は、
ぜひ一度ポラリスアカデミアの無料受験相談にお越しください。
あなたの現状を分析し、最適な学習プランをご提案します。