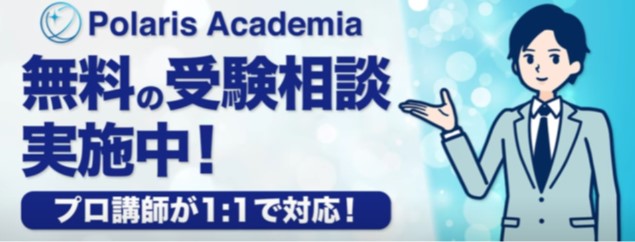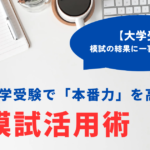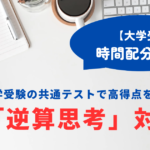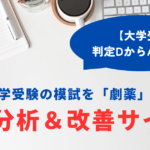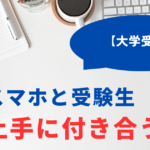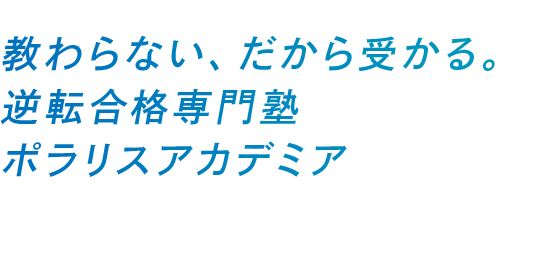自分にあう勉強方法の探し方
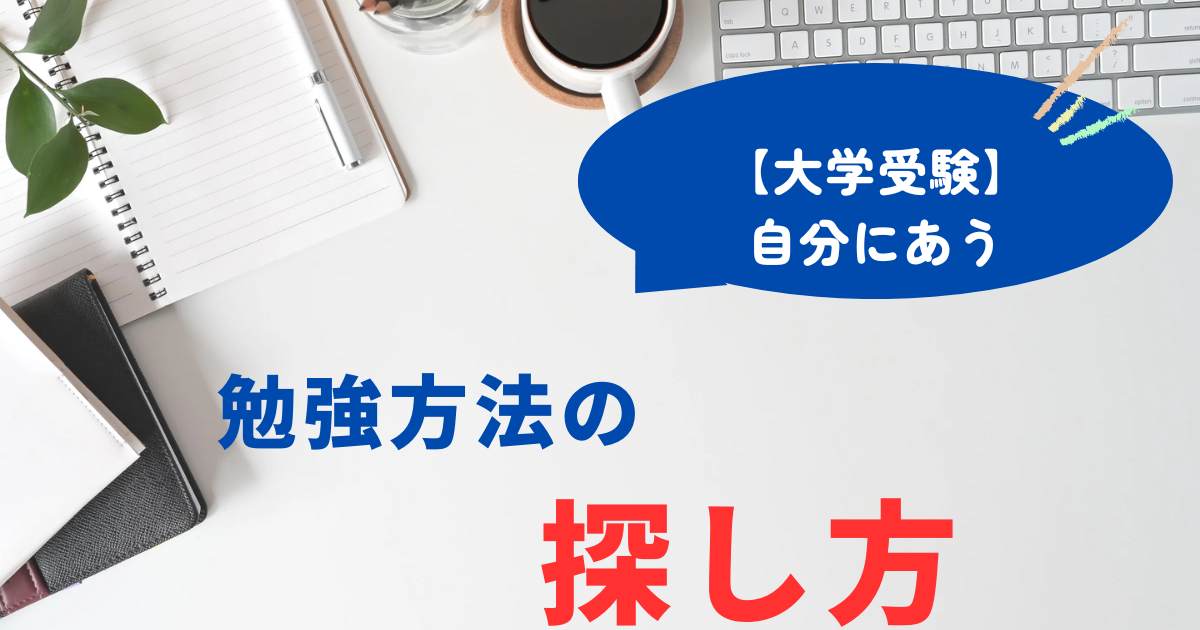
「友達は集中して長時間勉強できるのに、自分はすぐ飽きちゃう…」
「参考書を読んでも頭に入ってこないのは、勉強方法が間違ってるのかな…?」
こんな風に、自分の勉強方法に悩んでいませんか?
「効果的な勉強方法」と聞くと、多くの人は「長時間机に向かうこと」や「ひたすら問題を解くこと」を想像しがちです。
でも、人にはそれぞれ個性があるように、「自分に合う勉強方法」も人それぞれ違うんです。
私はこれまで多くの受験生を指導してきましたが、志望校合格を掴み取った生徒たちに共通していたのは、「自分に合った勉強方法」を早い段階で見つけ、それを愚直に実践していたことです。
彼らは、周りのやり方を盲信するのではなく、自分自身の特性と向き合い、最適な学習スタイルを確立していました。
今回は、私自身の経験と、多くの合格者、そして私が指導してきた生徒たちが実践し、見事学習効率を飛躍的に高めた「自分に合う勉強方法の探し方」を徹底解説します。
皆さんが本当に「合格」に繋がる、自分だけの最高の勉強方法を見つけられるよう、具体的なステップでお伝えしていきますね!
なぜ「自分に合う勉強方法」を見つけることが重要なのか?

「自分に合う勉強方法」を見つけることは、受験勉強の効率と、ひいては皆さんの学習の継続性、そして合否に直結する非常に重要なプロセスです。
- 学習効率の最大化: 人間の脳は、情報を処理したり記憶したりする方法に個人差があります。自分に合った方法で学習することで、脳が最も効率的に機能し、学習内容の理解度や定着率が飛躍的に向上します。
- モチベーションの維持: 合わない勉強方法で無理を続けると、集中力が続かず、ストレスが溜まり、学習自体が苦痛になってしまいます。自分に合った方法なら、「できた!」という成功体験を積み重ねやすく、学習へのモチベーションを高く維持できます。これは、心理学における「自己効力感」を高めることにも繋がります。
- 挫折の防止: 受験勉強は長丁場です。途中で「自分には向いてない」と挫折してしまう受験生も少なくありません。自分に合った方法を見つけることは、学習を無理なく継続するための最大の原動力となります。
- 「非認知能力」の育成: 自分の特性を理解し、最適な学習方法を試行錯誤するプロセスは、問題解決能力や自己調整能力といった「非認知能力」を育むことにも繋がります。これは、大学入学後や社会に出てからも非常に重要なスキルです。
多くの教育研究機関が、個々の学習スタイルに合わせた教育が、学習効果を高めることを提唱しています。
大切なのは、流行りの勉強法を真似することではなく、「自分にとっての最適解」を見つけることなんです。
自分に合う勉強方法を見つける!5つのステップ
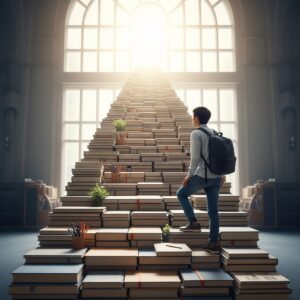
それでは、具体的に「自分に合う勉強方法」を見つけるための「探し方」を、5つのステップで解説していきます。
ステップ1:「現状」を徹底的に客観視する
自分に合う勉強方法を見つける第一歩は、今の自分の勉強方法と、そこから生まれている「結果」を徹底的に客観視することです。
- なぜ重要なのか?
- 漠然と「成績が上がらない」と感じるのではなく、「具体的に何が問題なのか」を特定することで、改善すべき点が明確になります。
- 自分自身を「実験台」と捉え、冷静に分析する視点を持つことで、感情に流されずに最適な方法を探せるようになります。
- 具体的な実践方法
- 「勉強ログ」をつける: 1〜2週間、以下の項目を記録してみましょう。
- 勉強時間: どの科目を何時間勉強したか。
- 勉強内容: 参考書を読む、問題を解く、暗記するなど、具体的に何をしていたか。
- 集中度: 勉強中の集中度はどれくらいだったか(例:5段階評価)。
- 感情: 楽しい、つらい、眠いなど、勉強中の感情。
- 休憩の頻度と内容: どんな休憩をどれくらい挟んだか。
- 模試やテストの結果を分析:
- 「どの科目・分野で点数が取れていないか?」
- 「間違えた問題の原因は何か?(知識不足、理解不足、ケアレスミス、時間不足など)」
- 「得意だと思っていた分野でも点数が取れていないか?」
- 「自分の感覚」を言語化する:
- 「どんな時に集中できるか?(例:朝、静かな場所、音楽を聴きながらなど)」
- 「どんな時に集中が途切れるか?(例:眠気、スマホ、単調な作業など)」
- 「どんな学習が楽しい、あるいは苦痛だと感じるか?」 これらの情報を、具体的にノートに書き出してみましょう。
- 「勉強ログ」をつける: 1〜2週間、以下の項目を記録してみましょう。
ステップ2:「学習スタイル」のタイプを知る
人間の学習スタイルにはいくつかの分類があります。自分の傾向を知ることで、自分に合った勉強方法のヒントが見つかります。
- なぜ重要なのか?
- 心理学や教育学の研究では、視覚、聴覚、身体感覚など、人によって情報を効率的に取り入れるチャネルが異なることが示されています。自分の優位なチャネルを知ることで、それに合った学習方法を選べます。
- これらのタイプ分類はあくまで目安ですが、自分を理解するための一つのツールとして活用できます。
- 代表的な学習スタイル(VARKモデルなど)の例と活用法
- 視覚型(Visual):
- 特徴: 図、グラフ、イラスト、映像などで情報を視覚的に捉えるのが得意。
- おすすめ勉強法: 参考書の図やイラストを重視する、色ペンで線を引く、マインドマップを作る、動画授業を活用する、板書を綺麗にまとめる。
- 聴覚型(Auditory):
- 特徴: 音や話を聞いて情報を記憶するのが得意。
- おすすめ勉強法: 音読する、講義を録音して聞く、耳で聞く参考書を活用する、友達と教え合う、自分自身で内容を口に出して説明する。
- 読書/書字型(Read/Write):
- 特徴: 文字を読んだり書いたりすることで情報を整理し、記憶するのが得意。
- おすすめ勉強法: 参考書を熟読する、重要な部分をノートに書き写す、要約を作る、過去問の解答を記述して覚える、単語帳を書いて覚える。
- 運動感覚型(Kinesthetic):
- 特徴: 体を動かしたり、実践したり、体験を通して学ぶのが得意。
- おすすめ勉強法: 実際に問題を手を動かして解く、実験動画を見る、体を動かしながら暗記する、ウォーキングしながら音声教材を聞く、立って勉強する。
- 視覚型(Visual):
- 活用法: ステップ1の自己分析と照らし合わせ、「自分はどのタイプに近いか?」を考えてみましょう。複数のタイプを合わせ持つ人もいます。
ステップ3:「仮説」を立てて「小さく試す」
自分の現状と学習スタイルを理解したら、「こんな勉強方法なら自分に合うかも」という「仮説」を立て、それを実際に「小さく試してみる」ことが重要です。
- なぜ重要なのか?
- 頭で考えるだけでなく、実際に試してみることで、その勉強方法が自分に合うかどうかを体感できます。
- いきなり全てを変えるのではなく、「小さく試す」ことで、リスクを抑え、合わなかった場合でもすぐに別の方法に切り替えられます。これは、科学実験における仮説検証プロセスと同じです。
- 具体的な実践方法
- 仮説を立てる: ステップ1と2を踏まえ、「数学は視覚型だから、図を多く使った参考書で、色分けしてノートにまとめながら勉強してみよう」「英語の単語は運動感覚型だから、部屋を歩きながら音読で覚えてみよう」など、具体的な勉強方法の仮説を立てましょう。
- 期間を決めて試す: 1週間〜2週間程度の期間を決め、その期間はその仮説に基づいた勉強方法を実践してみましょう。
- 「勉強ログ」を継続: 引き続き勉強ログをつけ、集中度や感情の変化を記録しましょう。
ステップ4:「効果」を測定し、「改善」する
試した勉強方法が、本当に自分に合っていたのか、効果があったのかを客観的に評価し、次の改善に繋げることが重要です。
- なぜ重要なのか?
- 感覚だけでなく、データに基づいて効果を測定することで、本当に効果があった勉強方法を特定できます。
- 効果がなかった場合は、何が原因だったのかを分析し、次の仮説を立てるための貴重な情報となります。これは、PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回すことにも繋がります。
- 具体的な実践方法
- 勉強ログの分析: 記録した勉強ログ(集中度、感情など)を見返し、仮説を試した期間とそれ以前を比較してみましょう。
- 「この方法で勉強した時に、集中力は上がったか?」
- 「前よりも嫌だと感じなくなったか?」
- 小テストや問題集の進捗:
- 「この方法で勉強した分野の理解度は上がったか?小テストの点数は?」
- 「問題集の進捗は早くなったか?」
- 「なぜうまくいったのか/いかなかったのか」を分析:
- うまくいった場合: 「なぜこの方法が自分に合ったのか?」その理由を言語化し、他の科目にも応用できないか考えてみましょう。
- うまくいかなかった場合: 「何が問題だったのか?(難しすぎた、退屈だった、情報量が多すぎたなど)」その原因を特定し、次の仮説に活かしましょう。
- 新しい仮説を立てる、あるいは継続する: 分析結果に基づき、次の新しい勉強方法の仮説を立てるか、効果があった方法をさらに深掘りして継続するかを判断しましょう。
- 勉強ログの分析: 記録した勉強ログ(集中度、感情など)を見返し、仮説を試した期間とそれ以前を比較してみましょう。
ステップ5:「継続」と「進化」!最適な方法を確立する
自分に合った勉強方法は、一度見つけたら終わりではありません。皆さんの学力や興味の変化に合わせて、常に「見直し」と「進化」をさせていくことが重要です。
- なぜ重要なのか?
- 受験期を通じて、皆さんの知識レベルや苦手分野、そして集中力のリズムなどは変化していきます。それに合わせて勉強方法も柔軟に調整していくことで、常に最適な学習効率を維持できます。
- このプロセス自体が、皆さんの「自己調整学習能力」を鍛え、「学び方」を学ぶという一生モノのスキルを身につけることに繋がります。
- 具体的な実践方法
- 定期的な見直し: 模試の前後や、区切りの良い時期(月ごとなど)に、ステップ1〜4のプロセスを改めて実行し、今の自分に最適な勉強方法であるかを確認しましょう。
- 新たな方法の探求: ネットや友達から新しい勉強方法の情報を得たら、すぐに取り入れるのではなく、まずはステップ3のように「小さく試す」ことから始めましょう。
- 「自分だけの参考書」を作る感覚: 自分に合う勉強方法は、まるで自分だけのオリジナル参考書を作るようなものです。常にアップデートし、最高の教材を完成させていく感覚で取り組みましょう。
- 「完璧主義」にならない: 全てを完璧にこなそうとせず、8割程度の効果で十分と割り切る潔さも大切です。
まとめ:「自分に合う」は「最高の武器」になる!

受験生の皆さん、勉強方法は、他人から与えられるものではありません。
それは、皆さん自身が「自分と向き合い、試行錯誤し、見つけ出すもの」なんです。
そして、「自分に合った勉強方法」は、皆さんの学習効率を劇的に高め、モチベーションを維持し、挫折することなく受験勉強を乗り切るための「最高の武器」になります。
今回ご紹介した「現状分析」「学習スタイル理解」「仮説と試行」「効果測定と改善」「継続と進化」という5つのステップは、私自身の経験と、多くの合格者、そして私が指導してきた生徒たちが実践し、見事学習効果を高め、夢を叶えた方法です。
さあ、今日から「自分に合う勉強方法」探しを始め、自信を持って学習に取り組み、志望校合格を掴み取りましょう!
大学受験で悩むすべての受験生へ

ポラリスアカデミア南千里校では無料受験相談を実施しています!
志望校から現状を逆算し、「あなただけのオリジナル合格計画」を作成します。
「今の自分を変えたい!」
「合格までの計画を立てたい!」
と少しでも思うことがあれば、南千里校でお話を聞かせてください!
連絡先はこちらから登録できます!
今ならなんと!
10月12日(日)にあの吉村学長が南千里校で1:1の個別受験相談をしてくれます!
詳しくはこちら!
指導歴12年の校舎長があなたの逆転合格をサポート

少しでもポラリスアカデミア南千里校に興味がわいた方は、
無料の受験相談に足を運んでいただけると嬉しいです。
今までの経験から、あなたにあった最適な学習プランを探っていきます!
ポラリスアカデミア南千里校では、尾崎校舎長が無料受験相談をしています!
「合格に向けて自分にあった勉強法を教えて欲しい!」
「E判定だけど京阪神、医学部、関関同立に逆転合格したい!」
「勉強しているのに成績があがらない!」
といった、質問に一つ一つ丁寧に答え、
あなたの志望を現実にする勉強方法や勉強の戦略を提案いたします!!
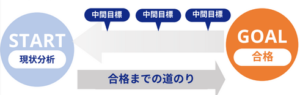
また、
「そもそも何を勉強すればいいかわからない…」
「今まで勉強をサボってきてしまった…」
「もう受かる気がしない…」
といった、勉強に関わるどんな小さなお悩みでも構いませんので、
ぜひ相談してください!
お申し込みは、
下記の無料受験相談フォームにご入力いただくか、
南千里校(070-5361-0669)に直接お電話ください‼