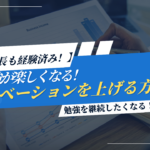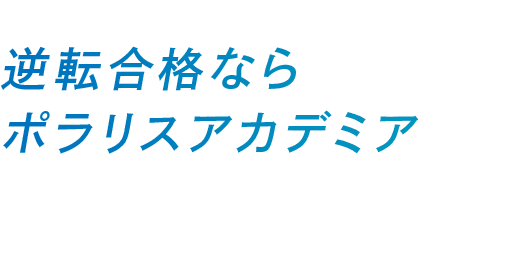志望校の選び方|偏差値やブランドではなく、「意味」で選ぶ
大学を選ぶとき、多くの人は「どこに行くか」を考える。
けれど、本当に大事なのは「そこで何をするか」だ。
偏差値、ネームバリュー、なんとなく…そんな基準で決めてしまうと、後悔につながりやすい。
自分にとって、その大学に行く意味があるのか。そこを突き詰めることが、後悔のない進路選びにつながる。
1. 大学は「目的」ではなく「手段」
「なぜ大学に行くのか?」
この問いにすぐ答えられないなら、まずは立ち止まったほうがいい。
たとえば、
・医師や教師などの資格が必要だから大学に行く
・学びたい専門分野がある
・就職に有利な学歴がほしい
・幅広い選択肢を残しておきたい
といった理由があるなら、大学進学は意味のある選択になる。
逆に、明確な目的もないまま進学すると、時間もお金もムダになってしまう。
大学は「何かを成し遂げるための手段」でしかない。目的が先にあるべきだ。
2. 環境は人を変える
大学での4年間は、これまでとは違う新しい環境に身を置く時間になる。
だからこそ、「どんな場所で、どんな人たちと過ごすか」がとても大きな意味を持つ。
たとえば、学生の雰囲気はどうか。
活発なタイプが多いのか、落ち着いた人が多いのか。
キャンパスが都会にあるのか地方にあるのかでも、生活の仕方や出会うチャンスは変わってくる。
校風や教授陣のスタンス、先輩たちの卒業後の活躍なども、環境を判断する材料になる。
自分がどんな4年間を送りたいのかを想像しながら選ぶと、ミスマッチを避けやすくなる。
3. 「とりあえず大学へ」は危ない
やりたいことが決まっていないから、とりあえず大学へ。
この考え方は一見無難に見えるけれど、実は一番リスクが高い。
迷っているなら、無理に大学に進む必要はない。
たとえば、ギャップイヤーを取って海外に行ったり、バイトやボランティアで経験を積んだりするのもひとつの道。
専門学校で手に職をつけるのもいいし、思い切って何かに挑戦してみるのも悪くない。
大学は「何かをやりたい人」にとっては良い選択肢だけれど、目的がはっきりしないまま進学しても、得られるものは少ない。
4. 偏差値ではなく、「学びの中身」で選ぶ
偏差値が高いから良い大学だと思われがちだけど、それだけでは判断できない。
自分が本当に学びたいことが、その大学にあるかどうか。
それが、選ぶうえで一番大事なポイントになる。
大学のパンフレットや公式サイトでカリキュラムを確認してみよう。
自分の興味に合った授業があるか、どんな教授がいるか。
ゼミや研究室の実績、在学生の活動なども見ておきたい。
大学は「学ぶ場所」だからこそ、何をどう学べるかをしっかり見ておくべきだ。
5. 学費という“投資”を冷静に考える
大学進学には数百万単位の費用がかかる。
それが将来的に回収できる見込みがあるか、現実的に考えておく必要がある。
学費に見合うだけの学びや就職実績があるのか。
奨学金を借りる場合、卒業後何年かけて返すことになるのか。
家計への負担も含めて、家族ともよく話し合っておきたい。
進学は「払えるかどうか」ではなく、「その金額に見合う価値があるかどうか」で考えたほうがいい。
6. 自分の足で確かめる
ネットの情報やパンフレットだけで判断するのは危険。
実際に足を運んでみて、雰囲気を体で感じることが大切だ。
オープンキャンパスに参加して、授業や施設、在学生の様子を見てみる。
できれば学生と直接話して、生の声を聞いてみるといい。
その大学がある街も歩いてみて、「ここで4年間過ごせるかどうか」を感じ取ってみよう。
頭の中だけで考えるのではなく、現地に行って自分の直感を確かめることが、最後の決め手になる。
7. 「行きたい大学」ではなく、「行くべき大学」を選ぶ
進学先を決めるとき、つい「憧れ」や「ブランド」に引っ張られがちになる。
けれど本当に見るべきなのは、そこに行く意味があるかどうか。
自分の目的や価値観に合っているかどうかが最優先だ。
以下のチェックリストを使って、自分に問いかけてみよう。
- 大学に行く目的は明確か?
- その大学の環境で、自分は成長できそうか?
- 「とりあえず」で選んでいないか?
- 学びの中身をちゃんと調べたうえで選んでいるか?
- 学費と将来の見通しを冷静に考えたか?
- 実際に足を運び、自分に合うと感じたか?
最後に
大学は「合格するための場所」ではない。
行くこと自体が目的になっているなら、その選択は間違っているかもしれない。
自分の目で見て、頭で考えて、「自分にとって本当に意味のある大学」を選んでほしい。